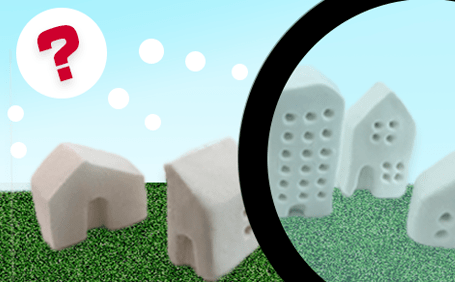住宅ローンの債務者変更はできる?可能なケースや手続きは?

そもそも変えることはできるのか、住宅ローンの債務者を変更する際にはどうすればいいのか悩む人も少なくないと思います。今回は債務者変更ができるケースや手続きの方法などを解説します。
記事の目次
住宅ローンと債務者と不動産の名義人の違い

住宅ローンの債務者とは
債務者とは、お金を借りた人のことを指します。住宅ローンの債務者とは、金融機関からお金を借りて、返済する義務を負う人のことです。
債務者は、住宅ローンを完済しなければなりません。また、契約時に結んだ返済期間や金利などの条件を守る義務があります。
もし、債務者が返済を怠ると、金融機関は強制執行をおこなうことができます。強制執行とは、債務者の財産(住宅)を差し押さえ、ローンの返済に充てることです。
住宅ローンにはさまざまな種類があり、一人が債務者となって連帯保証人をつける場合もあれば、複数人が債務者となる連帯債務もあります。連帯債務で住宅ローンを組むと、一人が債務者となる住宅ローンと比べると、契約関係が複雑になるため、注意が必要です。
不動産の名義人とは
不動産の名義人とは、土地や建物などの不動産の所有者のことです。不動産を新たに取得すると、法務局で不動産の登記をおこない、登記事項証明書に所有者名が記載されます。
不動産の登記をしないと住宅ローンを組むことができません。住宅ローンの債務者と同様に、単独名義になる時もあれば、複数人で購入をすれば複数人が名義人となることがあります。
複数名義になる際は、購入時の負担割合に応じて持分割合を決める必要があります。
負担割合と持分割合が異なると、贈与税の課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。
住宅ローンの債務者変更は原則できない

住宅ローンの債務者変更は原則としてできません。なぜなら、住宅ローンは、金融機関が債務者の返済能力や信用力を評価したうえで契約します。もし変更を認めれば、金融機関にとって貸し倒れのリスクがあります。そのため、途中で審査を受けていない人に変更することを原則として認めていません。住宅ローンを契約する際には、債務者の変更ができないことを理解したうえで、決めるようにしましょう。
住宅ローンで債務者変更できる可能性があるケース

住宅ローンの債務者変更は、原則としてできませんが、以下の5つのケースでは変更できる可能性があります。ここで挙げているのは、あくまで可能性があるケースです。詳しく知りたい方は金融機関に相談しましょう。
離婚する時
離婚する際、住宅ローンの債務者が変更できる可能性があります。具体的には次のようなケースです。
- 単独名義の名義人が家を出る
- 住宅ローンをペアローンで契約している
夫が住宅ローンを契約していて、離婚後は妻が住宅に住み続ける場合には、債務者変更が認められる可能性があります。ただし、金融機関が妻に返済能力があると判断する時のみとなります。
また、住宅ローンをペアローンで契約していた場合にも、共有名義ではなく単独名義への変更、つまり債務者の変更が認められる可能性があります。なぜなら、ペアローンは一方が家を出た時点で契約違反となってしまうためです。しかし、こちらも名義人が家を出る時と同様、新しい債務者に返済能力があると判断された場合に限ります。
債務者に経済的な理由がある時
債務者に経済的な理由がある場合にも、債務者の変更が認められる可能性があります。
住宅ローンの債務者を変更することで、住宅ローンの返済義務を新しい債務者に引き継ぎます。
この場合も、金融機関に新しい債務者に充分な返済能力があると認められる必要があります。詳しくは後述しますが、贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。事前に税務者や税理士に相談しましょう。
親が亡くなり住宅ローンを相続する時
通常、相続の場合、団体信用生命保険の保険金で一括返済するため、返済義務自体がなくなり、債務者を変更する必要はありません。しかし、団体信用生命保険に加入していなかった場合には、返済義務も引き継ぐことになります。この場合には、債務者の変更が認められる可能性があります。
住宅ローンの返済は、長期に渡り、精神的・経済的にも負担がかかります。団体信用生命保険に加入せずにローンを組む場合には、相続人に返済義務が及ぶ可能性があることを理解したうえで、よく考えて判断しましょう。
親子リレー返済を利用する時
親子リレー返済を利用する時には、債務者の変更が認められる可能性が高くなります。
親子リレー返済とは、親子で契約し、二世代に渡って住宅ローンを返済していく方法です。この場合、親から後継者である子どもに引き継ぐタイミングで債務者変更をおこないます。ただし、子どもに充分な返済能力があること、住宅ローンを契約している物件に住んでいることなどの条件があります。金融機関によっても条件が異なるため、確認しておきましょう。
遺産分割をやり直す時
遺産分割後にトラブルがあり、やり直す時も住宅ローンの債務者変更ができる可能性があります。
例えば、はじめの遺産分割で長男が引き継いだ場合。しばらくして長男が病気になった、障がいを負ったなどで住宅ローンの返済が難しくなった時には、遺産分割協議をやり直し、他の兄弟を債務者にすることができます。繰り返しますが、新しい債務者に安定して返済できる能力があることが前提です。
しかし、遺産分割協議には、相続人全員が書面で合意する必要があります。必要書類の準備、金融機関の承諾など、時間がかかることを理解しておきましょう。
住宅ローンの債務者を変更する方法

前章で挙げたケースであれば、住宅ローンの債務者を変更できる可能性があります。具体的な流れや必要な書類について理解し、スムーズな手続きができるようにしましょう。
金融機関に相談する
まずは債務者変更ができるのか、金融機関に相談しましょう。変更するためには、金融機関の同意が必要です。金融機関は新しい債務者の信用状況や返済能力を確認したうえで、変更を認めるか判断します。
債務者変更に必要な書類
債務者を変更するためには、下記の書類が必要となります。
- 登記済権利書
- 住民票
- 印鑑証明書
- 登記原因証明情報
- 代理権限証書(専門家に依頼する場合)
- 固定資産評価証書
相続で変更する時には、遺産分割協議書が必要になります。また、離婚で債務者を変更する時には、これらの他に、下記の書類が必要になる場合があります。
- 住宅に関する財産分与の状況
- 離婚協議書
金融機関や債務者を変更する理由によって、必要な書類が変わるため、事前に確認するようにしましょう。
住宅ローンで債務者を変更する時の注意点

住宅ローンの債務者を変更する際、気をつけなければならない点が3つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
贈与税が課される場合がある
離婚により住宅ローンの債務者を変更した際、贈与税が課される場合があります。例えば、夫の稼ぎにより、住宅をはじめ、預貯金や株式などの資産があったとします。それらの財産を全部妻に分けると、税務署に多すぎると評価され、受け取るべき財産を超える部分に贈与税が課される可能性があります。
住宅ローン契約者を新しくすることは債務者にできない
すでに住宅ローンを契約している人を、新しく債務者として立てることはできません。住宅ローンは、契約者が自宅に住む前提で成り立っています。住宅ローンを契約しているということは、すでに自宅があるということです。その人が住む目的で、2軒目の住宅ローンを借りることはできません。債務者を変更する際には、住宅ローンを契約していない人を選ぶようにしましょう。
住宅ローンの債務者と不動産の名義人が一致する必要がある
住宅ローンの債務者を変更する際には、不動産の名義人も同時に変更する必要があります。不動産の名義を勝手に変更すると、住宅ローン規約に契約違反することになり、最悪の場合は一括返済を求められる可能性があります。金融機関から、不動産の名義変更に関して承諾を得ることは難しい場合がありますが、無断でおこなうとリスクが高いです。事前に金融機関に相談するようにしましょう。
手続きに費用がかかる
住宅ローンの債務者を変更する際には、不動産の名義も変更する必要があります。具体的には次の3つの費用がかかります。
登録免許税:固定資産税評価額×税率
税率は名義変更の理由によって異なります。
| 名義変更の理由 | 税率(軽減税率後) |
|---|---|
| 相続 | 0.4% |
| 贈与 | 2% |
| 財産分与 | 2% |
| 売買 | 2% |
必要書類の取得費用
不動産の名義変更に必要な書類を取得する際に、手数料がかかります。また、必要な書類は名義変更の内容によって異なります。
| 証明書 | 手数料 |
|---|---|
| 住民票 | 300円 |
| 登記簿謄本 | 600円 |
| 固定資産評価証明書 | 200〜300円 |
| 印鑑証明書 | 300円 |
司法書士への報酬
名義変更をおこなう際、司法書士に依頼する場合は、報酬も支払う必要があります。相続による名義変更であれば6万円〜10万円程度です。事務所や手続きの内容によっても異なるため、事前に確認しましょう。
債務者変更ができなかった時の対処法

住宅ローンの債務者変更は、金融機関にとって貸し倒れのリスクがあるため、断られる可能性があります。債務者変更ができなかった場合には、次の対処法が考えられます。
具体的にどういった方法なのかを見ていきましょう。選択肢を知ることで、ご自身に合った対処法を選ぶことができます。
住宅ローンを借り換える
債務者が変更できなかった時の対処法として、住宅ローンを借り換える方法があります。借り換えるとは、現在借りている住宅ローンを、新しく借りる住宅ローンの借入金で返済することです。例えば、夫から妻へ債務者を変更したいとします。そのためにはまず、夫名義で借りている住宅ローンを完済しなければなりません。そこで、妻を債務者として新しく住宅ローンを借り入れ、その借入金で夫名義のローンを返済します。これで、債務者を妻に変えることができます。
しかし、妻を債務者として新しく住宅ローンを組むためには、金融機関で審査を受ける必要が出てきます。返済能力や信用力がなければ、ローンを組めない可能性もあります。少しでも審査が通りやすくなるよう、住宅ローン以外のローンを完済する、頭金を多めに入れるなどの対策をおこないましょう。
親族間売買によって債務者を変更する
親族間売買によって債務者を変更できます。親族間売買とは、親子または夫婦の間で買主・売主となり、売買をおこなうことです。例えば、元夫から元妻に債務者を変更したい時、元妻が新規に借り入れた住宅ローンで、今契約している住宅ローンを完済し、住宅を買取ることができます。
ただし、元妻が住宅ローンを契約できるかは金融機関の審査に委ねることになります。
また、相場の価格よりも低い価格で売買をおこなうと、低額譲渡とみなされ、贈与税が課される可能性があります。リスクを理解したうえで、おこなうようにしましょう。
まとめ
住宅ローンの債務者変更は、原則としてできません。しかし、離婚や現在の債務者の経済的理由などによって、変更できる可能性があります。個々のケースによって異なるため、金融機関に相談しましょう。また、変更できなかった場合には、住宅ローンの借り換えや親族間売買といった方法があります。いずれも、新しい債務者が新規で住宅ローンを借りることになるため、審査を受ける必要があります。住宅ローン以外の借り入れを返済する、頭金を多く入れるなど、対策をしましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ