連帯債務と連帯保証の違いは?住宅ローンを借りる前に知っておくべきことを解説

そこで本記事では、連帯債務と連帯保証の違いをわかりやすく解説し、選び方のポイントをご紹介します。
記事の目次
連帯債務と連帯保証の違い

連帯債務と連帯保証はよく似た言葉で、いずれも借金に関わる責任を示していますが、内容は異なります。端的に説明すると、連帯債務は「共同の責任」で、連帯保証は「補助的な責任」です。では、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
連帯債務
連帯債務は、複数の債務者が共同で借金の返済を負います。つまり、すべての債務者が返済の義務を負い、もし一人が返済できなくなった場合、他の債務者がその分も代わりに返済しなければなりません。一つのローン契約に対し、お互いが返済を分割して進めているイメージが当てはまるでしょう。
例えば、夫と妻が共同で3,000万円の住宅ローンを組み、月々の返済額が10万円の場合、夫と妻のそれぞれが5万円ずつなど分担して返済します。もし、それぞれの収入に差がある場合はこの限りではありません。例えば、夫の年収が400万円、妻の年収が600万円など収入に差がある場合、夫婦の合計収入に対する割合を計算して、負担額を調整します。このケースでは、夫が40%、妻が60%の割合で収入を得ているため、それぞれの債務持分もこの比率になるでしょう。しかし、夫が急な病気や失業で返済できなくなった場合には、妻が全額の10万円を返済する義務を負います。この点で連帯債務は、返済義務がより重く共有される形といえるでしょう。
一方、連帯債務には収入を合算して審査を受けられるメリットもあります。例えば、夫が年収400万円、妻が年収300万円の場合、合算すれば年収700万円として審査を受けられるかもしれません。そのため、より高額の借り入れが可能になる可能性があります。ただし、この仕組みは双方が安定した収入を持っている場合に限り有効で、いずれかが収入を失った場合のリスクは高くなります。
連帯保証
連帯保証は、主債務者(借り入れをおこなった人)が返済できない場合に、保証人が代わりに返済義務を負う仕組みです。保証人は、主債務者の代わりに返済をおこなう責任を負い、主債務者の返済が滞った場合に返済をしなければなりません。一方、主債務者が返済を継続していれば、保証人が返済する必要はなくなります。
例えば、夫が3,000万円の住宅ローンを借り入れ、妻が連帯保証人になったケース。この場合、夫が毎月返済を続けている間、妻に返済の義務は発生しません。しかし、夫が失業や病気などで返済不能に陥った場合、金融機関は妻に対して未払いの全額を請求できます。この仕組みは、主債務者が返済を果たせない「万が一」の事態に備えるためのものです。
連帯債務のメリットとデメリット

連帯債務は、複数の債務者が一つの借り入れに対して共同で返済義務を負う形態で、特に共働き夫婦に利用価値のある選択肢です。では、具体的にどのようなメリットおよびデメリットがあるのでしょうか。
連帯債務のメリット
連帯債務の主なメリットは以下です。
- 収入合算し予算を上げられる
- 住宅ローン控除を夫婦で受けられる
- 共同で資産を所有できる
- 責任を分担できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
収入合算し予算を上げられる
連帯債務では、夫婦など複数の収入を合算して借入額を決定できます。そのため、単独では借りられない高額なローンを組める可能性があり、希望する理想の物件を購入できるかもしれません。例えば、夫の年収が400万円、妻の年収が300万円だった場合。合算して700万円の収入として審査されるため、夫単独では借入上限額が5,000万円だったものが、夫婦で合算すれば7,000万円など上限を上げられる可能性があります。
住宅ローン控除を夫婦で受けられる
連帯債務の場合、各自のローン返済の負担割合に応じて、それぞれ住宅ローン控除を受けられる点がメリットになります。例えば、夫が7割、妻が3割を負担する形でローンを組んでいる場合、それぞれの負担額に応じた控除の申請が可能です。住宅ローン控除が夫婦ともに受けられ、節税効果の恩恵を期待できるでしょう。
共同で資産を所有できる
連帯債務は、資産(住宅)を共同所有する点が前提になります。そのため、夫婦で住宅を購入する場合、双方が所有権を持ち、住宅に対して公平な権利が確保されます。互いに自己の資産として所有し、それぞれが持分割合に応じた資産価値を主張できます。
責任を分担できる
住宅ローンの返済負担を双方で分担するため、ローン返済を負う経済的なプレッシャーが軽減されます。一人でローン全額を背負うよりも、家計全体で計画的に返済を進めるほうが精神的に楽になるでしょう。責任を一人で負わず、協力できる点がメリットになります。
連帯債務のデメリット
連帯債務の主なデメリットは以下です。それぞれの解説も見ていきましょう。
- 債務の連帯責任が重い
- 離婚時の手続きが複雑
- 住宅ローン控除の申請が複雑になる
- リスク管理が難しい
債務の連帯責任が重い
連帯債務では、夫婦のどちらか一方が返済不能になった場合、もう一方が全額を返済する責任を負わなければなりません。例えば、夫が失業や病気で収入を失った場合、妻がすべての返済を続ける必要があるため、経済的負担が重くなる可能性があります。責任を分担して返済義務を負う点がデメリットにもなりえるでしょう。
離婚時の手続きが複雑
連帯債務は、金融機関との契約になるため、夫婦が離婚しても債務は残ります。どちらかが住宅ローンを引き継ぐ場合は、金融機関の承認が必要です。また、住宅を売却してローンを清算する場合でも、売却額がローン残高を下回れば、残りの債務を2人で負担しなければなりません。離婚後も経済的なつながりが残ることで、トラブルに発展する可能性がある点がデメリットです。
住宅ローン控除の申請が複雑になる
住宅ローン控除を夫婦2人分申請でき、負担割合に応じて控除を受けられる点はよいですが、申請の複雑さはデメリットです。手続きには各自の所得状況や負担割合を明確に示す必要があり、税務処理を複雑に感じる方も多いでしょう。さらに、収入の多いほうに多くの控除を集中させたい場合でも、連帯債務では各自の割合が固定されるため、柔軟にはできません。
リスク管理が難しい
主債務者が団体信用生命保険に加入していても、連帯債務者が加入できるかは契約によります。万が一、保険に加入ができない契約で、連帯債務者が死亡したり、高度障害を負った場合、残る債務者に全額の返済義務が生じるかもしれません。
連帯保証のメリットとデメリットは?

連帯保証は、主債務者が返済できない場合に、保証人が責任を負う形態です。では、具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
連帯保証のメリット
連帯保証の主なメリットは以下です。
- 連帯保証人は返済を分担しない
- 借り入れと資産管理がシンプルになる
- 離婚時の手続きが連帯債務より簡単である
それぞれの解説も見ていきましょう。
連帯保証人は返済を分担しない
連帯保証人は、主債務者が返済を続ける限り、一切返済する必要がありません。つまり、通常時の生活には影響を与えずに、主債務者を支援できます。
借り入れと資産管理がシンプルになる
資産(住宅など)は主債務者の単独所有になるため、管理や売却時の手続きがスムーズです。保証人の権利や所有割合を調整する必要がなく、家計全体での資産運用が明確になります。
離婚時の手続きが連帯債務より簡単である
夫婦間で住宅ローンの責任を共有しないため、離婚後のローン処理がシンプルです。例えば、保証人を外れる場合、金融機関の同意があれば契約を解除できます。
連帯保証のデメリット
連帯保証の主なデメリットは以下です。それぞれの解説も見ていきましょう。
- 主債務者が支払えなくなるリスクがある
- 保証契約の解除が難しい
- 団体信用生命保険(団信)の保障を受けられない
- 住宅ローン控除の対象外になる
主債務者が返済できなくなるリスクがある
主債務者が失業や病気、事故などで返済不能になった場合、保証人が全額を返済する義務を負います。そうなると、保証人の経済状況に大きな影響を与えるかもしれません。例えば、主債務者の夫が住宅ローンの返済を続けられなくなった場合、保証人の妻が残額すべてを返済する義務が発生します。
保証契約の解除が難しい
保証人の契約を解除するためには、金融機関の同意が必要で、一般的に新たな保証人を立てる必要があります。しかし、離婚や経済状況の変化などで保証契約を見直したい場合でも、簡単に解除はできません。
団体信用生命保険(団信)の保障を受けられない
連帯保証人は団体信用生命保険(以降、団信)の保障は受けられません。団信は、主債務者が死亡や高度障害となった場合に、保険金で残債を一括返済できる仕組みのためです。このリスクを補うには、連帯保証人自身が別途生命保険に加入し、必要な保障を確保するなどの対策が必要になります。
住宅ローン控除の対象外になる
連帯保証人が主債務者に代わって住宅ローンを返済する場合、住宅ローン控除を受けられません。住宅ローン控除は、自分が居住するために購入した住宅に対するローン契約が対象であり、保証人が支払う場合は適用外です。つまり、連帯保証人が支払いを引き継いだ場合、税制上の優遇措置が受けられず、実質的な負担が増します。このような状況を避けるには、主債務者の返済能力を十分確保し、無理のない返済計画を立てなければなりません。
連帯債務と連帯保証の選び方
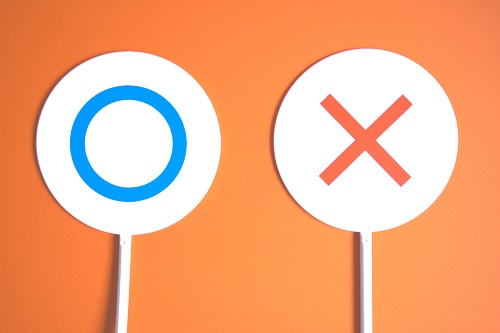
住宅ローンを組み、夫婦で協力して返済していく場合、連帯債務と連帯保証のどちらがよいのでしょうか。夫婦の生活スタイルや将来設計によって選ぶべき返済方法は異なります。では、どのようなケースでどのような返済方法を選ぶとよいかを見ていきましょう。
連帯債務と連帯保証の特徴比較
| 特徴 | 連帯債務 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除 | 2人分 | 1人分 |
| 団体信用生命保険 への加入 |
1人分(※1) | 1人分 |
| 手数料 | 1人分 | 1人分 |
| 所有権 | 持分割合に応じる | 債権者のみ |
| 収入合算 | できる | できない(※2) |
※1 金融機関によっては連帯債務でも団信に加入ができる場合があります。
※2 条件によっては収入合算を利用できる場合もあります。
連帯債務がおすすめのケース
以下に当てはまる夫婦には、連帯債務がおすすめです。
- 将来的にも2人で安定した収入を見込める
- できるだけ予算を広げたい
- 住宅ローン控除を活用したい
具体的にどのような理由で連帯債務がおすすめなのか、以下で詳しく説明します。
将来的にも2人で安定した収入を見込める
連帯債務が成り立つ前提条件として、夫婦双方に安定した収入が見込めることが重要です。例えば、両者ともフルタイムで働き、今後も収入が減少するリスクが低い場合は、連帯債務によって住宅ローンの返済を分担できます。
特に、共働きで収入がバランスよくある夫婦にとって、返済負担を2人で分担する連帯債務はメリットが大きいでしょう。例えば、夫婦のどちらか一方に返済負担が偏ると生活全体のバランスが崩れる恐れがあります。しかし、連帯債務を選ぶと返済の責任を共有し、家庭内での経済的な均衡を保てるでしょう。また、収入が安定していると、ローン返済が滞るリスクが低減し、長期的な計画が立てやすくなります。
できるだけ予算を広げたい
希望の家を購入したいなど、できるだけ予算を確保したい場合も連帯債務を選ぶとよいでしょう。それは、連帯債務を選択すると、夫婦の収入を合算して住宅ローンの審査を受けられるためです。通常の住宅ローン審査では、一人分の収入だけで借入可能額が決定されます。しかし、連帯債務では、夫婦の収入を合わせた金額をもとに審査がおこなわれるため、より高額なローンの承認が得られるかもしれません。
例えば、夫の収入だけでは4,000万円までの物件しか手が届かない場合でも、夫婦の合算収入で審査を受けると、5,000万円や6,000万円の物件も選択肢に入る可能性があります。そうなれば、さらに立地条件のよいエリアや、希望する間取り、大きさなどを選ぶ自由度が広がるでしょう。特に、住環境に妥協したくない場合や、広い住居が必要な場合に効果的です。共働きで収入が安定している場合、このように予算を広げて希望の住宅を手に入れられる点は、連帯債務を選ぶ大きな理由になるでしょう。
住宅ローン控除を活用したい
連帯債務を選ぶと、住宅ローン控除を夫婦それぞれが受けられる点も有利です。住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高に応じて所得税が軽減される制度で、会社員には効果的な節税手段になります。
連帯保証の場合、主債務者しか住宅ローン控除を受けられません。しかし、連帯債務では夫婦双方が住宅ローン控除を申請できるため、控除額が2人分になります。例えば、年間40万円の控除を1人で受ける場合と、夫婦で合計80万円の控除を受ける場合では、長期間にわたる節税効果が大きく異なります。このため、特に共働きで所得がある夫婦の場合は、連帯債務を選ぶほうが所得税や住民税の負担を減らし、家計全体のキャッシュフロー改善が期待できるでしょう。長期的に見ると、節税分の金額が大きな財産形成につながる可能性もあります。
連帯債務は、共働きで安定した収入があり、希望する住宅を購入するための予算を増やしたい場合や、節税効果を最大化したい場合におすすめです。ただし、夫婦それぞれが返済責任を負う形になるため、将来的なリスクを考慮して計画を慎重に立てましょう。
連帯保証がよいケース
以下のライフスタイルや将来の見通しがある場合には連帯保証がおすすめです。
- 専業主婦(主夫)になる
- 離婚した場合の手続きを簡単にしたい
- 夫婦どちらかの収入を住宅ローン返済以外に充てたい
具体的にどのようなケースで連帯保証が有利となるのか、以下に詳しく説明します。
専業主婦(主夫)になる
専業主婦(主夫)になり、今後は働かずに家庭を支える予定がある場合は、連帯保証を選ぶほうがよいでしょう。すると、万が一ローンの返済が滞った際に、主債務者が返済できなくなった時の保証人として返済責任を負う形となります。
例えば、夫婦のいずれかが子育てをしながら専業主婦(主夫)となるケースや、フリーランスとして仕事をしているが、収入が不安定な場合などが考えられるでしょう。専業主婦(主夫)の立場では、ローンの返済を毎月負担するのが難しくなる可能性が高まります。そのため、返済は一方が責任を持つ形にし、返済できなくなった時にのみ保証人が責任を果たすやり方が合うでしょう。この場合、保証人は平常時の負担を軽減できます。
離婚した場合の手続きを簡単にしたい
結婚して住宅ローンを組む際に、将来離婚する可能性があるかを判断するのは困難でしょう。しかし、少しでもそのリスクに備えたい場合は、連帯保証がおすすめです。もし連帯債務を選んだ場合、どちらもローンの返済責任を負うことになります。もし、ローン返済中に離婚した場合、所有権や返済義務が問題になり、再分割や財産分与でトラブルに発展する可能性も。
一方で連帯保証の場合は、どちらか一方が返済責任を持つようになります。そのため、もし離婚を選択した場合でも、ローン返済に関する合意はシンプルです。主債務者が返済を継続できていれば、保証人には金銭的負担は発生しません。離婚にともない、主債務者がローンを完済するか単独名義に切り替えれば、連帯保証人は契約から解放されます。主債務者と保証人の関係は「補助的」なものに留まるため、金融機関との調整も比較的スムーズです。
夫婦どちらかの収入を住宅ローン返済以外に充てたい
夫婦のそれぞれの収入の使い道を明確に分けておきたい場合は、連帯保証が適しています。例えば、夫の給料を住宅ローンや光熱費、妻の給料を貯金や日々の生活費に充てるケース。連帯保証は責任範囲が主債務者に集中しているため、もう一方の収入を自由に運用できる点が有利です。
連帯債務と連帯保証の特徴を理解してライフスタイルに合った方法を選びましょう。
連帯債務と連帯保証の違いに関するよくある質問
連帯債務と連帯保証の違いに関するよくある質問をまとめました。
連帯債務と連帯保証の違いは?
連帯債務と連帯保証は、どちらも借金に関わる責任を示す点で異なります。連帯債務は「共同の責任」です。複数の債務者が借金の返済義務を共有し、どちらかが返済できなくなると、他の債務者がその分を代わりに返済しなければなりません。一方、連帯保証は「補助的な責任」であり、主債務者が返済できない場合にのみ保証人は返済義務を負うことになります。保証人は、主債務者が返済を続けている限り、返済義務は発生せず、主債務者の返済が滞った場合に代わりに返済することになります。
連帯債務のメリットとデメリットは?
連帯債務のメリットは、収入を合算してローンの借入額を増やせる点です。夫婦での合算収入で、高額な物件購入が可能になり、希望に近い住宅を手に入れやすくなるでしょう。また、住宅ローン控除を夫婦それぞれが受けられるため、税制面での節約が期待できます。さらに、住宅を共同で所有し公平な権利が確保され、ローン返済の責任も分担されるため、経済的負担の軽減が期待できるでしょう。
一方、デメリットは、連帯債務によりどちらか一方が返済できなくなった場合、残りの一方が全額を返済する責任を負う点です。離婚した場合も、債務は残るため、ローンの引き継ぎや住宅の売却時に調整が難しくなる点があります。また、住宅ローン控除の申請が複雑であり、税務処理が面倒になるかもしれません。万が一、連帯債務者が団体信用生命保険に加入していない場合、残された債務者が全額返済しなければならないリスクが生じます。
連帯保証のメリットとデメリットは?
連帯保証のメリットは、保証人になっても、主債務者が返済を続ける限り、返済を分担しないため、通常の生活に影響を与えず支援できる点があります。また、資産管理がシンプルで、住宅などの資産は主債務者の単独所有となり、売却手続きもスムーズです。離婚時には住宅ローンの責任が共有されないため、契約解除が比較的簡単な点もメリットでしょう。
一方デメリットは、主債務者が返済不能になると保証人が全額返済する義務を負うリスクがあり、経済状況に大きな影響を与える可能性がある点です。また、保証人の契約を解除する際には金融機関の同意が必要で、簡単に見直せない点や、保証人自身の経済状況が悪化した場合でも責任を果たさなければならないリスクがあります。
連帯債務と連帯保証の選び方は?
住宅ローンの返済方法として連帯債務と連帯保証の選択は、夫婦の生活スタイルや将来設計に応じて選びましょう。まず連帯債務は、夫婦の収入を合算して借入額を増やせるため、希望する住宅の購入が可能になり、共働き夫婦が住宅ローン控除をそれぞれ受けられるなどの節税効果も期待できるでしょう。ただし、連帯債務では夫婦双方が責任を共有するため、離婚時や収入変動のリスクが高まる点に注意が必要です。
一方、連帯保証は主債務者が返済を続ける限り保証人に負担がかからず、専業主婦(主夫)になる場合や夫婦いずれかの収入を住宅ローン以外に使いたい場合に有効です。また離婚時の手続きがシンプルで済む点も利点になります。
それぞれの仕組みの特性を理解し、ライフスタイルや将来の見通しに基づいて最適な選択をしましょう。
まとめ
連帯債務と連帯保証はどちらも住宅ローンで選べる契約方法ですが、それぞれに異なる特性があります。連帯債務は夫婦が平等に返済責任を負い、税制優遇や所有権分割のメリットがある一方で、離婚や収入の減少時にトラブルになるかもしれません。一方、連帯保証は返済責任が主債務者に集中し、片方が保証人となるためシンプルな仕組みでトラブルが少ない反面、税制面での優遇が限られています。家計状況やライフプラン、リスク管理の観点から、自分たちに合った方法を選びましょう。
注文住宅を建てる
物件を探す

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ







