【専門家監修】トレーラーハウスとは?住居にするメリット・デメリットや種類・価格、かかる税金について解説

記事の目次
トレーラーハウスとは

トレーラーハウスとは、けん引によって移動可能な「車両扱いの住まい」で、車台(シャーシ)と居住空間から成る構造が特徴です。アメリカでは「モービルホーム」と呼ばれ、旅や暮らしの自由度を高める選択肢として親しまれています。近年は日本でも、セカンドハウスや事務所、店舗、宿泊施設など多様な用途で導入が進んでいます。水回り設備や断熱性も一般住宅と同等のレベルで、移動性と快適性を両立した住まいといえるでしょう。
キャンピングカーやコンテナハウスとの違い
トレーラーハウスは、けん引されて移動する家であり、自走できるキャンピングカーとは異なります。住まいとしての設備や快適性を重視し、一定期間定置して使用するのが一般的です。一方のコンテナハウスは、建築物扱いとなるため設置後の移動はむずかしいものの、増築や2階建てなど設計の自由度が高いのが特徴です。トレーラーハウスは移動の自由さが魅力であり、用途やライフスタイルに応じた選択が求められます。
トレーラーハウスの種類

トレーラーハウスには、用途やサイズに応じたさまざまな種類があります。なかでも代表的なのが、公道を走行できる「車検付きタイプ」と、広々とした空間を実現できる「大型タイプ」です。それぞれの特徴を解説します。
車検付きトレーラーハウス
車検付きトレーラーハウスは、長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m以内のサイズであれば保安基準に基づいて車検を取得でき、自動車と同じ扱いになります。ナンバープレートが交付されるため、公道を自由に走行できるのが特徴です。必要に応じて移動できるため、仮住まいや事業利用にも便利です。設置場所を変えながら、柔軟に使いたい方に適しています。
大型トレーラーハウス
大型トレーラーハウスは、長さ12m、幅2.5m、高さ3.8mを超えるサイズのもので、車検を取得できないためナンバープレートは交付されません。公道を走行するには、「基準緩和認定書」と「特殊車両通行許可証」の2つの書類を取得することにより公道面を走らせることが可能です。広さを活かして快適な居住空間の確保ができます。
トレーラーハウスの価格

トレーラーハウスは、本体価格だけではなく、運搬料や設置費、税金などを含めて検討しましょう。以下は、おおまかな費用の目安です。
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体価格 | 500~1,000万円 | 種類・サイズにより異なる |
| 運搬費用 | 約20万円~ | 距離や搬入経路によって増減 |
| 設置費用 | 12万円~ | 地盤や勾配によって変動 |
| 車検費用 | 約5万円 | 車検取得にかかる費用 (※車検付きの場合) |
| 税金関係 | 約10万円 | 環境性能割・重量税・自賠責保険など(車両扱い) |
新品の相場は、事務所用で200~1,000万円、居住用で300~1,300万円です。中古品は150~1,000万円程度ですが、流通が少なく品質の見極めが重要です。特に、初めて購入する方は、専門店からの購入をおすすめします。
輸入品は車検に通らない可能性があるため、国産品が安心です。断熱性や内装設備の有無によっても価格は大きく変わるので、ライフスタイルや使用目的に合わせて検討しましょう。
トレーラーハウスのメリット
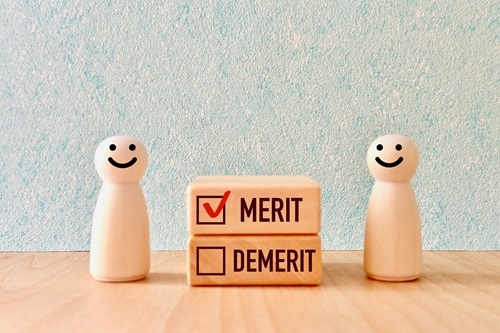
トレーラーハウスには、一般住宅にはない多くのメリットがあります。主な7つのメリットを解説します。
初期費用を抑えられる
トレーラーハウスは基礎工事が不要なため、初期費用を大幅に抑えられます。土地代や建設費が不要な場合もあり、そうなれば必要になるのは車体購入費のみです。エアコンやトイレ、浴室などの住宅設備も設置できるため、コストを抑えながら快適な暮らしの実現できるでしょう。
市街化調整区域にも設置できる
市街化調整区域とは、都市の無秩序な拡大を防ぐために、建物の建築が制限されている地域のことです。通常は住宅を建てられませんが、トレーラーハウスは建築物に該当しないため、行政の承諾を得ることで設置できます。土地価格を抑えつつ拠点を構える手段として有効であり、事務所や仮設住宅としても活用されています。なお、設置前には必ず自治体への確認が必要です。
建築確認申請が不要
トレーラーハウスは、常に移動可能な状態でライフラインの接続も工具を使わずに着脱できる場合、建築物と見なされません。そのため、原則として建築確認申請は不要です。設置手続きの簡略化や時間の短縮につながり、導入のハードルを下げられます。日本トレーラーハウス協会の基準を満たしていれば、自治体が車両として認めるケースも増加しています。
自由に移動ができる
トレーラーハウスはタイヤが付いているため、けん引車を使えば簡単に移動ができます。一定期間使用した後、別の場所に移すこともでき、引越しや拠点の変更にも柔軟に対応が可能です。設置や撤去にかかる費用や手間も抑えられ、中古として再販売する選択肢もあります。
固定資産税や不動産取得税がかからない
トレーラーハウスを車両として扱う場合、本体には固定資産税や不動産取得税がかかりません。これは、地面に定着していない移動可能な構造であるためです。ただし、設置する土地には固定資産税が発生し、住宅用と異なり軽減措置は適用されません。また、車検付きで登録すれば、自動車税などの課税対象となります。税制上の扱いは用途や設置状況によって変わるため、事前確認が重要です。
不要になったら売却できる
トレーラーハウスは建物と違って動産扱いのため、不要になった際に売却しやすいのが特徴です。中古市場での需要も高く、状態がよければ高値で取引されるケースもあります。新車価格1,000万円が、5年後でも500〜700万円で売れる例もあります。移動も容易なため、別の土地での再利用もでき、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる資産といえるでしょう。
自宅敷地内に設置ができる
建築物ではないため、建築基準法に当てはまりません。そのため2世帯住宅として利用したり、趣味部屋や店舗、子供部屋等あらゆる用途に対応できます。
トレーラーハウスのデメリット

多くのメリットがあるトレーラーハウスですが、注意しておきたいデメリットも存在します。以下で、主な5つのデメリットを解説します。
間取りに制限がある
トレーラーハウスは公道を走れる車両としての制限があるため、2階建てや極端に広い間取りにはできません。横幅や高さにも上限があるため、家族全員で暮らす場合には、スペースが不足していると感じることもあるでしょう。ただし、ロフトを設けたり収納を工夫したりすれば、限られた空間の有効利用が可能です。
強風の影響を受けやすい
トレーラーハウスは軽量なため、台風などの強風に対して横転や移動のリスクがあります。特に、開けた場所では風の影響を受けやすく、安全性に不安が残る場合もある点に注意してください。被害を防ぐためには、アンカーでの固定や設置場所の選定、断熱や窓の補強などが有効です。天候に応じて移動できる特性を活かすことも、安全確保につながります。
運搬費がかかる
エンジンを持たないトレーラーハウスは自走ができないため、けん引による移動が必要です。大型のトレーラーハウスは購入者自身で運ぶことが難しく、専門業者に依頼するケースが一般的です。運搬費用は距離や設置環境によって異なりますが、最低でも20万円以上かかります。
一般的な住居と比べて耐久性が劣る
住宅と異なり、トレーラーハウスは移動を前提とした構造です。そのため、強度や耐久性が一般的な住居より劣ります。居住スペースの壁や床は軽量化されており、衝撃や湿気の影響を受けやすくなります。長年使用する場合、風雨や紫外線による劣化も進みやすく、一般住宅と同等の耐久性は期待できないでしょう。使用環境によって劣化のスピードも大きく変わります。
定期的にメンテナンスが必要
長く快適に使い続けるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。雨風にさらされやすく、サビや劣化が進みやすい構造のため、タイヤの状態確認や防錆処理、雨漏り対策などが必要です。メンテナンスを怠ると、雨漏りや電気系統のトラブルが発生するリスクが高まります。住宅同様に、手入れを前提とした運用が求められます。
トレーラーハウスの注意点

導入の自由度が高いトレーラーハウスですが、設置や運用にはいくつかの注意点があります。主な5つの注意点について、以下で解説します。
自治体によって扱いが異なる
トレーラーハウスが車両か建築物かの判断は、自治体ごとに異なります。「随時かつ任意に移動できる状態かどうか」が基準となり、建築物と見なされると固定資産税の対象となる場合もあるでしょう。また、市街化調整区域への設置についても、自治体によって基準や制限が異なるため、設置前には必ず確認が必要です。
車両扱いだと車検が必要となる
車両として扱われるトレーラーハウスは、公道を走行するために車検を受けます。車検に通すには「道路運送車両の保安基準」を満たす必要があり、自動車取得税や重量税なども発生します。また、自治体によっては車検を通しても建築物と判断され、固定資産税の対象になるケースもあります。設置前には、専門家と相談のうえ自治体へ確認をおこないましょう。
車両扱いだと自動車税の対象となる
車両扱いとして登録されたトレーラーハウスは固定資産税の対象外になりますが、一方で自動車税や自動車取得税、重量税の支払いが必要です。税額はサイズや仕様によって異なり、一般的な自家用車と同様に毎年の維持費が発生します。車検付きタイプを選ぶ際には、このような税負担も把握しておきましょう。ただし、大型のトレーラーハウスはナンバーが取得できないため、自動車税はかかりません。
自分で移動させるには、けん引免許が必要なケースもある
車両総重量が750kgを超えるトレーラーハウスを自分で移動させる場合は、けん引免許が必要です。免許を持たずに運転すると、道路交通法違反に該当する可能性があるため注意が必要です。750kg未満であれば免許は不要ですが、住居設備の充実は難しいサイズといえます。大型タイプをけん引する場合は、免許取得か専門業者への依頼が不可欠です。
設置場所によって道路幅や敷地面積の制限がある
トレーラーハウスを設置する際は、搬入経路となる道路の幅や敷地の広さに制限があります。大型タイプは全長10m以上になることもあり、狭い道では運搬できないケースもあるでしょう。また、設置には一定のスペースが求められ、傾斜や障害物の有無も確認が必要です。
【人数別】おすすめのトレーラーハウスを実例で紹介

トレーラーハウスには、暮らす人数やライフスタイルに応じたさまざまなタイプがあります。二人暮らし向けのコンパクトなモデルから、家族で快適に過ごせる広々としたタイプまで、選択肢は豊富です。ここでは、使い勝手や設備、デザイン性にも配慮したおすすめのトレーラーハウスを紹介します。
2人暮らし

パークキュービック6m 12平米/パークキュービックスライドアウト12m 22平米
木目調の外観が目を引くスタイリッシュなトレーラーハウス。内部にはL字型の収納豊富なキッチンと、ゆったり浸かれるバスルームが完備され、2人暮らしにぴったりの設備が整っています。生活動線が確保されており、快適に過ごせる空間です。
お風呂がシャワーブースでよい方は全長6mでも可能ですが、湯船を付けたい場合には、12mのタイプが広々と生活できます。


3人家族~4人家族

パークフェニックス11m 33平米/パークキュービック12m 25平米/パークキュービックスライドアウト12m 46平米
広々としたリビングやダイニングに加え、寝室やバスルームも本格的な仕様で、快適に暮らせるゆとりのある空間が魅力です。モダンな内装とスタイリッシュな外観が調和し、日常生活に必要な設備も充実。家族での長期利用にも安心の設計です。
ちなみに外壁については、木造タイプは山、コンテナタイプは海川などの景観に合います。



トレーラーハウスについてよくある質問
トレーラーハウスは、近年注目されている新しい住まいです。ここでは、トレーラーハウスの基本的な特徴から、メリット、デメリットなど、よくある質問にお答えします。
トレーラーハウスの特徴は?
トレーラーハウスは車両としての機能を備えながら、住宅のように居住できる移動式の建築物です。必要に応じて移動が可能で、内装は一般的な住宅と同等の快適性があります。
トレーラーハウスのメリット・デメリットは?
メリットには土地の制限を受けにくく、比較的安価に導入できることや、住む場所を柔軟に変えられる自由度が挙げられます。一方で、自治体による法的な扱いの違いや、断熱性、気密性など設備面の確認も必要です。
トレーラーハウスを建てる際に気を付けることは?
自治体によっては建築物とみなされる場合があり、固定資産税が発生するケースがあります。また、設置場所の道路幅や敷地面積の制限、ライフラインの確保など、事前に確認すべきことも多いでしょう。設置前に専門家への相談が重要です。
トレーラーハウスは、自分らしい暮らしを実現できる柔軟な住まいです。ただし、導入には法的な知識や立地条件など、慎重な準備が欠かせません。後悔のない選択をするためにも、事前の情報収集と自治体への確認をしっかりおこないましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる



