床下浸水の対処法は?床上浸水との違いや保険・補助金制度などを解説

今回はそのなかで、床下浸水が起きる原因や状況、床下浸水の処理方法や補償、処理時の注意点なども併せて解説します。
記事の目次
床下浸水とは

床下浸水とは、建物の床下空間が水で浸かる浸水被害を指します。建物内部には水が入ってこないので、第三者的には比較的軽微な被害とイメージされがち。しかし、実際は床下浸水でも、建物や住人にとっては相当のダメージを負う被害です。
床下浸水の定義
床下浸水の定義では、浸水深が50cm以下であり、建物の床より下の部分まで浸水する状態とされています。そのため、建物が建っている地盤高などが大きく影響し、隣り合う建物でも基礎の高さの違いによって、床下浸水する建物と被害を受けない建物に分かれるケースもあります。
床下浸水の原因と影響
床下浸水の原因のほとんどが大雨です。台風や低気圧の影響により雨が降り続くことで、住宅地の排水が機能しなくなったり、河川の増水により堤防が決壊し川の水が住宅街に流れ込むことで、浸水が起こります。
床下浸水が起きてしまうと、床下空間が湿った状態となり、建物の基礎や地盤、床下に設置された配管や電気設備などに損害を与える可能性も。また、駐車場は住宅よりも地盤が低いため、駐車してある自動車やバイクなどは水に浸かってしまいます。
床下浸水と床上浸水の違い
建物の浸水被害には、床下浸水と床上浸水という2種類があります。ここで、それぞれの違いを確認しておきましょう。
床下浸水は先ほど述べたとおり、浸水深が50cm以下であり、床より下の部分が浸水すること。一方で、床上浸水は50cm以上建物が水に浸かる程度と、国土交通省にて定義されています。簡単にイメージすると、建物の床より下が水に浸かるなら床下浸水であり、建物の床より上が水に浸かってしまうと床上浸水となります。
床下浸水後の処理方法
床下浸水は、建物にさまざまな影響を与えます。湿気やカビの発生、木材の腐食、絶縁材や配線の損傷、さらには地盤沈下などが起こる可能性もあるでしょう。また、湿気やカビのために室内の空気が悪化し、住宅環境の快適性にも悪影響を与えます。したがって、床下浸水してしまった場合には、正常な住宅環境に戻すための掃除や補修が必要です。
床下浸水の被害直後にやっておくべきこと
床下浸水の被害にあった場合には、水が引いた直後に被害状況を撮影しておくようにしましょう。写真撮影は、被災者生活再建支援法に基づいて支援金を受け取るための、「罹災(りさい)証明書」を申請する際に必要です。撮影し終えたら、早急に水抜きをおこないましょう。できるだけ早く水を抜かないと、湿気によるカビや木材の腐食が進んでしまいます。
それぞれについて詳しく説明していきます。
被害箇所の写真撮影
まず、罹災証明書の交付をスムーズにするために、被害状況の写真撮影が重要です。撮影にはポイントがあり、建物の内側と外側の両方を撮影します。
建物の外側は、建物の周囲4面の全景写真を撮影してください。そして、浸水被害にあった個所は浸水した深さがわかるようにメジャーをあてて、全体を撮影する遠景と目盛が読み取れる近景の2パターンを撮影します。
建物の中は、被害にあった部屋ごとに床下が浸水したことがわかるよう、全景と近景の2パターンを撮影します。
罹災証明書の発行

次に、罹災証明書を発行してもらう手続きをおこないましょう。
罹災証明書は、浸水被害にあった際に被害の程度を証明する書類です。被災者が申請をおこなうことで、自治体の職員が被害状況を調査して被害の程度を認定します。なお、罹災証明書の発行は、災害対策基本法により、遅延なく発行しなければならないと定められています。
罹災証明書は、被災者が支援金の支給や保険金を受ける際などに必要であり、床下浸水での申請先は自治体の担当部署となります。申請には基本的に以下の書類などが必要となりますが、自治体によって若干異なるためホームページでよく確認しておきましょう。
- 罹災証明交付申請書(自治体の担当部署またはホームページからダウンロード)
- 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 被害状況がわかる写真や図面
罹災証明書を申請する時期は、できるだけ早く申請をおこなうことが望ましいでしょう。万が一、何らかの理由で代理人が申請する際には、委任状が必要となるので注意してください。
罹災届出証明書の発行
必要に応じて、「罹災届出証明書」の発行申請もおこないましょう。
罹災届出証明書は、先にご紹介した罹災証明書とは異なり、建物全般だけでなくブロック塀や庭の設備、家財道具や自動車の被害を証明する書類です。
罹災届出証明書は被害者が届けることで発行され、自治体による現地調査はおこなわれません。そのため、損害割合の記載がないのが特徴です。
罹災届出証明書は、加入している損害保険や勤務先の補償制度への請求に使用したり、さまざまな被災者支援策を利用する際に必要となります。発行先は罹災証明書と同じ自治体の担当部署であり、申請は罹災証明書と一緒におこなえます。
専門業者へ依頼する場合
床下浸水の被害にあってしまった場合、自分ですべて適切な処理ができる人は多くありません。床下に侵入した水は泥水であり、水分が渇くと土砂が残ってしまいます。また、残った土砂には雑菌も混入していて、衛生面では最悪の状況となります。
床下浸水後の大変な状況を原状回復するには、専門業者に依頼するのがよいでしょう。水を抜いて乾かし、土砂を取り除き消毒や消臭までもおこなってくれます。床下の木材が水によって腐食している場合や、配管が破損しているケースなど、自分でできない範囲については業者に依頼して工事やリフォームをしてもらいましょう。
自分で処理する場合
先ほど述べたように、床下浸水した場合には専門業者に処理を依頼するのがよいですが、被害を受けた家が多い場合、順番待ちになることもあります。ただ、できるだけ早く処理をしないと、床下浸水であっても健康面や住宅の耐久性に影響を及ぼす危険性があります。また、金銭的な理由から、自分で処理を試みる人も少なくありません。
床下浸水の被害を自分で処理する場合は、次の手順を参考におこなってください。
⑴ 準備をする
自分で床下浸水の処理をおこなう際には、服装や道具などの準備を万全にしておきましょう。
床下の泥水は、汚染されている可能性が高いです。そのため、服装は廃棄可能な動きやすい作業服を選びます。長靴でも構いませんが、溜まった水が跳ねることも想定すると胴長を着るのが最適。また、特に気を付けたいのは、泥水に直接触れないことです。厚手のゴム手袋を使用し、もしも薄手のゴム手袋しかない場合は、2重にして作業を開始します。汗を拭うタオルやホコリを防ぐマスク、状況によってはゴーグルが必要になるケースもあります。
床下浸水後の処理は重労働なので、水分補給がすぐにできるよう、近くに水筒やペットボトルを用意しておきましょう。万が一、作業中に泥水が顔にかかってしまった際にも、すぐにきれいな水で洗い流すことができます。
そして、作業開始前には配電盤のブレーカーを落とす感電防止措置が重要です。
そのほか、水をかき出すためのポンプやバケツ、スコップ、雑巾、扇風機などの道具を用意しておきましょう。
⑵ 排水
排水用のポンプがあればベストですが、ポンプがない場合はバケツやスコップなどで泥水をかき出します。泥水の量が少なくなってきたら、スポンジや雑巾などで吸い取ってバケツに絞りだしましょう。泥水が溜まったバケツは、半分程度で外に捨ててください。バケツを一杯にしてしまうと運ぶのに重くなってしまいますし、万が一ひっくり返すと大変です。
⑶ 泥の除去
排水が完了したら、溜まった泥の除去をおこないます。スコップなどで集めて、建物の外に出しましょう。ある程度の泥が堆積していれば、スコップですくうことが可能です。
泥が少ない場合は、水で洗い流します。床下の基礎部分だけでなく、柱などにこびり付いている泥も、水で洗い流しておくことが重要です。泥が残ってしまうと、乾燥して部屋の中に舞い散ることになり、不衛生です。水で洗い流す時は、できるだけ水圧が高く、水流が増すホースの利用がおすすめ。可能であれば、高圧洗浄機で洗い流すのがよいでしょう。
⑷ 床下換気口の掃除
ここまでの処理が完了したら、床下換気口の掃除もおこないます。床下への泥水の侵入口でもあり、外側にはゴミが貼り付いているケースが少なくありません。できることなら、床下に入り、内側から外側に向けて水で洗い流す方法がよいでしょう。無理な場合には、内側にゴミや泥が入らないように掃除してください。床下換気口をきれいにすれば、風の通りがよくなって床下の乾きも早くなります。
⑸ 乾燥
泥の除去が完了したら、床下をしっかり乾燥させなくてはなりません。床下は日光も当たらず、普段から湿った場所です。泥を確実に除去するために水で洗い流しているので、完全に乾燥するまでは約1カ月かかります。その間は、点検孔などのフタを閉めず開けっ放しにしておくことが大切。送風機や扇風機で風をしっかり送れば乾きが早くなります。できるだけ、床下に新鮮な風を送り込みましょう。
⑹ 消毒
最後に、床下が乾いたら、消毒をおこなうことをおすすめします。泥を洗い流してきれいにしており、それなりに時間も経過しているので、消毒は不要という人もいますが、健康被害を防ぐためにも消毒は大切です。ホームセンターで手に入る消石灰(しょうせっかい)を床下に散布するだけで、消毒・殺菌が可能なので、必ずおこなうようにしましょう。
床下浸水を自分で処理する際の注意点
床下浸水を自分で処理するには、かなりの苦労とリスクをともないます。ここまでで何度か触れていますが、床下に侵入した泥水には健康被害を引き起こす細菌が混ざっているため、注意しなければなりません。また、床下の清掃は体力的にも厳しいので、ケガや疲労など身体への負担にも要注意です。
床下浸水を自分で処理する際の注意点について詳しく説明していきます。
時間と労力が必要となる
年齢的にも若く、普段からスポーツなどで身体を動かしている人なら、体力もそれなりにあるでしょう。しかし、そうでない人や高齢者では、なかなか処理が進まないため、時間がかかるだけでなく、大勢のサポートを必要とします。時間と労力、周囲のサポートがなければ、自分で処理をおこなうのは難しいでしょう。
感染症や粉じん被害に注意する
泥水の排水作業や泥の除去作業では、身を守る装備が重要となります。軽微な服装で作業をすると、細菌や有害物質により感染症や粉じん被害にあって重篤な状態に陥る危険性もあります。
また、泥の除去作業では、すでに乾いた泥が土埃となり風に乗って舞い上がるケースも少なくありません。口や鼻から吸い込んでしまったり、目に入ってしまった場合、気管支炎やレジオネラ症に感染するリスクが高くなります。
床下浸水の処理を自分でおこなう場合は、ゴム手袋や防塵マスク、ゴーグルなどの対策をしっかり施すことが重要です。
汚水や汚泥を残さないようにする
床下浸水の処理を自分でおこなった場合、泥水や汚泥を残さないことが重要です。
先にお伝えしているとおり、床下の水が乾くまでには約1カ月もの期間が必要となります。自分で処理をおこなうと、「これくらいで大丈夫だろう」という自己判断で、汚水が少し残った状態で点検孔などのフタを閉めて作業を完了させるケースも見られます。また、床下での態勢が辛いので、汚泥が若干残っていても作業を終えてしまうこともあり得るでしょう。
しかし、床下に汚水や汚泥が残っていると、雑菌が繁殖して柱などの木材を腐らせたり、シロアリの巣ができたりしてしまいます。また、完全に乾かしていないため湿気によって、腐食した柱が配線に影響し漏電の原因を作ってしまうかもしれません。
そのため、泥水や汚泥を少しも残すことなく、きれいに処理する必要があります。
床下浸水を放置した場合の危険性
床下浸水は、部屋まで水に浸かっていないので、床下ならそのまま乾くのを待てば大丈夫だろうと考える人がいるかもしれません。しかし、侵入した泥水は決してきれいな水ではなく汚水です。そのような泥水を処理しないで放置すると、さまざまな悪影響が生じてしまいます。
悪臭やカビが発生する
床下の泥水を放置すると、雑菌によって悪臭やカビが発生します。床下だからと処理を怠ると、日常生活に支障をきたすほどの悪臭に悩まされることでしょう。その結果、改めて床下の処理をすることとなります。
建物の劣化や設備に不具合が起こる
泥水の放置は健康被害に留まらず、建物の劣化や設備などにトラブルを生じさせます。起こり得る建物のトラブルには、以下のようなものがあります。
- 土台や柱が腐食する
- ボルトや金物類などが錆びる
- 床下に電気の配線などがある場合には、漏電の危険性がある
- 断熱材の断熱効果がなくなる
- 湿気によって床材の耐久性が弱くなる
- 柱が腐食して建物自体の耐久性が弱くなる
シロアリなどの害虫が住み着く

カビや細菌が繁殖すると、シロアリやゴキブリなどの害虫や、ネズミなどの害獣が巣をつくります。不衛生な環境が常態化してしまい、ゴキブリやネズミの大量発生でパニックになるケースも珍しくありません。
健康被害が起こる
床下は常に湿度が高い状態にある場所です。そのため、菌の繁殖力は凄まじく、人体への感染リスクが高くなります。カビも尋常ではないほどの量が発生し、カビ菌を吸い込むことでアレルギーや気管支炎、喘息などを引き起こします。
床下浸水の保険や補助金について
床下浸水であっても、業者に依頼すれば処理費は10万円単位で必要になります。また、床材が侵入した泥水によって傷んでしまい、交換を余儀なくされるケースもあるでしょう。あるいは、泥水によって床下の配線をやり直したり、排水設備を修理したりするケースも考えられます。このような費用を、保険や補助金でカバーできるのか確認してみましょう。
床下浸水の処理やリフォームにかかる費用相場
床下浸水の処理を専門会社に依頼した際の費用は、被害の規模によって異なってきます。例えば排水、乾燥、消毒の各作業をセットで依頼すると、費用相場は約20万円~40万円かかるでしょう。これに加えて、床材のフローリングの張り替えが必要なケースでは6畳で約4万円~20万円必要です。
また、床下浸水であっても、石膏ボードや断熱材などが被害を受ける可能性もあるため、専門家によるチェックが必要です。万が一、石膏ボードや断熱材にダメージがある場合は、リフォームするのと同じになります。そのため、石膏ボートや断熱材の取替、廃棄、クロスのやり替えなどで約30万円は必要でしょう。床下浸水時の処理費用やリフォーム代をトータルで考えると、費用は約60万円以上になります。
火災保険の対象となる場合

火災保険に加入していれば、自然災害による被害も補償されます。しかし、火災保険にはさまざまなタイプがあり、水災補償がオプションになっているケースも多いでしょう。もしも水災補償が付帯していなければ、床下浸水時の補償は受けられません。加入している火災保険に、水災補償が付帯しているか確認しておきましょう。
水災補償の支払基準
水災補償が付帯している火災保険であっても、床下浸水では補償の適用条件を満たしていないため、補償を受けられないことが少なくありません。
火災保険の水災補償にて支払われる基準は、以下のようになっています。
- 建物および家財の保険価格の30%以上の損害を受けた場合
- 床上浸水、または地盤面から45cmを超える浸水による損害を受けた場合
いずれかの条件を満たせば補償を受けられますが、床下浸水の場合はハードルが高いといえるでしょう。
水災補償で支払われる金額
火災保険では、あらかじめ定められた金額を上限に損害額が支払われる、実損てん補が基本となっています。床下浸水だと45cmを超えていれば適用となり、再調達価額(損害が生じたものを再築・再購入するのに必要な金額)の15%未満の損害を受けた場合は保険金額×5%(上限100万円)までが補償されます。また、再調達価額の15%以上30%未満の損害を受けた場合は、保険金額×10%(上限200万円)の補償を受けられます。
特約オプションの水災縮小支払特約(定率払)を付けているなら、選択している縮小支払割合に応じて、実際の損害額より縮小して補償を受けることが可能です。縮小支払割合は、70%、50%、30%、15%、5%から選びますが、基本的には15%以上を選択します。
自治体の補助金制度の対象になる場合
ただし、条件がある点に注意しましょう。市区町村なら10世帯以上、都道府県なら100世帯以上など、一定の被害規模を超える必要があります。実際には、深刻な床下浸水の被害に合った場合は市区町村で10世帯以上の浸水被害が起きているケースがほとんどなので、ほぼ適用となるはずです。
賃貸で床下浸水した場合
アパートやマンションなどの賃貸物件の1階に居住していて、床下浸水の被害にあった場合、泥水の排水などの一連の処理は大家さん(貸主)が負担します。万が一、床下浸水にあった場合は大家さんや管理会社に連絡して、被害の処理や建物の修繕をおこなってもらいましょう。
ただし、家財道具などは個人の所有となるため、大家さんでは損害を補償しません。例えば、床下浸水した玄関にて靴箱や自転車などが泥水で使えなくなっても、損害は自分が持つことになります。
すぐにできる床下浸水対策
床下浸水は大雨時に起きる災害であり、あらかじめ自宅が浸水する可能性があるか否かを把握できます。浸水状況がわかっていれば、火災保険の水災補償へ加入するなど、浸水への対策を施すことも可能です。
ハザードマップを確認する
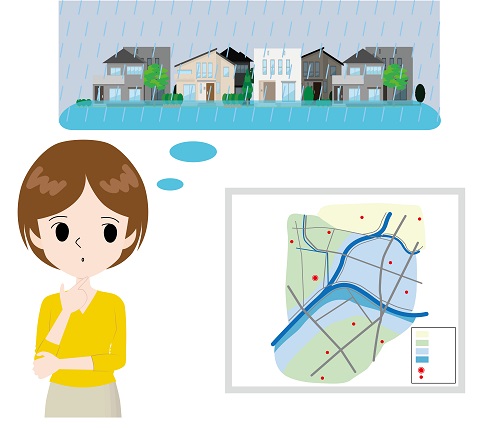
自宅が浸水するかは、洪水ハザードマップを確認すれば簡単に把握できます。また、浸水の深さもわかるため、火災保険の水災補償や家財保険に加入すべきかを判断できるでしょう。
洪水ハザードマップで黄色の着色になっているなら、水災補償は必須です。また、肌色やピンク色に着色されているなら、家財保険への加入もしておくと安心でしょう。
ハザードマップの見方については、以下の記事でも詳しく説明していますので、参考にしてみてくださいね。
自分でできる浸水対策をする
大雨時に浸水が想定されている地域に自宅があるなら、浸水対策は重要です。特別に専門業者に依頼しなくても、自分で浸水対策をおこなうことは可能なので、どのような浸水対策を実行できるのか確認してみましょう。
- 土のうの設置
- 簡易止水板を設置
- 床下換気口を塞ぐ
土のうとは専用の袋に土を詰めたもので、浸水を防ぐのにとても役立ちます。ただし、1袋だけで防ぐのは難しいため、浸水してくる範囲分が必要です。ホームセンターで土のう袋や詰める土も購入できますし、最近では土が不要な水でふくらむ吸水式の土のう袋も販売されています。
また、複数の簡易止水板を設置すれば、建物内への水の侵入が防げます。簡易止水板とは、近年のゲリラ豪雨対策に開発された高い止水性能を持つ板です。
そして、床下への雨水の侵入は床下換気口からになるため、この床下換気口を板などで塞げば、床下への水の侵入を防ぐことが可能。最近では安価な床下換気口を塞ぐアイテムも販売されているので、購入を検討してみてください。
水害対策については、以下の記事で詳しく説明しています。参考にしてみてくださいね。
まとめ

Q:床下浸水してしまったらどうすればいい?
A:床下浸水してしまったら、泥水の排水と溜まった泥の除去、乾燥、消毒などの処理が必要です。万が一処理を怠ると、床下に細菌やカビが繁殖して、健康被害を引き起こします。また、湿気で柱や床板の傷みも激しくなるため、決して放置してはいけません。確実に処理するには、専門の会社へ依頼するのがおすすめです。
Q:床下浸水は火災保険で補償される?
A:床下浸水は火災保険で補償されますが、水災補償に加入していないと適用になりません。また、支給にも条件があり、加入していれば必ず補償されるわけではないので注意が必要です。
今回は被害を受けた際の処理方法や、火災保険の適用、自治体からの支援金などを詳しく解説しました。床下浸水は大雨時に起きる可能性のある災害です。洪水ハザードマップを確認すれば、自宅がどのくらい浸水するか把握が可能。その情報をもとに、あらかじめ浸水防止措置を施すことができます。しかし、できれば大雨が降っても、浸水を気にしないで過ごしたいですよね。これからマイホームの建築を検討しているなら、高台にあり浸水を気にしなくて済む土地を検討するのはいかがでしょう。
物件を探す



