バリアフリーの注文住宅を作るには?場所別のポイントと補助金・助成金・減税制度を解説

新築する注文住宅をバリアフリーにする際、玄関や居室、水回りなど、それぞれの場所に採用したい設備があるかもしれません。
そこで今回の記事では、場所別にバリアフリーにする際のポイントを解説します。さらには、利用できる補助金・助成金、減税制度をご紹介します。
記事の目次
バリアフリー住宅とは
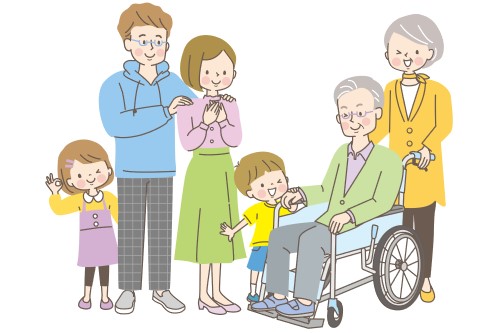
バリアフリー住宅とは、小さな子どもから高齢者まで、誰もが安心・安全に暮らすための設備やシステムを備えた住宅のことです。特に高齢になると足腰が弱り、体力も衰えてくることから、転倒や転落など家の中での事故を防ぐためにバリアフリー住宅を検討する人が増えています。
バリアフリーな注文住宅にするポイント│外構

バリアフリーな注文住宅を建てる際、門や塀、アプローチ、駐車スペースなどの外構にはどのような工夫が必要なのでしょうか。ここでは、バリアフリーな外構にするための4つのポイントをご紹介します。
段差をなくす
バリアフリー住宅では段差を極力なくすことが重要です。家族に車椅子が必要な人や足が不自由な人がいる場合、門から玄関までのアプローチに段差があると乗り越えるのは大変です。また、わずかな段差でも転倒やケガなどのリスクが高まります。バリアフリー住宅では、安心して移動できるよう、できるだけ段差をなくしましょう。
スロープを作る
玄関から外へ出る際、高低差がある場合はスロープを作るとよいでしょう。緩やかなスロープがあれば車椅子でも安全に移動でき、小さな子どもや高齢者がいる場合でも転倒や転落を防止できるため安心です。
手すりを取り付ける
高齢者や歩行が困難な方は、玄関までのアプローチに段差や階段があると、転倒や転落の事故が起こりやすくなります。そんな時アプローチに手すりがあると、転倒や転落を防止でき、移動が楽になります。
駐車スペースに砂利を敷かない
施行費用を抑えられて、照り返しを防ぐことから、駐車スペースに砂利を敷くケースは多いようです。しかし、砂利は歩く時に足を取られやすく、車椅子では移動がしづらくなります。バリアフリーを考えるなら、駐車スペースに砂利を敷くのは避けましょう。
バリアフリーな注文住宅にするポイント│玄関

家への出入りで必ず通る玄関は高低差が生じやすくなっています。靴を脱いだり履いたりする場所でもあるので、バリアフリー化は必須でしょう。ここでは玄関をバリアフリーにするためのポイントを3つご紹介します。
扉は引き戸にする
家をバリアフリーにするなら、玄関の扉は引き戸にするのがよいでしょう。引き戸は力を入れなくても開けられるので、体力が衰えている高齢者に向いています。
また、車椅子の人も引き戸なら1人で開け閉めしやすくなります。玄関だけでなく、居室や浴室の扉も引き戸がおすすめです。もし予算があれば、リモコン操作や顔認証で楽に開閉できる自動ドアを検討してもよいでしょう。
手すり・腰掛を設置する
立ったまま靴を脱いだり履いたりすると転倒の危険があります。安全に靴を脱ぎ履きできるよう、玄関には腰掛を設置するとよいでしょう。また、玄関には上がり框の段差があるので、安心して移動できるように手すりも設置しましょう。
上がり框(かまち)をなくす・低くする
一般的な住宅では玄関の上がり框は、20~30cmの高さがあります。しかし、高齢者や小さな子どもにとって、この高低差は転倒や転落の危険があります。バリアフリー住宅では、上がり框を10cm以下にするとよいでしょう。また、車椅子に乗る人がいる場合は、上がり框をなくすと家の出入りが楽になります。
バリアフリーな注文住宅にするポイント│居室

家族が生活する居室にもバリアフリーにするポイントがあります。今回は、居室をバリアフリーにする時のポイントを3つご紹介します。
滑りにくい床材を使用する
滑りやすい床材を使用してしまうと家の中で滑ったりつまずいたりして、転倒する事故が起きやすいといわれています。小さな子どもから高齢者まで、家の中でケガなく安心して過ごすためには、滑りにくい床材を選ぶことが大事です。また、やわらかい材質の床材を選ぶと、足腰の弱い高齢者の負担を軽減でき、安心でしょう。
トイレや浴室、リビング・ダイニング・キッチンを近くに配置する
トイレや浴室、リビング・ダイニング、キッチンなど生活に必須な部屋を可能な限り近くに配置することで、高齢者や移動が困難な方の移動距離を短くできます。部屋同士を近くに配置すれば、介助が必要になった場合の周囲の人の負担も比較的軽くなるでしょう。また、要介護の方の様子を確認しやすくするため、要介護の方がすごす部屋を家族が過ごすリビング・ダイニングの近くに配置するとよいでしょう。
廊下と居室の間に段差をなくす
バリアフリー住宅にするには、家の中の段差をなくすことが重要です。転倒の事故がなく、高齢者でも安全に移動できるよう、居室と廊下の間に段差を設けないようにしましょう。段差がなくなれば、車椅子でも移動しやすくなり安心です。
バリアフリーな注文住宅にするポイント│水回り

トイレや浴室など、住宅の水回りはバリアフリーにしておきたいポイントが多いエリアです。ここでは、水回りでバリアフリーにしておきたいポイントを5つご紹介します。
介助をしやすいスペース・仕様にする
要介護者を介助するには、出入り口や部屋に広めのスペースを取ることを推奨します。車椅子に乗っていても移動しやすい広さと、使いやすい仕様の設備を設けておきましょう。
浴室の床材・バスタブは滑りにくい素材にする
浴室は特に滑りやすいところです。足腰の弱い高齢者が入浴する時に転倒しやすいので、床材は滑りにくい素材を選びましょう。また、バスタブは高齢者だけでなく、子どもや大人でも滑りやすい部分。誰もが安全に使用できるよう滑り止めを設けておきましょう。
浴室に手すり・リフトを設置する
誰もが安心・安全に入浴できるように、浴槽や浴室の壁に手すりを設置しておきましょう。また、介助が必要になった時のために、入浴介助用のリフトがあると介助者の負担を軽減できます。
ヒートショック対策をする
ヒートショックとは、急激な温度差によって血圧が上下し、心筋梗塞や脳出血、脳梗塞などを引き起こすことです。冬場は脱衣所やトイレなどと居室との温度差が大きくなり、高齢者は特にヒートショックを起こしやすくなります。脱衣所には暖房器具を置き、窓の断熱性を高めてヒートショック対策を施しておきましょう。
アクセスや作業のしやすいキッチン・洗面所にする
長い時間立ったまま調理をするのが難しい方も安全に作業ができるようキッチンに椅子を設置するのもおすすめ。シンクなどの高さも、座りながら作業できる高さに調節するとよいでしょう。さらに、つかまって作業ができるように狭くして近くに物を配置したほうがよいのか、車椅子で移動するためにある程度の広さを確保したほうがよいのかなど、必要に応じて使用しやすいキッチンを検討しましょう。洗面所も車椅子に乗ったままでも使える車椅子対応の洗面台もあるので、使用しやすいものを選びましょう。
バリアフリーな注文住宅にするポイント│設備

バリアフリーな注文住宅にするには、安心・安全に生活できるような設備を導入するのもよいでしょう。予算を確保できそうであれば検討してみてください。
エレベーター・昇降機を付ける
足腰が弱くなった高齢者でも階をまたいで移動しやすくするため、いす式階段昇降機を設置するのもよいでしょう。また、要介護者と介助する家族の移動を楽にするため、あるいは車椅子でも容易に家の中を移動できるようにするため、ホームエレベーターを設置するもの一つの方法です。
オール電化にする
高齢になってからも調理する機会がある時は、安全のためにオール電化を検討してもよいでしょう。ガスコンロの場合、火の消し忘れやガス栓の閉め忘れによる火災のリスクが高まります。他にも、自力で立位を保つのが難しい方がつかまりながら作業をしていた際に、手をついた先に火がついていたなどの事故が起きてしまう可能性も。その点、オール電化にすればキッチンで火を使わずに済むため、火災・事故のリスクを減らせるでしょう。
車椅子でも通行できる広めの廊下にする
家族に車椅子を必要とする人がいる場合、廊下は介助する家族が並んで歩けるくらいのスペースがほしいところです。廊下が広いと車椅子の移動がしやすくなります。また、廊下とともに寝室や浴室、トイレ、洗面所の出入り口も広めに確保しておきましょう。
バリアフリーな注文住宅で利用できる補助金・助成金・減税制度

この章では、バリアフリーな注文住宅を建築する際に利用できる補助金・助成金と、減税制度をご紹介します。
補助金・助成金
まずは2つの補助金・助成金制度を紹介します。
ZEH補助金
ZEH補助金とは、国が実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」による補助金制度です。新築の一戸建て住宅で、ZEH、ZEH+を施し、高断熱・省エネ・創エネを実現する住宅を建築する場合、ZEHでは55万円、ZEH+では100万円が補助されます。また、蓄電システムや地中熱ヒートポンプ・システムなどのシステムを導入すると、その費用の一部も補助されます。
ZEH補助金には予算があり、申請期間は2024年12月23日までとなっていますが、予算を達成すれば終了するので注意が必要です。ZEH補助金の詳細は、一般社団法人環境共創イニシアチブの「令和6年度戸建ZEH」のサイトを参照してください。
東京ゼロエミ住宅導入促進事業
東京都では、都内に高度な省エネ性能の東京ゼロエミ住宅を新築する場合、その費用の一部を助成しています。
助成額は、取得した認証の水準により異なりますが、2024年10月1日からは新水準が採用されます。
- 水準A:240万円/戸
- 水準B:160万円/戸
- 水準C:40万円/戸
この他、太陽光発電設備や蓄電池、V2Hなどの設備を導入すると、追加で助成を受けられます。東京ゼロエミ住宅導入促進事業には予算があり、申請期間は2024年12月27日までとなっていますが、予算に達した時点で終了となります。
東京ゼロエミ住宅導入促進事業の詳細は、東京都の「令和6年度東京ゼロエミ住宅導入促進事業」のサイトを参照ください。
減税制度
減税制度を2つ紹介します。
住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)のことで、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から最大13年間控除される制度です。新築・購入の場合、対象となる住宅が長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に限定されます。現時点の制度では、2024年入居、2025年入居の場合に住宅ローン控除が適用されることになっています。これから制度がどうなっていくのかは、今後の税制改正の内容をチェックしましょう。
固定資産税の減税
土地や家屋などの不動産や償却資産の所有者は、毎年固定資産税を納付することになっています。新築の戸建て住宅を建築した場合、2026年3月31日までは固定資産税が3年間、2分の1に軽減されます。さらに認定長期優良住宅を新築した場合、適用期間が5年間に延長されます。
バリアフリーな注文住宅に関するまとめ
バリアフリーな注文住宅を作るポイントを解説しました。今回の記事のまとめです。
玄関をバリアフリーな注文住宅にするポイントは?
力の入りにくい方でも簡単に開閉できるよう、扉は引き戸にするのがおすすめです。また、靴の脱ぎ履きで転倒しないよう手すりや腰掛を設置するとよいでしょう。さらに、転落防止のために上がり框を低くするか、思い切ってなくすと安心です。
水回りをバリアフリーな注文住宅にするポイントは?
浴室には手すりを設け、床は滑りにくい素材にして、バスタブには滑り止めを施しましょう。また、冬場になると、居室と浴室、脱衣所、トイレなどでは温度差によりヒートショックを起こしやすくなるため、暖房器具や断熱性の高い窓などを導入することをおすすめします。その他、水回りは高齢者の介助がしやすくなるよう広めのスペースを取り、洗面所などは車椅子でも使いやすい仕様にするとよいでしょう。
バリアフリーな注文住宅で利用できる減税制度は?
建築する注文住宅を長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅にすると、年末の住宅ローン残高の0.7%が最大13年間、税額控除になる住宅ローン控除を受けられます。
ただし、2024年10月現在では、2024年と2025年入居の場合のみ対象となっています。今後の住宅ローン控除の動向は、国の発表を確認してください。
この他、2026年3月31日までは、新築してから3年間(認定長期優良住宅の場合は5年間)、固定資産税が2分の1に減税されます。
バリアフリーな注文住宅を新築する時は、外構や玄関、居室、水回りなどを安全に利用できること、そして要介護者を介助する時のことを考えながら設備や素材などを考えるとよいのではないでしょうか。今回の記事を参考に、家族がいつまでも安心して生活できるバリアフリーな住宅を検討してください。
注文住宅を建てる






