【実例あり】注文住宅の外構とは?外構の種類や失敗しないためのポイントを徹底解説

本記事では、外構を決める際に知っておきたい点をわかりやすく解説しています。注文住宅で失敗したくないという方は、ぜひ家づくりの参考にしてください。
記事の目次
注文住宅の外構とは?

注文住宅における外構とは、屋外にある構造物のすべてを指します。門扉や門柱、塀やアプローチ、植栽など、すべてが外構です。自家用車を持っていれば駐車場が必要ですし、自転車を使うなら駐輪スペースも設けるでしょう。例え屋根を付けないとしても、注射・駐輪のためコンクリート敷にしたり砂利を敷いたり、舗装工事をするのであれば外構の一つにくくられます。
外構と似たものに、エクステリアという言葉もあります。エクステリアも屋外に関するものですが、外構が「物」を指すのに対して、エクステリアは「空間」を指す点で異なります。例えば家具や電化製品、雑貨などが置かれてインテリアが作られますが、これと同様、門扉や植栽などの外構が置かれて作られる空間がエクステリアです。
注文住宅の外構の役割

そもそも外構は、何のために作るのでしょうか。以下で、外構の役割について見ていきましょう。
外観デザインが向上される
外構の役割としてまず挙げられるのが、デザイン性を向上してくれるという点です。外構のテイストによって注文住宅の雰囲気は大きく変わります。好みのテイストを比較検討しながら決めましょう。
プライバシーが確保できる
外構は敷地外からの視線を遮り、プライバシーを確保する役割を担っています。そのため、周囲の環境に合わせた設計にすることが重要です。
防犯性が高まる
外構には、不審者の侵入を防ぐ役割もあります。例えばフェンスや植栽を適切にレイアウトし、見通しをよくすることも有効でしょう。あるいは、フェンスや門扉を高くして、物理的に侵入を防ぐ方法もあります。センサーライトや防犯カメラを設置すれば、不審者へのけん制効果が期待できます。
アクティビティ溢れる生活空間をつくる
外構には、生活やアクティビティをより充実させる役割もあります。屋外にテーブルやチェアを置けるようなエリアを作れば、庭でバーベキューを楽しめるようになるでしょう。また、家庭菜園のスペースを設ければ、野菜を育てる楽しみを見出すことも可能です。
注文住宅で外構専門施工会社に依頼するメリット・デメリット
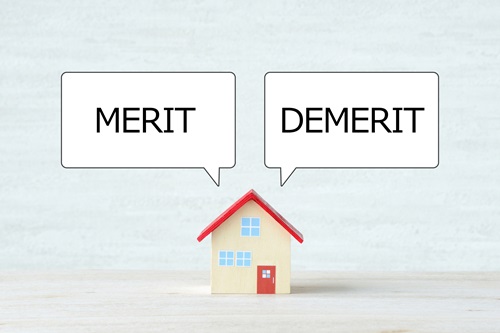
外構の施工は、ハウスメーカーや工務店に任せることもできます。しかし、人によっては外構専門会社に依頼することも少なくありません。では、どちらに任せるのがよいのでしょうか。ここからは、外構専門施工会社へ依頼することのメリットとデメリットをご紹介します。
メリット
外構専門施工会社に依頼するのには、次のメリットがあります。
- 種類・実績が豊富
- 好きなタイミングで工事ができる
- 担当者と直接打ち合わせができる
外構専門施工会社は、外構に特化しているため知識や経験が豊富です。外構工事も好きなタイミングでおこなうことができるので、より生活スタイルに合った外構を作ることが可能になります。また、個々に応じて臨機応変に対応してくれることが多く、自由度の高さを求める方や、細かいところまでこだわりたい方に向いています。
デメリット
外構専門施工会社に依頼することには、次のようなデメリットがあります。
- 施工会社を自分で探す必要がある
- 打ち合わせや手続きが増える
- 費用がかさむ
外構専門施工会社とのやり取りは、ハウスメーカーや工務店を介さずに進めることになります。そのため、施工会社を探すところから自分たちでおこなわなければなりません。もちろん、打ち合わせするのも自分たちです。そのため、手間と時間がかかることを覚悟しておきましょう。また、こだわるほどに費用がかさみがちになる点も、事前に理解しておきたいポイントです。
注文住宅の外構工事の進め方

外構工事がどのような流れで進められるのか、ここでは外構専門施工会社に依頼する場合を想定し、事前準備から完成、引き渡しまでのおおまかな流れを説明します。
優先順位を決める
まずは、どんな外構にしたいかイメージをふくらませます。雑誌やWebで事例を見たり、外を出歩いた際に見かけた家の特徴に目を向けたりすることで、少しずつ自分たちの理想とする外構がイメージしやすくなるでしょう。ただし、要望をすべて叶えられるとは限りません。「カーポートを屋根付きにしたい」「花壇を設けたい」「ウッドデッキもあったらいいな」など、きっとさまざまな要望が湧いてくるはずです。そのなかから、必ず実現したいもの、できれば叶えたいものを仕分けましょう。ある程度の優先順位を設けておくと、プランの検討がスムーズに進みやすくなります。
予算をしっかりと確保する
次に、外構に割ける予算を決めます。外構工事の費用は、新築の場合で住宅本体費用の10%程度が相場といわれています。しかし、実際には100万円でおさめる収める方もいますし、家の中より外構を優先させ、外構費用の比率を高く設定する方もいるでしょう。自分たちが外構をどの程度重視しているかを踏まえて、予算を決定するのがおすすめです。
施工会社の選定・依頼
外構のイメージが湧き予算が決まったら、施工会社を選びます。施工会社によって、施工法に得手不得手があります。ホームページ等で実績を確認し、自分たちの理想に近い実績がある会社を選ぶのがよいでしょう。また、あまりに安価な会社には要注意です。適正価格よりも極端に安い場合は相応の理由がありますし、保証やアフターサービスの有無も確認して信頼できる会社を選んでください。最初から1社に絞るのではなく、2〜3社から相見積もりを取ると安心です。
現地の調査と打ち合わせ
依頼する施工会社を決めたら、打ち合わせをおこないます。実際の寸法を測ったり写真を撮影したりするため、現地で打ち合わせるのが一般的です。このとき、どんな外構にしたいのか、予算なども含めて詳しく伝えることになります。伝えそびれのないよう、事前に要望をまとめておくとスムーズです。不明な点も、このタイミングで尋ねましょう。
プランと見積書の提出
現地調査および打ち合わせを踏まえて、施工会社からプランと見積書が提出されます。相見積もりを取っている場合は、ひととおり揃ったあとで見比べると、相対的な視点で検討できるでしょう。なお、イマイチだと感じた場合は、どのような点がイメージと異なるのかを施工会社に伝えましょう。場合によっては、別の施工会社へ相談することで理想の外構プランに出合えることもあります。
依頼先の決定と契約
プランが決まったら、施工会社へ正式に発注します。発注時は、外構工事請契約書を必ず結んでください。契約書の締結は建設業法の第18条でも義務付けられていますし、契約書を結ばないと、あとになってトラブルを招きかねません。契約書を受け取ったら、工事内容と代金の内訳の記載があること、そして完成した際に欠陥や不備があった場合買主や発注者が保証を受けることができる瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を確認します。
着工〜完成、引き渡し
契約が完了したら着工となります。ただし、一般的に外構工事の着工のタイミングは建物ができたあとです。完成したら、プランどおりに作られているか担当者と一つずつ確認しましょう。何か不具合があれば指摘し、補修など対処してもらえるよう交渉します。問題がなければ、引き渡しとなります。
注文住宅の外構の基本スタイル
注文住宅の外構は、おおまかに3タイプに分類されます。その際にポイントとなる「ゾーニング」の考え方について、まずは確認しましょう。
注文住宅の外構のゾーニングとは?
外構ごとにエリア分けすることをゾーニングといいます。門から玄関までのアプローチや庭、カーポート、あるいは洗濯物干し場など、異なる用途を持った場所ごとに配置と広さをおおまかに計画します。ゾーニングを考える際は、まず外構スタイルを決め、方針を固めることになります。外構の基本スタイルは、次の3タイプです。
オープン外構

フェンスや塀のない外構をオープン外構といいます。オープン外構の魅力は、なんといっても開放感でしょう。敷地が狭くても圧迫感が少ないですし、フェンスや塀を設けない分、外構施工費が安く済むのもポイントです。ただし、プライバシーの保護や防犯の面で工夫が必要になります。
セミクローズ外構

道路に面している部分のみなど、一部に塀やフェンスを設ける外構をセミクローズ外構と呼びます。それなりに開放感が欲しい一方、フェンスや塀ならではのおしゃれな雰囲気を求める方にぴったりでしょう。ただし、敷地が完全に囲われているわけではないので、侵入のリスクを大きく減らせるとは限りません。
クローズド外構

敷地をぐるりと囲うのがクローズド外構です。3タイプの中で、もっともプライバシーの確保と侵入のリスク減を叶えやすい外構といえるでしょう。
しかし逆に、一度でも侵入されてしまうと外から見えにくいというリスクも理解しておかなければなりません。
また、クローズド外構を採用するデメリットとして、開放感が少ないという点が挙げられます。また、施工費用も高くなりがちです。
【実例】注文住宅外構の種類
ここからは、実例を交えながら外構の種類について説明します。
門扉、門柱

まるで海外にいるかのような気持ちにさせる一軒家で、赤を基調とした家に対して濃茶の門扉と門柱が配されています。門柱に耐火煉瓦とブリックを使用することで、あたたかい雰囲気が生まれるとともに全体的な調和も生まれています。

オープン外構で、玄関前に門柱のみを立てた事例です。重厚感のある和モダンな家に対して、門柱にはライトグレーを採用しました。飽きのこないデザインが追求されています。
塀・フェンス

道路側からの見栄えを意識し、白い外壁に白い塀を組み合わせたおしゃれな住宅です。明るい印象で、セミクローズ外構でありながら閉塞感を感じさせません。
玄関へのアプローチ
![玄関へのアプローチは住まいの第一印象を決定づける重要な部分です 出典:パパまるハウス [(株)ヒノキヤグループ]](https://www.athome.co.jp/contents/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/exterior-structure_11.jpg)
玄関アプローチは、パブリックな場所から住宅というプライベートな場所へとつながる動線です。そのため、どのような作りにするかで、家への期待感が変わります。こちらのアプローチでは、明るいオレンジとベージュをベースに乱形の素材をレイアウトしています。歩みを進めるほど、ワクワク気分が高まりそうです。
メインガーデン

メインガーデンは屋内から眺められることが一般的であり、居室空間の快適性を上げるためにも大事なエリアです。こちらは、広々とした芝生に遊具を設置。ドッグランとしても最適で自然の良さをたっぷり感じられる作りになっています。デッキが併設されているので、のんびりと過ごすこともできます。子どもやワンちゃんと思い切り遊べる好事例です。
テラス・デッキ

テラスやデッキを洗濯干しスペースとして活用するときは、特に周囲からの見え方を意識しましょう。こちらの家は開放感たっぷりの作りですが、それは家そのものが小高い場所に建っていて、プライバシーが確保しやすい立地条件があるからこそ。外から丸見えになりそうであれば、テラス横に樹木をほどこすなどの工夫が必要です。
樹木や植栽、花壇

シンプルモダンなカラーで統一された一軒家です。塀もグレー一色とすることで寂しくなりがちなところを、正面に樹木と植栽をほどこし、おしゃれで洗練された佇まいに仕上げています。樹木は、年々成長していくのもポイントです。
駐車・駐輪スペース

駐車スペースは、車がある家にとって必要不可欠な外構です。車の台数だけでなく、車のサイズや運転スキルを踏まえて検討しましょう。こちらの方は歳を重ねても快適であるようにと、駐車スペースをゆったりと作りました。駐車場に屋根を設けると住宅全体を重く見せてしまうことがありますが、屋根に透過性の高い素材を採用することで、開放感と利便性の双方を叶えています。
照明

夜間の見た目にもこだわりたいのであれば、外構における照明も重要です。こちらの家は、外構としての照明使いが上手な好事例です。大きな4枚の採光窓とバランスのいい位置に照明がレイアウトされ、まるで美しい写真を眺めているような印象深い外観に仕上がっています。
物置

家の中をスッキリさせたいときは、物置を外に置くのも一つの方法です。物置もこの事例のように、外壁と色味を合わせることで統一感が生まれ、機能性だけでなくデザイン性も高めてくれます。
水道・電源

どんな生活をしたいか次第では、水道や電源も必要になるでしょう。こちらは、バーベキューができるようにと屋外キッチンを設け、水道と電源を作った事例です。リビングの大きな掃き出し窓の正面にデッキを設け、炊事スペースを設置することで動線も追求されています。
注文住宅の外構で失敗しないためのポイント

最後に、注文住宅の外構で失敗しないためのポイントをまとめました。
周辺環境や間取りからスタイルを決める
基本スタイルは、周辺環境や間取りを踏まえて、どのようなスタイルにするのかを決めましょう。一般的には、自然に囲まれた場所であればオープン外構、街中であればクローズド外構が向いているといわれています。
外観や街並みと調和を図る
外構は家の外観を左右するだけでなく、街の一部にもなります。あまりに奇抜なデザインだと浮いてしまうので、街並みと調和しているかも考慮してください。
駐車スペースは十分な広さを確保する
実際に暮らしてみたら、駐車スペースが狭かったという失敗談は少なくありません。必要十分なスペースだと思っていても、家族が増えたため大きな車に買い替えたり、自転車を購入し駐車スペースに余裕がなくなってしまったりすることがあります。今だけでなく、将来も見据えて十分な広さを確保しましょう。
機能性とデザインのバランスを意識する
外構は、どうしても見た目重視で選びがちです。しかし、機能性も考えながら全体を設計しましょう。例えば、日没後に帰宅しても玄関までのアプローチが暗すぎることはないかなど、実際に暮らしたときのことをイメージして不自由がないかチェックしてください。
メンテナンスや点検のしやすさを考慮する
注文住宅は、一度建てたら終わりではありません。定期的に点検やメンテナンスをすることで、長く安全に暮らせます。そのため、メンテナンスや点検のしやすさを考えておきましょう。建物の裏側は狭くしたくなるかもしれませんが、メンテナンスや点検で使うことになるので、最低限の通路スペースを確保する必要があります。
植栽やフェンスが隣家とトラブルになるのを避ける
隣家とのトラブルを招かぬよう、植栽やフェンスの位置や形状には十分に注意しましょう。隣家との境界ギリギリに樹木を設置すると、枝が越境したり落ち葉が隣家のスペースに落ちたりする可能性があります。また、フェンスの選び方によって、隣家の日当たりや風通しが悪くなることがあるので気をつけてましょう。
まとめ
注文住宅の外構には、門扉や門柱、塀やアプローチ、植栽などさまざまなものがあります。外構は、ちょっとした工夫でデザイン性も機能性も向上するので、ぜひ細部までこだわりましょう。ハウスメーカーや工務店も外構を手がけてくれますが、自由度の高さを求めるのであれば、外構専門施工会社に依頼するのもおすすめです。周辺環境や間取りを踏まえて考える、外観や街並みとの調和を意識するなど、失敗しないポイントを押さえ満足度の高い外構を作りましょう。
注文住宅を建てる



