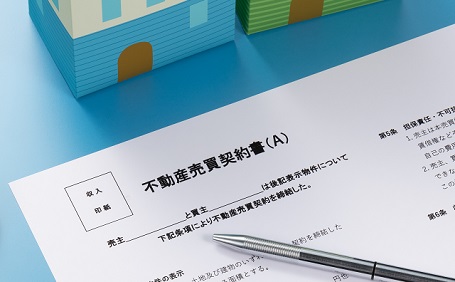注文住宅の相場は?価格別の特徴や予算を組むポイントを解説

これから注文住宅を建てるのであれば、予算オーバーや費用のかけ方で後悔することがないよう、注文住宅の費用を知っておくことが大切です。
今回のテーマは、注文住宅の相場です。注文住宅の費用内訳や、土地がある場合とない場合の建築費の相場、建築費に影響する要素についてまとめました。注文住宅の資金計画を考えるうえで知っておくべきことを解説します。
記事の目次
注文住宅にかかる費用

注文住宅にかかる費用には、主に土地の購入費・建物の建築費の2つがあります。順に解説します。
土地の購入費
土地の購入費は、土地代金のほか次のような諸費用がかかります。
仲介手数料
仲介手数料は、土地を購入する際に不動産会社の仲介を通じて売買した場合に、不動産会社に支払う報酬です。仲介手数料の上限金額は法律で規定されており、売買金額によって変わります。
| 売買代金 | 仲介手数料(上限) |
|---|---|
| 200万円以下 | 5%+消費税 |
| 200万円超え400万円以下 | 4%+2万円+消費税 |
| 400万円超え | 3%+6万円+消費税 |
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」
なお、土地を所有するハウスメーカーから不動産会社を介さず直接購入する場合、仲介手数料はかかりません。
印紙税
土地の売買契約を締結する際にかかる費用です。印紙税は、売買契約書や工事請負契約書など課税文書に課せられる税金です。
契約金額によって印紙税の税額は変わります。2027年3月31日までに作成される売買契約書には、軽減措置が適用されます。
登記費用
登記費用は、土地の所有権を購入者に移転するためにかかる費用です。登録免許税と司法書士に依頼した場合の報酬があります。登録免許税は、土地の固定資産税評価額に税率をかけて算出します。
また、土地購入資金で住宅ローンを利用する場合、事務手数料をはじめ住宅ローンの諸費用がかかります。
土地の購入費用は、土地代金のほかこれらの諸費用を含めて考えることが必要です。
建物の購入費
建物の購入費は次のような費用がかかります。
建築費用
建築費用は、本体工事費と付帯工事費の2つに大きく分けられます。
本体工事は、木工事(部材を組み立て骨組みを作る工事)のほか、仮設工事や基礎工事、内外装工事、キッチンなどの設備の設置工事、空調工事などです。設計料を本体工事費に含むこともあります。
一方、付帯工事は、外構工事や水道・ガスなどインフラの引込工事、照明やカーテンなどの取付工事などです。土地の状況によって、解体工事や地盤調査、地盤改良工事費がかかる場合もあります。
諸費用
建物にかかる費用には、上記で解説した建築費用のほか以下のような諸費用が必要です。土地購入の際にかかった手数料とは別に、建物にも登記費用や印紙代など似たような手数料がかかります。これらはおよそ建築費全体の10%程度が目安といわれます。
| 印紙代 | 工事請負契約書・住宅ローン契約書にかかる印紙税 |
|---|---|
| 登記費用 | 建物の所有権保存・移転登記、住宅ローンの抵当権設定にかかる登記費用 |
| 消費税 | 建物にかかる消費税 |
| 住宅ローン諸費用 | 住宅ローン借入にともなう事務手数料や保証料 |
| 地鎮祭や上棟式 | 地鎮祭や上棟式での神主さんへの謝礼やお供え物の費用 |
| 保険料 | 火災保険料・地震保険料 |
| 不動産取得税 | 不動産の取得にともなう税金 |
このほか、新居に合わせた家具や家電の購入費、引越し代なども、資金計画では考慮する必要があります。
注文住宅の建築費相場

では、注文住宅を建てるにはどれくらいの資金が必要なのでしょうか。ここでは、全国ならびに3大都市圏、主要都市の建築費相場を紹介します。
全国平均は3,935万円
国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査 報告書」によると、土地購入費用を除いた注文住宅の建築資金の全国平均は、3,935万円です。3大都市圏でみると、4,504万円と全国平均より500万円以上高くなっています。
また、住宅ローンなどの借り入れを除いた自己資金の比率は、全国で29.9%、3大都市圏で32.6%と、建築資金のおよそ30%程度を自己資金で準備しています。
土地ありの場合
注文住宅の建築費は、土地がある場合とない場合では変わります。
ここでは、住宅金融支援機構の調査をもとに、土地がある場合とない場合の建築費にどれくらいの違いがあるかをまとめました。
次の表は、土地がある場合※1の住宅面積※2と建築費※3をまとめたものです。
| 地域 | 住宅面積 | 建築費 |
|---|---|---|
| 全国 | 122.8平方メートル | 3715.2万円 |
| 首都圏 | 123.4平方メートル | 4015.9万円 |
| 近畿圏 | 126.1平方メートル | 3990.5万円 |
| 東海圏 | 125.2平方メートル | 3788.0万円 |
出典:住宅金融支援機構「フラット35利用者調査(2022年度集計表)」
※1 土地取得費をフラット35で借入していない
※2 住宅面積はバルコニー部分を除いた専有面積
※3 建築費には主体工事費だけではなく付帯工事(電気・給排水・ガス設備・太陽熱温水器など)、設計費、工事管理費、除却工事費、屋外付帯工事費、その他必要費用を含む
土地なしの場合
次に、全国ならびに主要な都道府県別にみた、土地から取得する場合の建築費ならびに土地取得費です。
| 地域 | 建築費/ 住宅面積 |
土地取得費/ 敷地面積 |
費用合計 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 3194.6万円/ 111.5平方メートル |
1499.5万円/ 237.0平方メートル |
4694.1万円 |
| 北海道 | 3427.7万円/ 117.9平方メートル |
1002.2万円/ 280.3平方メートル |
4429.9万円 |
| 東京都 | 2960.0万円/ 120.4平方メートル |
3662.9万円/ 120.4平方メートル |
6622.9万円 |
| 愛知県 | 3506.6万円/ 118.3平方メートル |
1736.2万円/ 214.5平方メートル |
5242.8万円 |
| 大阪府 | 2997.9万円/ 110.8平方メートル |
2052.4万円/ 141.1平方メートル |
5050.3万円 |
| 福岡県 | 3344.5万円/ 112.5平方メートル |
1197.1万円/ 266.2平方メートル |
4541.6万円 |
| 沖縄県 | 3472.5万円/ 115.4平方メートル |
1640.8万円/ 235.1平方メートル |
5113.3万円 |
出典:住宅金融支援機構「フラット35利用者調査(2022年度集計表)」
全国平均でみた場合、土地がある場合の建築費用が、3,715.2万円であるのに対し、土地から取得する場合の注文住宅の建築費は3,194.6万円と、およそ500万円の差となっています。土地の取得費がかかる分建築費は抑えられていることがわかります。
土地がある場合の首都圏の建築費平均が、4015.9万円に対し、土地がない場合の東京都の建築費平均が2960.0万円と1,000万円以上の違いです。
また、地域別に見た場合でも、土地の取得費が高い東京都や大阪府の建築費が、ほかの都道府県と比べ抑えられているのがわかります。
平均坪単価から注文住宅の費用をシミュレーション

ここでは、建築費の坪単価からみた注文住宅の費用をシミュレーションします。坪単価は、建物の1坪(約3.3平方メートル)を建築するのに、どれくらいの費用がかかるかを表すものです。
住宅金融支援機構の調査では、全国平均の建築費は3,194.6万円、住宅面積は111.5平方メートルでした。ここから、建築費の坪単価を算出すると、約94.7万円/坪となります。これをもとに建築面積別に費用を紹介します。
30坪の場合
木造の30坪、およそ100平方メートルの広さの家であれば、建築費の目安は2,841万円となります。
全国平均(111.5平方メートル)よりコンパクトな広さですが、3~4LDKの間取りで4人家族でも住める広さです。
ただし、通路やホールのほか階段部分も床面積に含まれため、有効な居住面積をしっかり確保できる無駄のない間取りプランが必要です。
35坪の場合
35坪、およそ115平方メートルの広さになると、建築費の目安は3,314万円となります。注文住宅では平均的な広さとなり、間取りタイプでいうと4LDK~5LDKが多い広さです。
5人家族でも無理なく住めます。世帯人数が少なければリビングを広くしたり、吹き抜けを設け開放感のある間取りにしたりもできるでしょう。
40坪の場合
木造でも40坪、およそ130平方メートルになると、建築費の目安は3,788万円です。
注文住宅のなかでも、かなり余裕を持てる広さになり、リビングだけでなく各居室も広くとることが可能です。将来の親世帯との同居などの家族構成の変化にも対応できます。
建築費は床面積だけで決まるわけではありませんが、建築費の目安として参考にしてください。
なお、坪単価から建築資金を考えるときに注意しなければならないのは、ハウスメーカーや工務店によって坪単価に含まれるものが違う点です。建物本体工事といっても、照明や空調などの電気工事もしくは、水道やガスなどインフラの配管工事まで含まれることもあれば、含まれない場合もあります。
坪単価を見るときは、何が含まれ、ほかにどれくらいの費用がかかるのかを把握しましょう。そのうえで、最終的な坪単価で住宅会社の見積もりを比較・検討することが大切です。
予算別に見る注文住宅の特徴

注文住宅の場合、建売住宅と異なり、土地購入費用と建物の建築費を調整することが可能です。ここでは、建物にかける予算別に、どのような注文住宅が建てられるか解説します。
1,000万円台の注文住宅
1,000万円台の予算で抑える場合、外観や間取りはシンプルなものが多くなります。
建物形状は長方形や正方形などの四角形が多くなります。L字型やコの字型の家は、同じ床面積でも外壁の面積が増え、材料費や足場代がかかりやすくなるためです。
また、外観はシンプルになりやすいでしょう。屋根も施工する面が1枚で済む片流れ屋根を導入するケースが多くなります。
1階と2階が同じ面積である総2階建ての建物がコストダウンを図りやすくなります。間取りは完全な自由設計ではありません。住宅メーカーごとに準備された、いくつかのプランから間取りや仕様、設備を選ぶことが多くなります。
2,000万円台の注文住宅
2,000万円台の注文住宅となると、33坪程度の平均的な広さであれば、坪単価60~90万円の家を建てられます。ある程度は、間取りや外観、内装、住宅設備にこだわることも可能です。
ただし、延床面積にもよりますが、2,000万円台は平均的な建築費用です。優先順位をつけて費用かける部分を決めないと、予算オーバーになる可能性もあります。
内装や外装より住宅設備にお金をかける、また、水回りの設備のなかでもキッチンのグレードにはこだわるが、それ以外の浴室や洗面、トイレにかける費用は抑えるなどのメリハリが必要です。
3,000万円台の注文住宅
3,000万円台の予算になると、33坪の平均的な家で坪単価は90万円~となります。
工法や省エネ、耐震性などの住宅性能にこだわりながら、価格帯が高いハウスメーカーから選べるでしょう。
ゆったりとした広い間取りにすることも可能です。例えば、間取りのなかに開放感のある吹き抜けのリビングを設けられます。
外壁材や屋根材など外装や内装材の仕様、設備のグレードを上げやすく、高い価格帯のアイランドキッチンやグレードにこだわれるでしょう。
4,000万円台の注文住宅
4,000万円台の予算になると、床面積を広くし1人あたりの居住面積を広くすることも可能です。居住面積を確保しながら、中央部に中庭を配置し開放感のある設計プランも考えられます。
また、一般的に木造より坪単価が高い鉄骨造も検討でき、壁や柱が少ない開放感のある間取りも実現しやすいでしょう。
加えて、外装・内装や水回りの設備も、高機能で省エネ性能が高いグレードの住宅設備を選べるでしょう。
建物本体だけでなく、外構工事も駐車場やウッドデッキ、門扉、アプローチ、植栽など、エクステリアデザインにこだわることも可能です。
注文住宅の費用が建売よりも高くなりやすい理由

建売住宅は、土地と建物がセットで販売される住宅です。注文住宅と異なり、間取りや外観などを選べる自由度はありませんが、注文住宅より価格を抑えやすい特徴があります。建売住宅の場合、同一の設備や建材を大量に仕入れることでコストダウンを図り、間取りのプランをいくつかに限定することで設計料や現場監理費を抑えています。
また、間取りプランや設備、仕様を統一することで工期の短縮が可能です。分譲地をはじめ複数の区画で販売される場合は、広い土地を一括購入することで土地取得費を抑えられます。
これに対し、注文住宅の場合、間取りや仕様、設備の選択の自由度が高い一方、大量仕入れや規格を統一することによるコストダウンは図りづらくなります。
建売住宅と異なり、ハウスメーカーは、モデルハウスや展示場を作るなど広告費をかける分、販売価格に含まれる販売経費が高くなりやすいでしょう。
注文住宅の坪単価を決める4大要素

建築費は、建築面積と坪単価で決まります。では、注文住宅の坪単価を左右する要素として、どのようなものが考えられるのでしょうか。4大要素を紹介します。
設備のグレード・素材の種類
住宅設備、なかでも水回りの設備のグレードで坪単価は変わります。
例えば、キッチンであれば、グレードのほかにサイズやキッチンタイプ、ワークトップや扉材に使われている素材などで価格が異なります。水回りの配置によって配管工事費も違ってくるでしょう。
また、外壁材や内装材のグレードでも建築費は変わります。外装材には、窯業系・金属系サイディングやモルタル、タイル、ALC(軽量気泡コンクリート)などいくつか種類があります。耐用年数やメンテナンスのしやすさ、耐震性(重量)など、それぞれ特徴がありますが、選ぶ素材ごとに価格が設定されています。
建物の形状・デザイン
家の形状やデザインによっても坪単価は変わります。
建物の形状を、凹凸が少なく角の数が少ないシンプルな四角形にすれば、外壁の面積を減らせます。これにより材料費や施工費、足場代などの費用を抑えることが可能です。また、角(コーナー)に使う部材を減らすことでコストダウンを実現できます。
また、1階と2階の床面積が違う間取りより、同じ面積である総2階にすることにより、基礎工事や足場代などの費用が抑えられます。
さらに、注文住宅では、ライフスタイルに合わせ自由に間取りを考えられますが、間仕切り壁が多いほど、使用する建材や施工費が増え坪単価は高くなります。
住宅構造
耐震性にこだわりたい、柱や壁のない広い空間を作りたいなど、構造によって希望する家が建てられるかが変わることはあります。ただし、選択する構造によって坪単価の相場はまったく異なります。
注文住宅の構造には、木造のほか、鉄骨造、鉄筋コンクリート造(RC造)があります。坪単価は、木造から鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順に高くなっていくのが通常です。
次の表は、国土交通省の建築着工統計調査をもとに、構造別の坪単価をまとめたものです。
| 構造 | 坪単価 |
|---|---|
| 木造 | 69.9万円 |
| 鉄骨造 | 98.5万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 107.6万円 |
出典:国土交通省「2023年度建築着工統計調査」
構造によって断熱性や防音性、気密性などの住宅性能も変わります。それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、何を優先するか決めることが大切です。
ハウスメーカー・工務店・建築会社
坪単価は、依頼する会社によっても異なります。
自社ブランドを持つ大手ハウスメーカーであれば、坪単価80~100万円以上が相場です。ハウスメーカーのなかでも、中堅のハウスメーカーでは、60~80万円/坪、ローコストメーカーだと40~60万円/坪が相場となります。地域密着型の工務店の相場は、50~70万円/坪です。
ハウスメーカーは、全国規模で営業拠点を構え、CMやモデルハウスなどの広告を積極的におこなっています。資材調達から施工まで一貫して管理しており、品質や仕上がりの差が出にくい点が特徴です。
地域の工務店は、一般的に特定の地域に特化し、施工エリアを絞っています。比較的コストは抑えやすく、予算や要望に合わせ柔軟に対応してもらいやすい点がメリットです。
依頼する住宅会社によって、予算規模だけでなく住宅性能やアフターサービスなども変わります。コスト以外の面も含め総合的に判断しましょう。
注文住宅の予算を組むのに大切な考え方

注文住宅の予算を決めるうえで、押さえておくべき考え方があります。
購入する土地の広さ
土地から購入する場合、建築面積や延床面積によって必要な土地の広さは変わります。
例えば、総二階の30坪の家を建てる場合、建ぺい率が60%の地域であれば約25坪以上、建ぺい率が50%の地域であれば約30坪以上の土地面積が必要です。確保する駐車場の台数やライフスタイルによっては、それ以上の広さが必要かもしれません。
必要な土地の広さと希望する立地の土地相場がわかれば、土地の取得費の目安がわかります。冒頭で紹介したように、注文住宅全体の予算を考えるとき、土地取得費と建物の建築費以外に諸費用を含めて考えなければなりません。
建物プランの打合せに入って予算が足りないとならないように、必要な土地面積の考え方を理解しておきましょう。
床面積・部屋数の考え方
リビングや各居室の広さ、部屋数は、長期的な視点で慎重に判断することが大切です。
床面積が広くなるほど建築費は高くなります。部屋数が増えれば建材や仕上げ、施工の手間が増え、建築コストは上がる傾向にあります。床面積が広いほど、固定資産税や光熱費などのランニングコストも増えやすくなるでしょう。
また、子どもの数や性別、年齢差などを考慮して部屋の広さや数を判断することが必要です。子どもが独立後、あるいはリタイア後のライフスタイルの変化、維持管理の負担など長期的な視点で広さや部屋数を決めるとよいでしょう。
年収・住宅ローンのバランス

年収によって住宅ローン借入可能額はわかりますが、借入可能額が必ずしも無理なく返済できる借入金額とは限りません。年齢や家族構成、家計支出などは1人1人異なりますので、慎重な判断が必要です。
住宅ローンの借入金額を決めるうえで、年収だけでなく返済負担率※や金利が上昇した場合の返済額の上昇なども考慮して決めることが大切です。
返済負担率とは、年収に対する年間の住宅ローン返済が占める割合をいいます。家計の支出は1人1人異なります。住宅ローン以外の支出を踏まえ、毎月の返済負担が無理なものでないか判断しましょう。
家を建てるエリアの選び方
家を建てるエリアによって建物にかけられる予算や資産性が変わりますので、選び方が大切です。
注文住宅のメリットは土地と建物の予算を調整できる点です。つまり、立地条件や周辺環境を優先して土地にお金をかけるか、もしくは、建物の広さや設備、仕様など建物にお金をかけるかで注文住宅の購入の仕方は変わります。
決められた予算のなかで、立地条件がいい人気エリアほど土地相場は高く、建物にかける資金を抑える必要があるでしょう。
また、資産性でみたとき、一戸建ての場合、築年数の経過とともに建物の価値は減少し、土地の価値に集約されていきます。土地は築年によって価値が下がる資産ではありません。そのため、需要が高ければ資産価値を維持できます。立地によっては、購入時より高くなることも考えられます。
将来、注文住宅を売却もしくは住み替えを考えている方は、家を建てるエリアの選定も重要です。
土地、建物にかける予算、あるいは資産性をどこまで考えるかでエリアの選び方は変わります。
ライフプラン踏まえ長期の視点で考える
注文住宅で考えることは、家づくりと資金計画です。ただし、いずれもライフプランを踏まえ、長期の視点で判断することが大切です。
家を購入すると、住宅ローン返済以外に、固定資産税や火災保険料、将来のメンテナンスのための積立などの維持管理費用が必要となります。子どもが増えたり、成長したりするなかで家計の状況が変わることもありますし、老後資金のための貯蓄も考えなければなりません。
また、家族構成やライフスタイルの変化に合わせて家の広さや間取りを考えることも大切です。注文住宅の購入計画は、ライフプランを踏まえた長期の視点で判断しましょう。
注文住宅の予算に関するまとめ
最後に、これまでの内容を踏まえ、注文住宅の予算に関して簡単に整理します。
注文住宅にかかる費用の内訳
注文住宅にかかる費用は、大きく分けて土地取得費、建築費用の2つに分かれます。土地取得費用には、土地代金だけでなく、仲介手数料や登記費用などの諸費用を考えておくことが必要です。一方、建築費用には、本体工事費のほか外構工事や水道・ガスの引込工事などの付帯工事費があります。その他、住宅ローンの諸費用や建物の消費税などの諸費用があります。
注文住宅の建築費用の相場
国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査 報告書」では、土地購入費用を除いた注文住宅の建築資金(全国平均)は、3,935万円です。3大都市圏でみると、4,504万円となっています。
また、土地を所有している場合といない場合で建築費用の相場は異なります。住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査(2022年度集計表)」では、土地ありの全国平均の建築費が3,715.2万円、土地なしの場合3,194.6万円と、約500万円の違いがあります。
注文住宅の坪単価を決める要素は?
注文住宅の坪単価を決める要素は、依頼する住宅会社によって決まる部分もあります。また、建物の構造や形状のほか、間取りや仕様、設備のグレードなどさまざまな要素が坪単価に影響します。
建売住宅と異なり、購入した土地で地盤改良が必要になったり、打合せ段階のプラン変更によって資金が増えたりすることもあります。そのため、まずは無理のない予算を決めることがスタートです。そのうえで、建物に必要な広さや立地条件など優先順位を踏まえ、土地と建物の予算配分を決めます。
自由度の高い注文住宅でも、すべての希望通りの家づくりは難しい場合もあります。建物の予算のなかで、費用をかけるところとかけないところのメリハリをつけることで建築費を抑えることを考えましょう。
注文住宅を建てる