ガレージの固定資産税はいくらかかる?かかるガレージの条件や計算方法を解説

本記事では、ガレージに固定資産税がかかる条件を解説します。また、固定資産税がかかるガレージ、かからないガレージを具体的に紹介。固定資産を所有している限り、固定資産税は毎年納めなければなりません。どれくらいかかるのかを押さえるためにも、把握しておきましょう。
記事の目次
ガレージに固定資産税がかかる条件

冒頭でも述べたように、ガレージの種類や構造によって、固定資産税がかかるかどうかが異なります。本章では、固定資産税の概要とガレージに固定資産税がかかる条件を解説します。
固定資産税とは
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産にかかる税金です。家屋の具体例としては、住宅や店舗、工場など。毎年1月1日時点の所有者が、固定資産の所在する市町村に納めます。税額は、固定資産税の価値(課税標準額)に一定の税率をかけた金額です。
ガレージに固定資産税がかかる条件
不動産登記規則の111条では、建物を次のように定義しています。
出典:不動産登記規則 百十一条
まとめると、次の3つの条件を備えた場合に建物とみなされ、固定資産税がかかります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
外気分断性
外気分断性とは、室内と屋外が区切られており、外部の空気や風雨が内部に入らないことを指します。具体的には屋根があり、3方向以上が壁に囲まれていること。不動産登記規則では「屋根及び周壁又はこれらに類するもの」と定義されている部分です。
ただし、周壁については、完全に外気との分断がされていなくても、使用目的や利用状況を考慮して外気分断性があると判断されるケースもあります。例えば、周りに壁がなくても、出入り口にシャッターを設置した場合、外気分断性があると判断されます。
土地への定着性
土地への定着性とは、土地に固定されていて、簡単に移動できないことを指します。例えば、基礎工事がおこなわれ、物理的に土地に固定されている場合は、固定資産税がかかります。一方、物置やコンテナを置いただけの状態は、土地に固定されていないため、固定資産税はかかりません。
用途性
用途性とは、目的に応じて利用できる状態にあることを指します。具体的には、ガレージとして使う設備が整っていれば、用途性ありと判断され、固定資産税がかかります。
固定資産税がかかるガレージとかからないガレージ

ガレージが「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の3つの条件を満たしている場合、固定資産税がかかります。本章では、固定資産税がかかるもの・かからないものの2つに分け、具体的なガレージの種類をご紹介します。
固定資産税がかかるガレージ
固定資産税がかかる可能性があるガレージは、次の3種類です。
プレハブ小屋
プレハブ小屋をガレージとして利用する場合、設置のみで済むため、短期間で工事が完了します。また、工場で生産されるため、品質が一定している点も特徴です。しかし、商品の選択肢が限られており、デザインの自由度が低い傾向にあります。
プレハブ小屋には屋根があり、すべての面に壁が設置されているため、外気分断性があると判断されます。土地への定着性は、設置方法によって判断が分かれるため、必ずしも固定資産税がかかるとは限りません。しかし、耐久性や利用状況なども考慮されます。そのため、プレハブ小屋を直接土地に固定していなくても、定着性があると判断され、固定資産税がかかることもあります。
コンテナハウス
コンテナハウスとは、コンテナを利用した建物のことです。鋼鉄で作られていることから、耐久性が高い点が特徴。また、ものによっては20万円台で購入できるため、安価な点もメリットといえるでしょう。しかし、設置場所にコンテナを運ばなければならないため、道路の幅が広くなければ設置が難しくなります。安く仕入れられても、輸送費が高額になることもあるため、事前によく検討しなければなりません。
コンテナは四方が壁に囲まれており、外気分断性があるとみなされます。また、ガレージとして利用する場合、随時かつ任意に移動できないため、定着性があると判断され、固定資産税がかかる可能性があります。この場合、建築物に該当するため、建築基準法に基づく確認申請をし、確認済証の交付を受けなければなりません。コンテナハウスをガレージとして利用したい場合、設置前に不動産会社に相談しましょう。
ビルトインガレージ
ビルトインガレージとは、駐車スペースを建物の一部に組み込み、シャッターやドアを設置したガレージのことです。インナーガレージと呼ぶこともあります。住宅内に組み込まれているため、荷物の積み下ろしが楽になる点がメリット。また、シャッターを付ければ、防犯性も高まります。一方、土地を広く確保しなければ、居住スペースや駐車スペースが狭くなってしまう可能性も。また、車のエンジン音が居住スペースに響くこともあります。
固定資産税の観点から見ると、ビルトインガレージは住宅内に組み込まれているため、外気分断性、土地への定着性の要件を満たします。一般的な住宅と比べ、ビルトインガレージの住宅は、床面積が広くなるため、固定資産税も高くなる傾向にあります。また、建築費用も高額になるため、よく検討しましょう。
固定資産税がかからないガレージ
次に、固定資産税がかからないガレージを見ていきましょう。それぞれ詳しく解説します。
カーポート
カーポートとは、屋根と柱だけで構成されたものです。屋根があることから、雨の日でも傘を差さずに乗り降りできる点がメリットです。また、デザイン次第で家の外観に調和させることもできます。一方、壁がないため、外部の空気や風雨を遮断できません。また、壁に囲まれたガレージと比較すると、防犯性は低くなります。
カーポートは、土地への定着性はありますが、外気分断性の要件を満たさないことから家屋とみなされず、固定資産税の課税対象外となります。
オープンスペース
オープンスペースタイプの駐車場は、コンクリートで舗装したり、砂利を敷いて駐車スペースを確保するものです。屋根や壁などがないため、設置費用を大幅に削減できます。また、周囲を遮るものがないため、開放的な印象を与えるでしょう。一方、屋根や壁がないことから、雨や風、直射日光などの影響を直接受けることに。車が汚れやすくなるなど、劣化が早まる可能性もあります。
屋根や壁がないことから、外気分断性がなく、家屋とはみなされません。しかし、土地自体に固定資産税がかかります。ただし、住宅用地の特例が適用され、税金の負担が軽減されます。
バイクガレージ
車だけでなく、バイクが好きな方もいるでしょう。基礎工事をせず、土地への定着性がなければ、固定資産税はかかりません。また、カーポートのように、屋根と柱だけで構成する場合もかかりません。しかし、ガレージと同様、基礎工事をし、屋根や壁を設ける場合は土地への定着性と外気分断性があるとみなされ、固定資産税がかかります。
ガレージにかかる固定資産税はいくら?
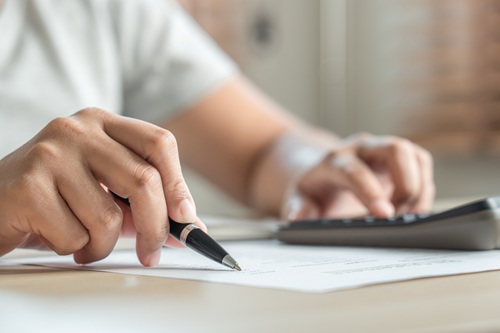
固定資産税がかかるガレージとかからないガレージを見てきました。それでは、実際にどれくらいかかるのでしょうか。本章では計算方法を解説し、シミュレーションをおこないます。
ガレージの固定資産税の計算方法
まずは、固定資産税の計算方法を押さえておきましょう。固定資産税額を求める計算式は次のとおりです。
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%
課税標準額とは、自治体が土地や家屋などの固定資産をいくらで評価しているかを表した金額です。一般的に家屋の場合、建築費用の約60%が目安となります。
例えば、ガレージの建築費用が180万円だった場合の固定資産税を計算してみましょう。この場合、課税標準額は次の計算式で求められます。
180万円 × 60% = 108万円
次に、固定資産税額を求めてみましょう。
108万円 × 1.4% =1万5120円
今回の場合、1年間で納める固定資産税額は1万5120円となりました。
ガレージの都市計画税の計算方法
都市計画税とは、市街化区域内に土地や建物を所有している人に対して課される税金です。税率は自治体によって異なりますが、0.3%が上限となります。都市計画税を求める計算式は次のとおり。
都市計画税額 = 課税標準額 × 0.3%
先ほどと同じ、ガレージの建築費用が180万円だった場合をシミュレーションしてみましょう。課税標準額は固定資産税の時と同様、108万円です。都市計画税を求める計算式は次のとおりです。
108万円 × 0.3% = 3240円
自宅が市街化区域内にある場合は、固定資産税とあわせて、都市計画税を納める必要があります。
ガレージを作る際の注意点

ガレージにはさまざまな種類がありますが、固定資産税以外にも共通して気を付けなければならない点があります。自宅と同様、建築すると簡単に変更できません。後悔しないためにも、注意点を押さえておきましょう。
無許可で作らない
ガレージを作る際は、必ず自治体に申告しましょう。例えば、コンテナやプレハブ小屋など、「設置するだけだから許可は必要ない」「バレない」と思われるかもしれません。しかし、固定資産税額の算出のために、自治体職員によって家屋調査がおこなわれます。
無許可で建築していることがバレれば、違法建築物として除却や使用禁止命令などが出されることも。場合によっては、罰金を支払わなければならない恐れもあるため、ガレージの建築を考えている場合は、事前に不動産会社や施工会社に伝え、自治体に申告しておきましょう。
建ぺい率・容積率を確認する
ガレージを作る際には、建ぺい率と容積率を必ず確認しましょう。建ぺい率や容積率は、敷地内で建築できる建物の面積や規模を制限するものです。もし、これらを超えたガレージを作った場合、違法建築物とみなされ、罰則や罰金の対象となります。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のこと。例えば、敷地面積が100平方メートルで、建ぺい率が60%だった場合、ガレージを含む建てられる建物の面積は60平方メートルです。
また、容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合のこと。例えば、容積率が300%だった場合、敷地面積100平方メートルに対して、延床面積が300平方メートルまでの建物を建てられます。
ただし、ビルトインガレージの場合、建物の延床面積の1/5を限度として、容積率の合計から除外することができます。例えば、建物の延床面積が100平方メートルで、駐車場が25平方メートルの場合。25平方メートルの1/5である5平方メートルは延床面積に含まれません。
内装や外装に制限がないかを確認する
ガレージは、火災時の安全性を確保するため、内装が制限されます。内装制限とは、屋根や壁に使用できる材料が制限されること。火災の延焼や有毒ガスの発生を防ぐため、燃えにくい素材を使用するよう、建築基準法で定められています。
また、ガレージを作る地域によっては、外装も制限される可能性も。例えば、防火地域や準防火地域では、延焼を防ぐため、防火性能を持つ素材の使用が求められます。自治体によって内容が異なるため、事前に問い合わせましょう。
登記が必要になる可能性がある
建築するガレージの種類によって、登記が必要になる可能性があります。不動産登記法の第47条では、建物を新築した場合、所有権を取得した日から1カ月以内に登記しなければならないと定められています。もし、申請を怠った時は、10万円以下の過料が科されることも。
ただし、登記が必要になるガレージは、建物とみなされるものです。そのため、壁で仕切られておらず、外気分断性がないカーポートは、原則登記は必要ありません。しかし、シャッターを付けたガレージやビルトインガレージなどは建物とみなされるため、登記が必要です。カーポートの種類によって異なるため、不動産会社や司法書士などの専門家に確認しましょう。
車の買い替えを考慮する
ガレージは、車の買い替えを考慮して作りましょう。ガレージは一度作ればそのままですが、車は買い替える可能性が高いもの。そのため、今所有している車に合わせてガレージを作ると、将来車を買い替えた時に出し入れが難しくなるおそれもあります。
例えば、今は夫婦2人の生活で、軽自動車で十分であっても、子どもが産まれてワンボックスカーに買い替えることも考えられます。将来の車の買い替えを見据え、余裕を持ったサイズのガレージを作ることが重要です。
ガレージの固定資産税を抑えるためのポイント

ガレージの広さや構造によって、固定資産税の金額は変化します。所有している限り、毎年納めなければならないため、できる限り抑えたいと考える方もいるでしょう。本章では、ガレージの固定資産税を抑えるためのポイントを解説します。
必要最低限の広さにする
ガレージの固定資産税を抑えるために、必要最低限の広さにする方法があります。固定資産税額は、固定資産税評価額をもとに算出されます。そのため、ガレージの面積が広くなると、その分固定資産税評価額が上がり、結果として固定資産税額も増加します。
しかし、先述したように、ガレージは一度作ると簡単に変更できません。将来の車の買い替えも見越しつつ、必要最低限の広さのガレージにすることで、税負担を軽減できるでしょう。
簡易な構造のガレージにする
ガレージの固定資産税を抑えたい時は、簡易な構造のガレージを検討しましょう。固定資産税は、外気分断性、土地への定着性、用途性の3つの条件を満たしたガレージに課されます。そのため、カーポートやオープンスペースなど、簡易なガレージにすることで、固定資産税の負担を軽減できます。また、このようなガレージであれば、建築費用も抑えられます。
ただし、屋根や壁がない分、雨や風、直射日光の影響を受けやすくなるため、車への負担は大きくなるでしょう。ガレージの種類によって、メリット・デメリットがあるため、よく比較したうえで選びましょう。
まとめ
本記事では、ガレージに固定資産税がかかる条件や計算方法を解説しました。外気分断性、土地への定着性、用途性の3つの条件を満たす場合、ガレージは建物とみなされ、固定資産税がかかります。そのため、カーポートやオープンスペースタイプのガレージは建物とみなされず、固定資産税がかかりません。
ただし、雨や風を避けるものがないため、車の劣化が早まる可能性があります。それぞれのガレージにメリット・デメリットがあるため、固定資産税だけでなく、さまざまな視点からよく検討したうえで、選択しましょう。
注文住宅を建てる

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ






