家を建てる際にかかる費用は?土地の有無・予算別に費用の内訳を解説

住まいは一生に一度の大きな買い物です。だからこそ、失敗や後悔を避けるために、正しい知識と視点を持って判断しなければなりません。本記事では、家を建てる際の費用の目安を解説します。「家を建てたいけれどお金がない」と悩む方は、現実的な選択肢と進め方を確認しましょう。
記事の目次
家を建てる際の平均費用

国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査 報告書」によると、土地の購入費用を除いた注文住宅の建築資金の全国平均は4,319万円です。建築資金の全国平均は年々高騰しており、今後もより高額になることが予想されます。
| 令和元年度 | 3,235万円 |
|---|---|
| 令和2年度 | 3,168万円 |
| 令和3年度 | 3,459万円 |
| 令和4年度 | 3,935万円 |
| 令和5年度 | 4,319万円 |
また、土地の購入資金の全国平均は1,929万円と、土地から購入する場合は6,000万円以上を見越して予算を立てることが現実的となるでしょう。しかし、あくまで平均費用のため、希望の住宅仕様と資金計画をあわせて検討することが重要です。
家を建てる際にかかる頭金の目安
住宅ローンでは、頭金として物件価格の10%〜20%を用意するケースが一般的です。
住宅金融支援機構の「2023年度フラット35利用者調査」によると、注文住宅を購入する際の頭金として用意した金額の平均割合は、土地付きの場合が所要資金の約9.7%、注文住宅のみの場合が約18%でした。よって、土地を除いて考える場合、4,000万円の住宅なら800万円を目安に用意するとよいでしょう。
近年では、頭金ゼロでも借りられる金融機関も増えていますが、頭金が多いほど借入額が減ることから、可能な範囲で頭金を準備することが望ましいでしょう。ただし、すべての資金を頭金に充ててしまうと、予備費や生活費が不足するリスクがあるため、手元資金とのバランスを考えて用意しなければなりません。
【土地あり・なし別】家を建てる費用の内訳

土地の有無は、家づくり全体のコストに大きく影響します。土地をすでに所有している場合は初期費用を抑えられますが、土地なしの場合は土地の購入費用に加え、建築費用がかかり、二重コストが発生します。資金計画を立てる際は、土地取得の有無で予算配分が大きく異なることを理解しておかなければなりません。
また、土地の有無によって建築にかかるスケジュールにも差が出ます。土地がある場合はすぐに設計や施工に進めますが、土地がない場合はまず立地選びからスタートします。期限が決まっている場合は、早めに着手することが好ましいでしょう。
土地ありで家を建てる場合の費用
すでに土地を所有している場合は、土地代がかからないため、予算を抑えたい場合はローコスト住宅やコンパクト設計を選ぶことで実現可能です。以下は、土地ありで家を建てる場合のおおまかな内訳を示した表です。
| 費用項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 土地代 | 0円 |
| 建築費用 | 3,500万円〜5,000万円 |
| 付帯工事費 | 100万円〜300万円 |
| 諸費用(登記など) | 300万円〜500万円 |
| 合計 | 4,000万円〜6,000万円 |
コストを抑えながらも、耐震性や断熱性など性能を確保するには、地域に根ざした工務店やローコスト住宅メーカーの活用が鍵となります。
土地なしで家を建てる場合の費用
土地を所有していない場合は、土地の購入費用が加わるため、総費用は大きく増えます。都市部では土地だけで2,000万円以上になることもめずらしくありません。土地代を抑えたい場合は、郊外や地方を選ぶことでコストを抑える戦略が有効です。
また、古家付き土地を購入して解体する手法も、全体のコストを抑える選択肢として検討できます。ただし、埋設物の除去や地盤改良が必要になるケースもあるため、注意しましょう。以下は、土地なしで家を建てる場合のおおまかな内訳を示した表です。
| 費用項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 土地代 | 1,000万円〜3,000万円 |
| 建築費用 | 3,500万円〜5,000万円 |
| 付帯工事費 | 200万円〜400万円 |
| 諸費用(登記など) | 300万円〜500万円 |
| 合計 | 5,000万円〜9,000万円 |
土地の購入には不動産会社とのやりとりや仲介手数料がかかるほか、地盤調査や上下水道の引き込みなど追加のインフラ整備費が必要になります。想定外の出費で予算オーバーにならないためにも、予備費の確保が重要です。
家を建てる際にかかる費用の内訳

家づくりにかかる費用は、本体工事費と付帯工事費、諸費用の3つに分類されます。それぞれの割合と内容を把握して、予算オーバーを防ぎ、無駄のない資金計画を立てましょう。本章では、家を建てる際にかかる各費用の内訳を解説します。
本体工事費
本体工事費とは、家本体の建築にかかる費用で、土地の購入費用を差し引いた全体の約70〜80%を占めます。注文住宅の場合、仕様や素材、施工会社によって変動が大きく、平均的には4,000万円前後が目安です。外壁材や屋根材、内装のグレードによって数百万円単位で変動するため、優先順位をつけて調整をおこなわなければなりません。
また、本体工事費には以下の工事が含まれます。
- 仮設工事
- 基礎工事
- 構造体工事
- 内外装工事
- 住宅設備工事
建築基準法や地域の気候、地形などによって設計・施工方法が変わるため、設計士や施工会社と丁寧に打ち合わせをし、コストを抑える工夫を取り入れることが重要です。
付帯工事費
付帯工事費は、屋外給排水や外構、地盤改良などにかかる費用で、総費用の約15〜20%を見込んでおきましょう。特に地盤改良は、調査の結果次第で、100万円以上の出費になることもめずらしくありません。土地から購入する場合は、土地選びの段階で地盤の状態も確認しておくことが重要です。
付帯工事は、住宅全体の安全性や快適性に直結する部分となります。駐車スペースの整備や庭の整地、照明やフェンスの設置など、住んでから必要と感じる要素が多く含まれるため、余裕を持った予算設定をおこないましょう。
諸費用
諸費用は、登記費用や住宅ローン手数料、火災保険料などの費用で、全体の5〜10%程度を見込んでおく必要があります。見落としがちな項目ですが、引越し費用や家具・家電の購入費用も含めると、最終的な出費は想像以上になることもめずらしくないため注意しましょう。引越し後すぐに必要となる費用も多く、総予算とは別で50万〜150万円程度の予備費を確保しておくと安心です。
住宅ローンの返済計画の立て方のポイント

住宅ローンは、家を建てる資金計画に欠かせません。借入可能額を把握し、無理のない返済プランを立てることが成功の鍵になります。
一般的に、住宅ローンの借入可能額は年収の5〜7倍が目安とされています。年収500万円なら2,500〜3,500万円程度が目安です。ただし、借入限度額ギリギリで住宅を購入すると、家計が圧迫される可能性があるため注意しましょう。
また、住宅ローンの審査は年収だけではなく、他の借入状況なども判断基準となるため、全体の家計を見直すよい機会にもなります。
住宅ローンの返済計画を立てる際の注意点
住宅ローンの返済計画を立てる際は、以下の3つのポイントを押さえましょう。
- 返済比率は年収の20%以内にする
- 返済期間は完済時の年齢を考えて設定する
- ボーナス返済は慎重に判断する
無理なく返済を続けられる返済比率の目安は、手取り年収の20%以内とされています。返済比率を超える借り入れをしてしまうと、返済負担が大きくなるため注意しましょう。
また、返済期間を短く設定すれば、利息の総支払額は減りますが、月々の返済額は増えるため家計を圧迫してしまう可能性も否定できません。一方、返済期間を長く設定すれば毎月の負担は軽くなりますが、総返済額が多くなります。また、定年後も返済を続ける可能性があるため、老後のリスクも踏まえて判断する必要があるでしょう。
繰り上げ返済のタイミングや、ボーナス併用の可否も慎重に検討し、余裕のある返済プランを立てることが、家計を安定させるコツです。
費用が払えなくても家を建てる方法

家を建てるには多額の費用が必要となります。しかし、返済期間を考えると、なるべく早めに家を建てたいと考える方も多いでしょう。
費用の支払いが難しくとも、フルローンや自治体の補助金制度、ローコスト住宅の活用などをうまく組み合わせることで「お金がないから家を建てられない」状況は回避できます。本章では、費用を支払えなくても家を建てる方法を解説します。
フルローンを活用する
近年では、頭金ゼロでもフルローンで借り入れできる金融機関が増えています。ただし、フルローンを選択する場合、借入金額が大きくなるため、毎月の返済額や返済期間に注意しなければなりません。
また、頭金を用意しない分、金利が高くなる可能性があるため、返済シミュレーションを念入りにおこなう必要があります。フルローンを活用する際は、事前に返済計画と資金繰りを明確にすることが成功の鍵です。
補助金・支援制度を活用する
国や自治体が実施している補助金制度を利用することで、実質的な建築費用を数十万〜数百万円単位の軽減が可能です。例えば「子育てグリーン住宅支援事業」を活用して、省エネ住宅やZEH住宅を建てることで最大160万円の補助を受けることができます。
ほかにも「給湯省エネ2025事業」では、高効率給湯器を導入することで最大20万円の補助金を受けられます。ただし、子育てグリーン住宅支援事業との併用ができないため、注意が必要です。申請には条件や期限があるため、工務店やハウスメーカーと連携して早めに準備を進めましょう。
ローコスト住宅を検討する
ローコスト住宅は、シンプルな構造と大量発注によるコスト削減で価格が抑えられた住宅です。間取りや外観の自由度がある程度制限されることもありますが、建築費用を抑えたい方にとって、ローコスト住宅は有力な選択肢となるでしょう。
ただし、安さだけで選ぶのではなく、断熱性や耐震性などの基本性能がしっかり確保されているかをチェックしましょう。複数の会社を比較し、見積もりや実例を確認することが、納得のいく家づくりへの第一歩です。
費用を節約しながら理想の家を建てるポイント
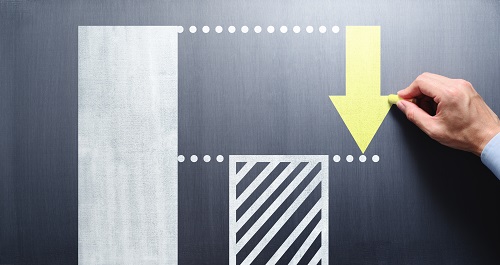
家づくりは、妥協と工夫のバランスが鍵となります。コストを抑えながらも、自分たちのライフスタイルに合った空間を実現するためには、家づくりに着手する前の事前計画が重要です。本章では、費用を節約しながら理想の家を建てるポイントを解説します。
事前に予算の優先順位を決める
家を建てる際の希望条件を明確にし、優先順位を決めることが予算内で理想の家を建てる第一歩です。家族で意見を出し合い、将来的なライフスタイルまで視野に入れて検討しましょう。
初期段階から設計士や工務店と相談し、優先度の高い要素と削ってもよい部分を整理することが重要です。必要な部屋数や広さ、設備などの希望を具体化し、予算とのバランスを見つつ調整しながら進めていきましょう。
相見積もりを取る
複数の工務店やハウスメーカーから見積もりを取り、費用と内容を比較しましょう。同じ要望でも会社によって、見積もり額が数百万円単位で異なる場合もめずらしくありません。
相見積もりを取ることで、価格の妥当性や仕様の違いを比較できます。また、交渉の材料にもなり、値引きやサービスの追加を得られる可能性も期待できるでしょう。
ただし、見積もり項目が他社と揃っているか、諸費用や付帯工事費が含まれているかを確認しなければなりません。形式だけの比較ではなく、施工実績や対応力もチェックして、最終的に信頼できるパートナーを選びましょう。
DIYや施主支給を活用する
照明器具や設備など、自分で手配することでコストを抑えられるケースもあります。DIYに自信がある方は、内装や外構の一部を自ら手がけることで大幅な節約も可能です。例えば、カーテンレールや棚、ウッドデッキの設置などは、ホームセンターで資材を購入して自分で取り付けることで費用の削減が期待できるでしょう。
また、施主自身が設備や建材を選び、メーカーから直接購入する施主支給を活用すればコストを大きく下げられる可能性があります。ただし、トラブルを防ぐためにも、施工会社との調整や保証の確認は忘れずにおこないましょう。
まとめ
家を建てる際に必要な費用は、建築費用だけではなく、土地の購入費用や付帯工事費、諸費用など多岐にわたります。また、頭金や住宅ローンの条件によっても、総返済額や月々の返済額は大きく変わるため注意しましょう。
家を建てる際の費用は年々高騰していますが「高いから無理」とあきらめるのではなく、住宅ローンの組み方や節約の工夫を知ることで、手の届く夢に変えることができます。理想の住まいを現実にするために、まずは情報を整理し、自分たちの条件に合った家づくりを一歩ずつ進めていきましょう。
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ









