犬にマダニが寄生したら?マダニの見分け方や噛まれた時の対処法について解説

記事の目次
マダニとは

マダニとは肉眼でも確認できる比較的大型のダニで、体長は吸血前で3~10mm、吸血後には20mm近くまで膨らみます。普段は草むらやヤブ、あぜ道、畑、山林などに潜み、シカやイノシシなどの野生動物のほか、人や犬を待ち構えています。一度寄生すると皮膚に口器を突き刺し、セメント状の物質で固定して数日から10日かけて吸血します。吸血後は大量の卵を産み付けるため繁殖力が強く、全国各地でみられます。春から秋にかけて活動が盛んになりますが、1年を通して注意が必要です。
犬に寄生するマダニの種類

犬に寄生するマダニには多くの種類があり、日本全国に生息しています。代表的な種類には「フタトゲチマダニ」「タネガタマダニ」が挙げられ、北海道や中部山岳地帯では「シェルツェマダニ」、西日本では「タカサゴキララマダニ」や「クリイロコイタマダニ」などが確認されています。これらは草むらや山林、畑などに潜み、犬が散歩中に触れることで寄生します。マダニの吸血は、皮膚炎やかゆみをもたらすだけでなく、SFTSやバベシア症など重篤な感染症を発症する可能性があります。とくに、草むらに近づくときは、犬も人も予防対策を徹底しましょう。
| マダニの種類 | 生息地 |
|---|---|
| シェルツェマダニ | 北海道・中部の山岳地帯 |
| タネガタマダニ | 全国 |
| フタトゲチマダニ | 全国 |
| ツリガネマダニ | 本州・九州 |
| キチマダニ | 全国 |
| タカサゴキララマダニ | 西日本 |
| クリイロコイタマダニ | 西日本・九州・沖縄 |
| ヤマアラシチマダニ | 本州・九州・沖縄 |
| ヤマトマダニ | 北海道・本州・九州 |
| ミナミネズミマダニ | 沖縄 |
犬がマダニに噛まれたか確認する方法

犬がマダニに噛まれたかどうかを見極めるためには、飼い主が日ごろから体を丁寧にチェックすることが大切です。マダニは、比較的大きいため肉眼でも見つけやすく、皮膚の上に黒や褐色の小さな塊のように見えます。吸血が進むと灰色や淡褐色に膨らみ、皮膚のしこりと区別しにくくなることもあります。直接マダニを確認できなくても、皮膚を撫でたときにイボのようなふくらみがあったり、赤みや炎症が見られたりした場合は要注意です。
とくに寄生が多いのは、耳、まぶた、鼻の周り、首輪の下、わき、ひじや足指の間、内股や尻尾の内側など毛が薄く、皮膚が柔らかく体温の高い部分です。噛まれると、局所の腫れやかゆみのほか、発熱や食欲不振など全身症状をともなう場合もあります。
犬がマダニに噛まれたらどうなる
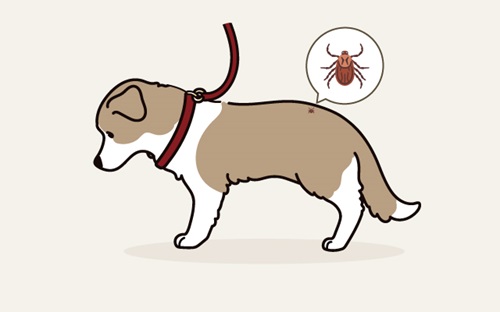
犬がマダニに噛まれると、局所の皮膚炎やかゆみだけでなく、貧血や発熱など全身に影響を及ぼすことがあります。ここでは、犬がマダニに噛まれたときの主な症状について解説します。
皮膚炎
マダニが犬の皮膚に吸着し吸血するときは、唾液が体内に注入されます。この唾液に含まれる成分が、アレルゲンとなり皮膚炎や炎症を引き起こし、強いかゆみや赤い発疹が生じます。患部が腫れることも多く、犬がしきりになめたり引っかいたりすると、脱毛や出血につながります。症状はノミアレルギー性皮膚炎や犬アトピーと似ているため、自己判断をせずに獣医師による診断が必要です。
貧血
犬がマダニに大量に寄生されると、長時間にわたり血を吸われることで、貧血を引き起こす危険があります。マダニは鋸状の口器を皮膚に突き刺し、数日間吸血し続けるため、小型犬ではとくに影響が大きくなります。さらに、マダニが媒介するバベシア原虫に感染すると、赤血球が破壊され溶血性貧血を起こし、発熱や血色素尿、脾腫など重篤な症状を伴うこともあります。
発熱
犬がマダニを介して感染するバベシア症では、赤血球が破壊されることで貧血や血色素尿に加え、発熱や黄疸といった症状が現れます。重症化すると多臓器不全に至る危険もあり、命に関わることもあります。また、ライム病では発熱や関節炎、けいれんなど全身症状がみられ、SFTSでは発熱に加え消化器症状や神経症状が起こり、死亡例も報告されています。
消化器症状
マダニを介して感染するSFTSでは、発熱に加えて嘔吐や下痢などの消化器症状がよく見られます。潜伏期間は6日~2週間で、食欲不振や強い倦怠感をともなうこともあるので注意が必要です。症状が進行すると頭痛や意識障害、さらには出血傾向を示す場合もあります。
神経症状
マダニが媒介するSFTSでは、発熱や消化器症状に加えて、神経症状が現れます。具体的には、強い頭痛や意識障害、けいれん、昏睡などで、症状が進行すると命に関わることもあります。
呼吸器不全
マダニ媒介性の感染症が進行すると、呼吸器にも深刻な影響を及ぼします。とくにSFTSでは、高熱や消化器症状に続き呼吸困難や肺炎のような症状が現れるケースがあり、重症化すると呼吸器不全に至ることもあります。犬の呼吸が荒い、息苦しそうにしているなどの異常を見せた場合は、感染症による合併症の可能性を疑いましょう。
感染症
マダニは犬や人にさまざまな病原体を媒介します。代表的なものに、致死率が高いSFTS、赤血球を破壊して貧血を起こす犬バベシア症、発熱や関節炎を伴うライム病、Q熱などがあります。これらは、犬だけでなく人にも感染する人獣共通感染症であり、命に関わる危険も少なくありません。予防のためには日常的なマダニ対策を徹底し、早期発見と治療につなげることが必要です。
| 病名 | 症状 |
|---|---|
|
重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) |
マダニが媒介するウイルス感染症。高熱、消化器症状(食欲低下、嘔吐、下痢)を中心に、頭痛や筋肉痛、出血傾向、意識障害などをともない、重症化すると死亡例も報告されている。 |
| 犬バベシア症 | バベシア原虫が赤血球に寄生して破壊する病気。急性期には発熱、貧血、血色素尿、黄疸などが見られ、進行すると重度の貧血や多臓器不全を起こし命に関わる危険性も。 |
| ライム病 | マダニを介してボレリア菌に感染する細菌性疾患。犬では発熱、食欲不振、関節炎、歩行異常などの症状が出ることがあり、人では頭痛や筋肉痛、神経障害なども発症する。 |
| Q熱 | コクシエラ・バーネッティという細菌による感染症。犬では発熱や倦怠感、呼吸器症状などがみられ、人にもうつる人獣共通感染症で、重症化すると肺炎や肝炎を起こす場合がある。 |
感染症は人間にもうつるため注意が必要

マダニが媒介する病気のなかには、犬だけでなく人間にも感染する「人獣共通感染症」が含まれています。代表的なものには、致死率が高く有効な治療薬やワクチンが存在しないSFTS、発熱や関節炎、腎障害を引き起こすライム病、Q熱などがあります。とくにSFTSは、日本国内でも人の死亡例が報告されており、犬から人への感染経路も指摘されています。犬が草むらでマダニに寄生されると、飼い主も同時にリスクを負うことになります。そのため、ペットだけでなく、人も予防対策の徹底が重要です。日常的なマダニ予防薬の使用や散歩後のブラッシング、草むらを避けるといった工夫を心がけましょう。
犬がマダニに噛まれた時の対処法

犬にマダニが付いていても、無理に引き抜くことは危険です。口器が皮膚に残り炎症や感染を招く恐れがあるため、自己処理は避け、必ず動物病院で安全に除去してもらいましょう。ここでは、犬がマダニに噛まれたときの主な対処法を解説します。
無理に引っ張らない
犬にマダニが噛みついているのを発見したら、すぐに取りたいと思うかもしれません。しかし、マダニは頭部を皮膚に深く食い込ませて吸血しているため、無理に引き抜くと頭部だけが皮膚内に残ります。そのため、炎症や感染を引き起こす危険があります。また、潰してしまうと体内にもウイルスや細菌が放出され、犬や人への感染リスクが高まります。マダニは吸血力が非常に強く、手で簡単に取り除けません。無理やり剥がそうとせず、適切な方法で除去しましょう。
動物病院に連れて行く
犬にマダニが付いていたら、自己処理は避けて、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。動物病院では専用の器具を用いて安全に除去できるほか、駆除薬の投与により自然にマダニが落ちるのを待つ方法も選択できます。肉眼では確認できない場合も多いため、疑わしい症状があれば、早めの受診が大切です。
犬をマダニから守る方法

マダニは一度寄生すると除去がむずかしく、感染症を媒介する危険もあります。犬を守るためには、駆除薬や虫よけを使用するほかに、草むらを避ける、散歩後のブラッシングや庭の手入れなど、日常的な予防が欠かせません。犬をマダニから守るための方法を解説します。
駆除薬を投与する
犬をマダニから守るためにもっとも効果的なのが、動物病院で処方される駆除薬の定期的な投与です。スポイトタイプやチュアブルタイプがあり、安全性が確認された薬剤を使用することで、寄生しても24時間以内に駆除が始まります。感染症のリスクを大幅に減らせるでしょう。市販の首輪タイプは効果が限定的な場合も多いため、確実な予防には病院の処方薬が推奨されています。とくに、春から秋は、マダニの活動が活発になる時期であり、現在ではSFTSなどの感染症には有効なワクチンが存在しないため、なによりも予防が重要です。
ペット用の虫よけスプレーを使う
マダニは犬に皮膚炎や感染症を引き起こし、ときには命に関わる病気を媒介します。そのため、日常的な予防策として、ペット専用や犬専用の虫よけスプレーの活用が有効です。ただし、人間用のスプレーはディートやピレスロイドなど犬に有害な成分を含むことが多く、誤使用は皮膚炎や神経症状を招くリスクがあります。必ず「ペット専用」「犬専用」と記載された商品を選び、舐めても安全な天然由来成分配合のものを使用しましょう。レモングラスやユーカリなどの精油を利用した製品は、犬の皮膚にやさしく、防虫効果も期待できます。香料やアルコール、不要な添加物が含まれていないかも確認し、犬に負担をかけない商品の選択が大切です。
散歩中は草むらに近寄らない
マダニは草むらややぶ、河川敷などに潜んでおり、犬が散歩中に入り込むことで寄生してしまいます。とくに、春から秋は活動が盛んなため、なるべく草むらや野山には近寄らせないことが重要です。また、野良猫や予防していない犬との接触も寄生の原因となります。ドッグランやペットホテルなどを利用する際にも、マダニやノミ予防を実施している施設かどうかを確認すると安心です。散歩コースは、舗装された道や手入れされた公園を意識して選び、必要に応じて動物病院で適切な予防法を相談しましょう。日常のちょっとした配慮が、犬をマダニから守る大切な対策につながります。
散歩から帰ったらこまめにブラッシングする
散歩後のブラッシングは、マダニやノミの早期発見と感染症予防に欠かせません。草むらで遊んだあとは、体全体に汚れや寄生虫が付着している可能性があります。耳や足回り、背中、口やお尻の周りなど、毛の薄い部分を中心にチェックしましょう。黒い砂粒のようなノミの糞や、小さなしこりを見かけたら注意が必要です。ブラッシングとあわせて月1回程度のシャンプーをおこなうと、清潔を保ち皮膚病の予防にもつながります。シャンプーは必ずペット用を使用し、乾かしたあとはノミ取り用のクシで仕上げると効果的です。日々の習慣として取り入れることで、病気やケガの早期発見にも役立ち、犬の健康を守るための大切なケアになります。
庭の雑草を取り除く
庭はマダニの潜伏場所になりやすく、とくに、雑草が生い茂った場所や落ち葉のたまった環境は、温床になりやすいといわれています。犬を守るためには、定期的に草刈りや剪定をおこない、清潔な状態を保つことが大切です。落ち葉や雑草をこまめに掃除すると、湿気を防ぎ、虫の繁殖を抑える効果も期待できます。また、防草シートを敷くと、雑草対策と害虫対策の両方に有効です。さらに、レモングラスやミントなど、虫が嫌う香りをもつ植物を庭に取り入れるのもおすすめです。
まとめ
最後におさらいとして犬をマダニから守るために知っておくべき項目をまとめました。
マダニが生息する場所は?
マダニは、森林や公園、河川敷、庭など草木の多い場所に潜んでいます。犬の散歩に出かける時はなるべく舗装された道路を歩くようにし、草むらに近づかないようにしましょう。
犬にマダニが噛みついていたらどうすればいい?
マダニは皮膚に入り込んで血吸するため、無理に引っ張ると頭だけ皮膚の中に残ってしまうことも。そのため、マダニを見つけたら動物病院に連れていきましょう。
犬から人間にうつる感染症は?
犬から人間にうつる代表的な感染症は、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)、バベシア症、ライム病、Q熱などが挙げられます。特にSFTSは重症化すると死にいたるため注意が必要です。
マダニは犬に皮膚炎や貧血、発熱を引き起こすだけでなく、SFTSやバベシア症など命に関わる感染症を媒介する危険な寄生虫です。これらは、人にも感染する人獣共通感染症であり、飼い主自身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、犬にマダニを寄せつけない日常的な予防策が欠かせません。駆除薬や犬専用の虫よけスプレーを用いた対策、草むらを避けた散歩、帰宅後の丁寧なブラッシング、庭の清掃などの徹底が重要です。万が一寄生を見つけても無理に除去せず、速やかに動物病院で安全な処置を受けましょう。日頃の予防と早期対応こそが、犬と人の命を守る最善の方法です。
物件を探す





