ハリネズミの飼い方は?初心者必見の注意点や情報まとめ

そこでこの記事ではハリネズミの特徴や種類をはじめ、揃えておきたい飼育環境から具体的な飼い方まで、徹底解説していきます!
記事の目次
ハリネズミはどんな動物?

ハリネズミは名前には「ネズミ」と付いていますが、実はモグラの仲間で、日中は暗い巣穴で過ごす夜行性の小動物です。よく見ると、鼻先が前に伸びたような顔付きがモグラに似ています。ちなみに日本でペットとして飼えるのは、「ヨツユビハリネズミ」のみ。他にも複数の種類のハリネズミが存在していますが、法的な規制により飼育できないルールになっています。
- 種類:哺乳綱 真無盲腸目ハリネズミ科
- 正式名称:ヨツユビハリネズミ
- 英名:Four-toed Hedgehog(フォートゥード ヘッジホッグ)
- 分布:中央アフリカ
- 体調:約15cm~25cm
- 体重:約200g~500g
- 寿命:約2年~5年
ハリネズミの特徴
ハリネズミの具体的な生態として、次のような特徴が挙げられます。
寿命は2~5年
ハリネズミは手のひらサイズの小さな生き物で、寿命はハムスターなどの小動物と同じ程度です。生後6カ月も経たない期間のうちに、人間でいう大人の体まで成長します。
全身にトゲトゲの針
ハリネズミといえば、背中全体を覆う硬い針です。針のようにはなっていますが、毛や爪と同じタンパク質でできています。何かに警戒した時にはこの針を立てて身を守ろうとしますが、普段は倒れた状態になっています。
臆病な性格
ハリネズミは警戒心が非常に強く、さらにマイペースな性格なのも特徴。基本的に単独行動を好み、人間とのスキンシップもあまりしない動物です。ただ、臆病ではあるものの、しっかりと信頼関係を築くことで飼い主に慣れてなついているような姿を見られる場合も。もちろん個体差はあるものの、場合によっては名前を呼ぶと近寄ってきたり、抱っこさせてくれたりするケースもあるようです。
好き嫌いが多い美食家
ハリネズミは昆虫や爬虫類などの動物のほか、果実や種子といった植物も食べる雑食性です。何でも食べるように見えますが、実はかなり好き嫌いがハッキリしているのも特徴。エサに飽きてしまうと、ある日突然これまで食べていたものを嫌がるケースもあります。
夜行性
ハリネズミは先ほども出てきたように、明るいうちは狭いすき間などに潜っていて、夜になると動きはじめます。日中のお世話にさほど手がかからないため、仕事などで昼間に家を空ける場合でも飼いやすいペットです。なお特に行動が活発なのは、夜中から早朝までの時間帯。場合によっては、夜間に回し車で遊んだりケージを噛んだりする音が気になる可能性があります。
泡を出す不思議な「アンティング」
何か今までにないにおいや味などを感じると、口の中でつくった泡とその物体を混ぜて体に塗る、アンティングと呼ばれる行動をする習性があります。明確な理由はわかっていませんが、新しい環境に適応するためともいわれています。
ハリネズミの種類

前述にもあるように、ハリネズミにはペットにできるヨツユビハリネズミを含め、さまざまな種類が存在します。さらにヨツユビハリネズミのなかでも、毛並みの色味によるカテゴリがあります。では以下から具体的に、どのようなハリネズミがいるのか見ていきましょう。
ハリネズミの種類一覧
| 種類 | 特徴 | 生息場所 |
|---|---|---|
| ヨツユビハリネズミ | ・さまざまなカラーがある ・日本で飼われているほとんどがこの種類 ・前足の指が5本で、後ろ足の指は4本 |
中央アフリカ |
| ナミハリネズミ | ・体全体を茶色の毛が覆う ・ハリネズミのなかでも体は大きめ ・毛が短く太い ・寒い地域に住む ・特定外来生物につき飼育禁止 ・北欧では害獣とされることも |
ヨーロッパ全域 |
| オオミミハリネズミ | ・耳が大きく立っている ・乾燥した草原や穴に住む ・以前は日本でもペットにできた ・現在は特定外来生物につき飼育禁止 |
中近東~中央アジア |
| アムールハリネズミ (マンシュウハリネズミ) |
・森や草原に住む ・日本でも野生種が見られる ・特定外来生物につき飼育禁止 |
中国を中心としたアジア |
| ブラントハリネズミ | ・体全体を黒色の毛が覆う ・四肢と耳が少し長め |
中東 |
| エチオピアハリネズミ | ・他のハリネズミに比べて体が小さめ ・顔が黒く、お腹は白い ・希少種 |
中東~北アフリカ |
ハリネズミの種類は幅広く存在しますが、表内でもあるように法律や輸入などの問題から、ヨツユビハリネズミ以外は国内で流通していません。とはいえヨツユビハリネズミにも、次のように個性豊かなカラーバリエーションがあります。
ヨツユビハリネズミのカラーバリエーション
| カラー | 特徴 | 費用相場 |
|---|---|---|
| スタンダード (ソルト&ペッパー) |
・背中の針が、白地に黒や濃い茶色のまだら ・皮膚や顔は黒やこげ茶色 ・よく見かけるポピュラーなノーマル色 |
5,000円~ 3万円 |
| シナモン (シニコット) |
・背中の針が、白地に薄茶色のまだら ・皮膚や鼻はピンク色 ・顔はお腹と同じく白め ・茶色味が濃いとシナモン、淡く薄いとシニコットと分類することもあるが、区別されないことも多い |
1万円~ 3万円 |
| アプリコット | ・背中の針が、シナモンやシニコットよりもさらに薄いオレンジ色 ・皮膚や鼻はピンク色 ・顔はお腹と同じく白め |
1万5,000円~3万円 |
| アルビノ | ・メラニン色素がない ・皮膚や鼻はピンク色、他はすべて白色 ・目は赤色 |
1万5,000円~3万円 |
| ホワイト | ・背中の針は白色 ・皮膚は黒く、鼻や顔周辺も黒っぽい ・希少種 |
2万円~ 3万円 |
| パイド | ・背中の針の色にバラつきがあり、カラーリングが混ざっている ・希少種 |
2万円~ 5万円 |
ヨツユビハリネズミのなかでも、針の色が薄めだったり不規則だったりするのは、レアな種類。また価格設定は販売元によって異なるため、それぞれで値段には幅がありますが、珍しい種類も合わせて大体1万円~4万円が相場です。
ハリネズミを選ぶ時のポイント
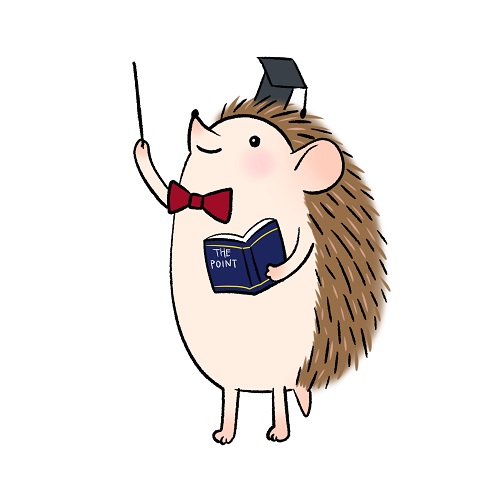
ではいざハリネズミをお迎えする場合に、あらかじめ確認しておきたいポイントについてもご紹介します。
購入先を確認する
- ペットショップで購入する
- ブリーダーから購入する
- 動物保護団体から引き取る
- ハリネズミカフェで引き取る
動物愛護法により、生体は対面販売が義務となっているため、基本的にネット通販はありません。例えばWebページにて、販売しているハリネズミたちを紹介しているケースはありますが、対面説明と実物確認をおこなう必要があります。なお一般的な販売元はペットショップやブリーダーですが、ハリネズミカフェからお迎えすることも可能。また動物保護団体から引き取る方法もありますが、初心者だと里親の審査に通らないケースもあるので注意しましょう。
また場合によっては不当にハリネズミを販売しているケースもあるため、購入先のお店やブリーダーの情報は事前に調べておくことも重要です。不正な販売元では、適切な飼育環境が整えられておらず、体が弱っていてすぐに死んでしまうケースもあります。正当な販売元と正しく取引するためにも、あらかじめしっかりとチェックしておきましょう。
ハリネズミの様子を確認する
ハリネズミが弱っている状態でお迎えした場合、環境の変化に対応しきれず、さらに健康状態が悪化してしまうケースがあります。特にはじめて飼う際には、うまくお世話ができない可能性も。できるだけ元気な子をお迎えできるように、あらかじめ購入先では健康状態をチェックすることも大切です。例えば次のような部分は、よく見ておくことをおすすめします。
- 目・鼻・口・耳・肛門周辺に、汚れやキズがなく衛生的
- 足・針・被毛に異常がない
(腫れ・抜け落ち・変色など) - 便が正常
- 体重が軽すぎない
またハリネズミは日中だと活動的ではないので、夜間の様子を動画などで確認させてくれるお店もあります。その際には、活発に動き回っているか・食欲はあるか、といった行動もしっかりチェックしましょう。
性格を確認する
どのハリネズミも、基本的には臆病でナイーブな性格ですが、個体ごとに気質には違いがあります。なかには人間になつきやすく、比較的早くから警戒心を解いてくれる子も。はじめてハリネズミを飼うなら、慣れないうちでもうまく接していけるように、あまり怖がりではない子を選ぶのが無難。例えばケージに近付いても逃げないなど、なるべく人間に慣れている様子が見られるほうがおすすめです。
年齢や性別の基本情報を確認する
ハリネズミを迎えるのに適した年齢は、大体生後2カ月~3カ月といわれています。赤ちゃんに近い年齢で販売されている場合、かなり早くから母親と離れ離れになってしまい、相当なストレスを受けている可能性も。そうなると体が弱かったり警戒心がより強くなっていたりするケースもあるため、月齢が低すぎる際には要注意です。また生後半年以上の成体なら問題ありませんが、月齢が低いほど新しい飼い主に慣れるまでに時間がかかりやすくなる傾向にある点は、覚えておくとよいでしょう。
ちなみに性別やカラーによる性格の違いはさほどありませんが、オスだと発情期で攻撃的になることがあります。慣れない初心者なら、メスのほうがいいかもしれません。
ハリネズミに必要なお世話
できるだけ元気に長く一緒に暮らしていくためには、当然ながら丁寧なお世話が不可欠です。しっかりとケアをしていくうちに、お互いの信頼関係にもつながっていくもの。では以下から、具体的な飼育方法を見ていきましょう。
ご飯のあげ方
ハリネズミは雑食で基本的に何でも食べますが、メインのエサは、きちんとバランスよく栄養摂取ができるハリネズミ専用のペットフードにします。ハリネズミは夜行性なので、夜の1日1回、大さじ1~2杯程度のペットフードを与えるようにしましょう。ただしハリネズミは美食家なので、いつも同じエサだと飽きてしまうことがあります。
そのためペットフードは複数の種類を不規則に出したり、ささみやゆで卵などの副食やおやつをあげたりするのがおすすめ。昆虫やミルワーム(虫の幼虫)などの生餌や乾燥したものは、ペットフードを拒否するようになる場合もあるので、たまにご褒美として与える程度がよいかもしれません。またエサをあげる時には、合わせて水も交換するようにしましょう。
トイレのしつけ方
ハリネズミは怖がりなので、一般的にしつけは難しいとされています。トイレについても、基本的に場所に関係なく排せつするので、なかなか教えられない場合が多いでしょう。ただしハリネズミのなかには、固定の場所で排せつする個体もいて、工夫次第ではトイレを覚えてくれるケースもあります。
例えば排せつした便をトイレに置いておいたり、いつも排せつするポジションにトイレを設置したりすると、自然とトイレができるようになることも。またハリネズミは、普段狭くて暗いところにいるので、部屋の隅など安心できるスペースにトイレをセットしておくのがおすすめです。
お手入れの仕方
ハリネズミはほとんどの時間をケージ内で過ごすので、汚れも溜まりやすい一面があります。動きながら排せつすることもあるため、ケージの床材は1週間に1度は掃除して交換するようにしましょう。ただし完全に自分のにおいがなくなってしまうと、ハリネズミは不安になってしまいます。そのため前の床材を少し残しつつ、きれいにしてあげましょう。ケージ全体や巣箱(寝床)は2~3カ月に1回、回し車は1~2週間に1回掃除します。
またハリネズミの体が汚れてしまったら、軽く拭いてあげるようにします。濡れたタオルやウェットシートを使うか、足の汚れならぬるま湯ですすぐ方法もよいでしょう。さらに爪も伸びてくると、どこかに引っかけてしまって危険なので、こまめに長さを見ながら定期的にカットします。
ハリネズミの飼育に必要なもの

ハリネズミの健康的な毎日のためには、きちんとした飼育環境も欠かせません。ハリネズミをお迎えする際に、事前に用意しておきたい飼育用品をご紹介していきます。
ケージ
ハリネズミのケージには、回し車や寝床になる巣箱なども設置するので、なるべくスペースにゆとりがあるタイプがおすすめです。大きさの目安としては、面積が60cm×90cm以上、高さは40cm~50cmはあるとよいでしょう。ケージの種類としては、ステンレスの金網式や、アクリル(水槽)式の2つに分けられます。風通しがいいのは金網式、保温性が高いのはアクリル(水槽)式とそれぞれ特徴があるので、部屋の環境も考慮して選んでいきましょう。
エサと水とお皿
毎日のお世話には、エサ入れと給水器も必要です。いずれも特に指定はありませんが、エサ入れはハリネズミが食べやすい浅めのお椀タイプ、給水器はケージに取り付けできるボトル式がおすすめです。またエサは先ほども出てきたように、主食としてハリネズミ専用のペットフードを用意。あわせて副食やおやつ用に、ミルワームといったエサ用の昆虫類を準備しておくとベターです。
床材
床材は、次のような吸湿性や消臭性のあるものをおすすめします。
- ペットシーツ
- ウッドチップ
(ポプラやアスペンなどの広葉樹)※針葉樹ではアレルギーが出る可能性あり - コーンリター
(トウモロコシの芯などの天然素材)
上記のものなら誤飲の危険性も低く、安全かつ衛生的です。なお新聞紙で代用するケースも見られますが、インクの成分がハリネズミにとって害になるリスクがあるため、できれば避けたほうが無難。きちんと床材としての機能性があるものを選ぶのがベストです。
トイレ
トイレを覚えさせたい場合には、ケージのコーナーなどに置けるものを用意しておくと便利です。ハリネズミは動きながらでも排せつするので必須ではありませんが、トイレトレーニングを考えるなら事前に準備しておきましょう。
隠れ家となるような巣箱
ハリネズミには、天敵から身を守るために物陰に潜り込む習性があり、安全と感じられるような隠れ家が必要です。また日中は暗くて狭い場所で眠るので、健康的な睡眠のためにも、すっぽり身を潜められる巣箱を用意しておきましょう。どのようなタイプでも構いませんが、ハリネズミが余裕を持って入れる程度の大きさがあるものにします。
運動するためのホイール(回し車)
夜間に動き回って遊んだり、爪の伸びすぎを防いだりするためにも、その場で走れるホイール(回し車)も準備します。大きさの目安は30cm程度で、もし音の心配がある場合には、静音タイプを選ぶとよいでしょう。
温度調整・確認する器具
暑すぎても寒すぎても、ハリネズミにとって危険な休眠状態になってしまうため、エアコンやペットヒーターといった温度管理のための設備は欠かせません。基本的に室温が判断できれば問題ありませんが、できればケージに取り付けられる温度計がベストです。小鳥用や小動物用の計測器も市販されているので、活用してみることをおすすめします。
お手入れ用具
ハリネズミのケア用品としては、次のようなものを用意しておくと便利です。
- 爪切り(病院でも対応可)
- 皮膚の洗浄スプレー、スキンケア用品
(シャンプーができない代わりに汚れ取りとして使用) - 防ダニスプレー、消臭スプレー
(ケージの掃除用) - 革などの手袋
(ハリネズミの針による怪我防止)
キャリーバッグ
病院などの移動用に、キャリーバッグも準備しておきましょう。持ち運びができる程度で、ハリネズミがきちんとなかに入れる大きさがあれば、どのようなタイプでも基本的にはOKです。うさぎなどの小動物用のキャリーバッグもいくつか市販されています。
ハリネズミを飼うのに必要な費用
では先ほどご紹介した飼育用品をふまえて、まずハリネズミを飼う場合に、あらかじめ想定しておきたい初期費用から見ていきましょう。
初期費用
| 項目 | 相場 |
|---|---|
| 生体価格 | 1万5,000円~4万円 |
| ケージ | 5,000円~1万円 |
| エサ(ペットフード) | 1,000円~2,000円 |
| エサ入れ・給水器 | 1,000円~2,000円 |
| 床材 | 1,000円~2,000円 |
| トイレ | 2,000円前後 |
| 巣箱 | 2,000円~4,000円 |
| ホイール(回し車) | 3,000円~4,000円 |
| 温度計 | 1,000円~2,000円 |
| お手入れ用具 | 6,000円前後 |
| キャリーバッグ | 2,000円~3,000円 |
ここまでの初期費用を合計すると、必要なコストは3万9,000円~7万7,000円。特に生体価格には差があるので、それを除いて考えても、飼育用品だけで2万4,000円~3万7,000円はかかる計算になります。大まかにではありますが、生体価格+3万円前後になるのが平均と想定しておくとよいでしょう。この他にも、部屋にエアコンがなければペットヒーターなども追加で必要です。
月々にかかる費用
| 項目 | 相場 |
|---|---|
| エサ(ペットフード) | 1,000円前後 |
| 副食(虫類) | 500円前後 |
| おやつ(野菜・肉・甘味系) | 500円前後 |
| 床材 | 1,000円前後 |
| トイレ砂 | 1,000円前後 |
上記を合計すると、月々の維持費は4,000円程度。加えて夏場や冬場は温度調整をする点を考慮すれば、実質的にはさらに数千円ほど上乗せになるイメージです。
ハリネズミを飼う時の注意点

ハリネズミは体も小さく繊細な動物で、長生きしてもらうためには、さまざまな配慮が必要です。それでは、特に気を付けておきたい注意点をご紹介します。
なつかない場合が多い
元々の生態として、ハリネズミは単独行動をする生き物のため、1匹でマイペースに過ごすことを好みます。人間に対しても、なついてすり寄ってくるようなケースは、基本的にありません。ただし飼い主の存在に慣れることはあるので、近付いても怖がらなくなったり、手に乗せても拒否しなかったりする場合はあります。とはいえ個体によっては、まったく慣れてくれない子も。臆病な性格は、ハリネズミの標準的な本能なので、受け入れてそっと遠くから見守ってあげるのも愛情です。たとえなかなか慣れてくれなくても、根気よく温かく接してあげましょう。またスキンシップのしすぎは、ハリネズミにとってストレスになってしまうため、いくらかわいくても、ほどよい頻度でコミュニケーションをするようにしましょう。
偏食家で栄養バランスが崩れやすい
ハリネズミは食べ物の好き嫌いが激しく、自分の好みでないエサは食べません。だからといって好きなものばかり与えていると、うまく栄養摂取ができなくなってしまいます。同じエサだと飽きてしまうこともあるため、あらかじめ数種類のエサを用意したり適宜変えたりなど工夫しましょう。場合によっては、ハリネズミの好きなミルワームや火を通したお肉など、ペットフードにトッピングしておいしく食べさせてあげる方法もあります。特になかなか食べてくれない時には、少し手を加えてあげるのがおすすめです。
温度は高くても低くてもダメ
ハリネズミは暑さにも寒さにも、さほど強くありません。ハリネズミにとっての適温は24度~29度なので、きちんと一定の室温に保てるように調整しましょう。エアコンなどとの併用の例としては、夏場なら、扇風機やひんやりマットなどを使って、なるべく涼しい環境をつくります。また冬場なら、保温電球を付けたり、寝床を毛布材にしたりして暖かくしてあげましょう。
床暖房の真上にケージを置かない
冬の寒さ対策で気を付けたいのは、暖まりすぎてしまう点です。特に床暖房はケージの保温に効果的ですが、直接ヒーターの上に置いてしまうと、熱がこもって暑くなりすぎてしまいます。部屋自体に床暖房を付けても問題ありませんが、ケージの設置場所には注意しましょう。
静かで落ち着く部屋で飼育する
ハリネズミは臆病でナイーブな性格に加えて、聴覚や嗅覚にも優れていて敏感です。あまりがちゃがちゃと音がしたり振動があったりすると、ハリネズミにとってストレスになってしまうので、部屋のなかでもできるだけ静かな場所にケージを置くようにしましょう。おすすめなのは、あまり人が通らない部屋の隅など。その反対に、テレビやスピーカー付近・玄関などの出入り口・歩く気配が伝わりやすいドアなどは、避けるようにしましょう。
こまめに健康チェックをする
ハリネズミはダニなどよる皮膚病になりやすく、毎日の健康チェックが欠かせません。衛生的な環境を保つのはもちろん、掃除の際にフケや針が落ちていないかなど、ケージの中の様子もきちんと確認しましょう。他にも、腫瘍や歯周病、ハリネズミ特有の神経病のハリネズミふらつき症候群などの疾患になりやすい一面があります。体や行動に異変がないかこまめに確認しつつ、動物病院の定期的な健康診断を受けることもおすすめします。
ハリネズミの飼い方に関するよくある質問

初心者にとって、ハリネズミは飼いやすいですか?
ハリネズミは夜行性で日中は寝ていて、昼間のお世話にも手がかかりにくく、初心者でも飼いやすいペットです。ただし飼い主になつきにくい一面があり、人間に慣れるまでは根気よく、徐々にコミュニケーションを取らなければなりません。またエサやりも1日1回ですが、偏食になりやすく工夫しながらご飯を与える必要がある点も、少し難しく感じる可能性はあります。
賃貸でもハリネズミを飼っていいですか?
ペット可の物件であれば、基本的にハリネズミをはじめとした動物は飼っても問題ありません。ただし飼育できる種類が決まっているケースもあるため、ハリネズミを飼う際は、管理会社などに確認する必要があります。
ペット不可の物件でもハリネズミは飼える?
前述にもあるように、原則はペット可の物件でないと、ハリネズミも含めてどのような動物だとしても飼育できません。ただしペット不可でも、管理会社やオーナーに交渉・相談をすれば、場合によっては許可してもらえる可能性もあります。とはいえ基本的にはペット不可が前提条件なので、認めてもらいにくいと考えたほうが無難でしょう。
またペット可の物件でも、ペットを飼う際には報告義務があり、敷金が追加されるケースがあります。もし報告せずに飼いはじめてしまうと、バレてしまった時には契約違反で強制退去になったり、ペットを手放さなければならなかったりする場合も。悲しい思いをしないためにも、きちんとルールは守って飼うようにしましょう。
飼育可でも気を付けること
ペット飼育ができる物件でも、できるだけトラブルを防ぐためには、次のような点にもしっかりと注意しておきましょう。
壁紙や床にキズをつけない
ハリネズミはあまり視力がよくないため、鼻でにおいを確認しながら移動したり食べ物を探したりします。その際に壁紙などをかじってしまう場合もあるため、しっかりと養生しておきましょう。保護シートやクッションフロアなどを利用すると、内装にキズを付けずに済みます。
騒音が漏れないように気を付ける
ハリネズミは夜間に動き回るので、特にホイールを回す音には注意が必要です。壁が薄いと、カラカラする音が近隣に響いてしまうケースもあります。静音タイプのホイールを選ぶか、夜間は音の伝わりにくい場所にケージを異動させるなどの対策が必要です。
逃げ出さないようにすき間を埋める
ハリネズミは小さいので、どこかすき間があると、そこから逃げてしまう可能性もあります。ハリネズミの頭よりも大きな穴などがある場合には、きちんと埋めておきましょう。また例えばケージから出した時に、窓が少しでも開いていると脱走してしまうかもしれないので、戸締りにも注意しましょう。
ハリネズミを飼うための物件探しのポイント
ハリネズミとより快適に長く過ごせる物件を探すには、次のような点も考慮しておきましょう。
ペット可(相談可)物件を探す
物件探しをしている段階からハリネズミを飼うことが決まっているなら、はじめからペット可を条件として物件を選びましょう。ペット不可の物件から交渉するのは難易度が高いためです。そのなかでも、ハリネズミの飼育が許可されているか事前に確認しておくと、より物件探しもスムーズにできます。
飼育する部屋にエアコンが付いている
今までにも出てきているように、ハリネズミは徹底した温度管理が欠かせません。エアコンがないと室温の調整が難しいため、安全な飼育環境を維持するためにも、空調設備の整った物件を選ぶようにしましょう。空調設備がない場合は、後から自分たちで設置手配することが出来るか、確認が必要です。
周辺にハリネズミを診療可能な動物病院がある
ハリネズミは、エキゾチックアニマルとも呼ばれる、ペットのなかでは特殊な小動物です。動物病院のなかには、犬や猫は診療できても、ハリネズミは受診できないケースもあります。いざという時にすぐにでも頼れるように、あらかじめハリネズミも診てもらえる動物病院があるか、必ず確認しておきましょう。何かあってから病院を探すのでは遅い場合もあるので、なるべく自宅の近くで、ハリネズミも受診できるところがないかチェックしておきます。
まとめ
ハリネズミは初心者でも比較的飼いやすく、においや鳴き声もあまりない人気のペットです。なつくのは難しいとされていますが、慣れてくれればかわいい行動もたくさん見せてくれます。また当然ながらハリネズミをはじめ、どのペットを飼うのにも、適切な飼育環境やお世話は必須。こまめな健康チェックやケアはもちろん、特にケージを置く部屋自体の温度管理なども大切です。ハリネズミを飼う場合には、一緒に暮らす部屋選びから配慮が必要。もし賃貸なら、まずは飼育できる物件なのか、必ず事前に確認しましょう。ハリネズミにとっても快適な住まいに配慮しつつ、愛らしい姿に癒されながら絆を深めていってくださいね。
物件を探す





