【初心者向け】アクアリウムの作り方は?必要なもの・注意点も解説!

そこで今回は「アクアリウムに挑戦してみたい!」という初心者さんに向けて、水槽の立ち上げ方法などの作り方をご紹介。ぜひ、アクアリウムのスタートガイドとして、参考にしてみてください!
記事の目次
アクアリウムとは?

アクアリウム(Aquarium)とは、和訳して水族館との意味も持つ言葉で、おもに水中生物を飼育して鑑賞する設備を指します。水槽の中に水草や魚などの水中生物の生息環境を整えて、自然さながらの風景を自宅で楽しめるのが特徴。またアクアリウムは、大きく分けて海水式と淡水式の2種類があります。海中生物を飼うなら海水式、川の水中生物なら淡水式のアクリアリムになります。
アクアテラリウムとの違い
アクアリウムについて調べていると、似たような言葉として「アクアテラリウム」が出てきたこともあるかもしれません。「テラリウム」とは、陸上の植物などをメインとした飼育環境を指します。水中生物によるアクアリウムと、陸上植物によるテラリウムを混在させて作るのが、アクアテラリウムです。アクアテラリウムでは、水中と陸地の両方の生息環境を再現でき、さまざまなアレンジを効かせた水辺の風景を生み出せるのが魅力。なお本記事では、このアクアテラリウムも含めて、アクアリウムとしてご紹介していきます。
アクアリウムを始める時の予算は?

アクアリウムでは、使用する設備や飼育生物などに応じて、必要な費用は大きく変わります。いくらでもコストをかけられてしまうものなので、あらかじめ予算を決めておくのがおすすめ。ちなみにアクアリウムは、1,000円台からでも十分に楽しむことが可能。まずはどれくらいお金をかけるのか、ある程度の目安を前もって決めておきましょう。ではそれぞれの予算ごとに、どのようなアクアリウムができるのか、大まかなイメージをご紹介します。
1,000円からのアクアリウムでできること
予算を1,000円程度に抑えようとすると、本格的な水槽にするのは難しいですが、小瓶や金魚鉢などを使った小型のボトルアクアリウムなら可能です。サイズ感の目安としては大体10cm~20cmで、コンパクトな卓上のアクセントにもぴったり。ちなみに「メダカ」や「アカヒレ」などの小さい魚1匹+水草程度なら、小型のボトルアクアリウムでも飼育できます。また貝殻やオブジェなど、数百円で買える装飾アイテムもあるので、ちょっと工夫すればリーズナブルにおしゃれなアクアリウムが作れます。
5,000円からのアクアリウムでできること
もう少し予算を上げて5,000円程度で検討してみると、サイズ感はコンパクトになるものの、きちんとした水槽のアクアリウムができます。なかには1,000円~2,000円台で購入できる、ろ過装置やカルキ抜きなどの基本の飼育用品も含めた水槽セットも市販されていますよ。20cm~30cmほどの水槽なら、小さい魚数匹+水草とあわせて、照明や装飾なども加えたアクアリウムを楽しめます。
10,000円以上のアクアリウムでできること
予算を10,000円以上かけられる場合には、ある程度の大きさの水槽を使った、より本格的なアクアリウムにできます。もし10,000円台に抑えるとすれば、45cm程度の水槽なら、装飾も含めて少し凝った飼育環境を整えることが可能。10,000円台を超えても問題なければ、60cmほどの大きめの水槽も選べるようになります。もちろん飼育できる生物の幅も広がるので、飼いたい魚や水草にこだわりがある時には、10,000円以上で検討してみることをおすすめします。
一般家庭で設置できる水槽のサイズは120cmまで
特に予算を気にしないのであれば、水槽もかなり大きめのタイプを選べますが、一般住宅に設置できるサイズには限度があります。特に注意したいのは、完成後の水槽の重さ。アクアリウムの水槽には、水・生体・飼育用品・装飾アイテムなどが入るので、最終的にはかなりの重量になります。そのためあまりに水槽が大きすぎると、家の床が抜けてしまう可能性も。こうした重さの分を考えると、自宅で使える水槽のサイズは、大体120cmまでといわれています。
120cmにもなると水槽用のスペースとして十分な広さを確保したうえで、さらに専用の設置台なども必要です。また大きめの水槽になると、初期費用はもちろん、設備の維持費用などのランニングコストも高くなります。大型のアクアリウムにしたい時には、あらかじめ資金面もしっかりと検討しておきましょう。
アクアリウムを作るのに必要なもの

ではここからはアクアリウムをはじめるにあたって、なるべく初期段階で揃えておきたい、必要アイテムをご紹介していきます。
最初に準備するもの
まずはアクアリウムの基本となる、飼育する生体や生息環境に必要な各種用品から見ていきましょう。
水槽
先ほども出てきたように、水槽の種類は予算に合わせて決めていきます。ちなみに自宅におけるアクアリウムの水槽のサイズで一般的なのは、30cm~60cm程度。きちんと水を入れて飼育できる深さがあれば特に問題はありませんが、なかにはアクアリウム専用タイプも市販されています。はじめてのアクアリウムであれば、専用タイプを選ぶのが無難でしょう。
魚
はじめてのアクアリウムで魚を選ぶ場合には、できるだけ飼育しやすい種類にします。まだお手入れに慣れない初心者のうちは、お世話の難易度があまり高くない種類のほうが、長生きもしてもらいやすくて安心。ちなみに初心者でも飼いやすい魚には、水質や水温などの環境変化に強い・人口飼料のエサを食べて食欲旺盛・病気にかかりにくい丈夫な体質といった特徴があります。また体が大きくなりにくい種類にしておくと、成長後の水槽の入れ換えなどの必要がなくておすすめ。
生体価格も、最初のうちは比較的リーズナブルだと買いやすいでしょう。なお初心者向きの魚の代表例としては、「アカヒレ」・「ネオンテトラ」・「グッピー」・「メダカ」・「金魚」などの淡水魚類。人気の「カクレクマノミ」なども飼いやすい種類ではありますが、海水魚なので水質調整が難しい点には注意しましょう。
エサ
エサは、飼育する生体に適した種類を選ぶのが基本です。ちなみに魚のエサの種類としては、人口飼料であれば、フレーク・顆粒・ペレット・タブレットなどがあります。なお中型や大型になると生き餌(稚魚や虫など)を食べるケースもありますが、一般的な小さい熱帯魚なら、先ほどの人工飼料で問題ありません。魚の種類ごとなどに分かれた専用のエサも多いので、実際に飼う生体に合わせて用意しましょう。
ここからのアイテムは、アクアリウムの規模や予算に応じて、必要か取捨選択しながら用意しましょう。
カルキ抜き剤
水道水には、魚には有害とされる、消毒用のカルキ(塩素)が含まれています。水槽に水道水を入れる際には、必ずこのカルキを取り除く必要があるので、あらかじめ準備しておきましょう。確実なのはアクアリウム用のカルキ抜き剤ですが、水を沸騰させる・日光に1日~2日間ほど当てるなどの方法もあるので、少しでも節約したい時にはおすすめです。
流木・水草など装飾品
予算に余裕がありそうなら、魚に加えて流木や水草などの装飾品もあると、おしゃれな雰囲気が出ます。その他にも個性的なオーナメントなど、アクアリウムの装飾品には幅広い種類があるので、好みに合わせて自由にアレンジしてみましょう。ちなみに水草は生きた植物だけでなく、コストが抑えやすいフェイクグリーンにするのもおすすめ。なお水草を入れる時には、ピンセットがあると植える作業がしやすく便利です。
砂・石など水槽内の下に敷くもの
基本的に砂や石などは、水草の固定や栄養補給のために敷くので、植えない場合には用意しなくても問題ありません。とはいえ砂や石などの敷材があったほうが、水質を保ちやすいメリットもあります。また砂や石が敷いてあると、アクアリウムの雰囲気も出やすいので、予算があれば準備しておくのがおすすめです。
ヒーター
アクアリウムを作るときにヒーターを用意すると安全です。一般的な熱帯魚は25度くらいの水温がベストとされており、寒い冬場には室温などを調整しながら、水が冷たくなりすぎないように管理する必要があります。特に寒さが気になりそうな部屋であれば、水槽の保温用のヒーターを用意しておくと安心でしょう。
クーラー
部屋の冷房で調整できそうな場合には、用意しなくてもさほど問題はありませんが、必要に応じて水温を下げるクーラーがあると便利です。もちろん部屋のエアコンでも水温維持はできるので、状況や予算に合わせて検討してみましょう。
ろ過装置
金魚やメダカなどの水質変化にも強い種類なら、こまめな水の入れ換えをする時に、ろ過装置はなくても問題ありません。とはいえ生き物を飼っている以上、水槽の水はどうしても汚れてしまうので、衛生的には用意しておくのがベストです。ちなみにろ過装置にもさまざまな種類があり、飼育する魚や水槽の大きさに合わせて、適したタイプを選ぶようにしましょう。
照明
照明を設置することで、おもに水草に光を当てて生育させる効果があります。また魚の体調が安定しやすくなる利点もあり、特に日光が入りづらい場所にアクアリウムを置く場合には、水槽用の照明があると便利です。
比重計
比重計は、海水生物を飼育するアクアリウムを作る場合に欠かせません。海水生物を飼うには、人工海水を用意する必要があり、適切な塩分バランスになるように調整する際に比重計を使います。なおアクアリウムの水槽に入れる海水は、通常の食塩ではなく、専用の人工海水の素を使用。比重計とあわせて準備しておきましょう。
水質計器
きちんと水の入れ換えをして水質維持ができれば、基本的には水質計器は用意しなくても、さほど大きな問題はないでしょう。ただし環境の変化に敏感な魚などを飼う時には、水質計器があると、こまめに管理ができて便利です。
自動給餌機は、水槽に設置してタイマーでエサやりができる便利アイテムです。特に外出時間が長かったり、長期で家を空ける頻度が高かったりする場合におすすめ。なお成魚であれば数日ほど空いても問題ありませんが、特に稚魚の場合はこまめなエサやりが必要です。小さいうちから育てる時には、自動給餌機も検討してみるとよいでしょう。
お手入れの時に必要なもの
きちんと衛生的な生息環境を保つには、水の入れ換えや水槽掃除などのメンテナンスも欠かせません。日々のお手入れに向けて、以下のような清掃グッズも用意しておきましょう。
メラミンスポンジ
メラミンスポンジは、水槽に付着した汚れを取るのに便利なアイテムです。水槽の表面を傷付けずに汚れを落とせるうえに、ゴシゴシ擦らなくても簡単にキレイになるのでおすすめ。スーパーやドラッグストアでも市販されているため、簡単に購入できます。
ヘラ
ヘラは、おもに水槽にこびり付いたコケを除去するのに使う道具です。水槽を長くキレイに維持したい場合には、お手入れ用品としてヘラも準備しておくと便利でしょう。
ブラシ
ブラシは、ろ過装置などの水槽アイテムを掃除する際に使用します。ブラシ部分が細く小さくなったパイプ用のタイプにしておくと、より細かい部分のお手入れにも使いやすくておすすめです。
バケツ
水槽の水の入れ換えには、バケツがあると便利です。アクアリウムの水交換では、1回につき、全体の3分の1ずつ換えていくのが基本。その際に、水槽から吸い出した古い水を受け取るのにバケツを使います。水を溜められるなら、どのようなタイプでも問題ありませんが、あまりに小さすぎるものは避けたほうが無難。ある程度の水量が入るバケツのほうが、排水しやすいのでおすすめです。
ホース
ホースもバケツと同様に、おもに水槽の水交換に使用します。こちらも水槽からの水を問題なく流せるのであれば、どのようなタイプでもOK。なかには、簡単に水のくみ上げができるポンプ式のホースもあるので、必要に応じて用意しておきましょう。
【基本】アクアリウムの水槽の作り方は?
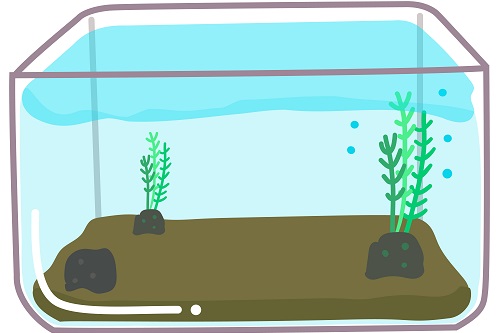
アクアリウムに必要なアイテムが揃ったら、水槽の中身を作ってセットしていきます。なおボトルアクアリウムなどのコンパクト型の場合、ろ過装置などは用意しない場合も少なくありません。なお以下にご紹介する手順は、おもに水槽のアクアリウムの設置方法です。実際に作りたいアクアリウムの形態に合わせて、どの工程が必要なのかも見ながら、参考にしてみてください。
- STEP 1水平な場所にマットなどを敷く
- STEP 2水槽に敷く砂・石を洗って敷く
- STEP 3ろ過装置をセットする
- STEP 4ヒーター・クーラーをセットする
水平な場所にマットなどを敷く
水槽が簡単に倒れてしまっては危険なので、必ず水平に安定した安全なスペースに置くようにしましょう。また滑り止めや水漏れ対策として、濡れてもいいマット(水槽マット・ゴムシート・布など)を敷いておくのがおすすめ。他にも照明やろ過装置など、電源が必要なアイテムを取り付ける場合には、コンセントの位置も考慮しながら設置します。
水槽に敷く砂・石を洗って敷く
水槽に水を入れる前に、砂や石は軽く洗って設置していきます。もし装飾アイテムもあれば、一緒にセッティングしていきましょう。なお砂を敷く場合には、ヘラがあると整地しやすくておすすめです。また水草は、ピンセットを使って、少し斜めに植え込むようにすると安定しやすくなります。
ろ過装置をセットする
ろ過装置は、商品のタイプごとに設置方法が異なります。水槽に取り付ける場合には、各商品の説明書をきちんと確認して、正常に作動するようにセッティングしていきましょう。
ヒーター・クーラーをセットする
ヒーターやクーラーを取り付ける場合も、ろ過装置と同じく、商品説明書を見ながら設置していきます。無事に必要なアイテムをセットできたら、水槽に水を入れて、各種装置がきちんと動きそうか一度確認してみましょう。また魚を入れる前に、水槽の水はカルキ抜きしておきます。そして特に問題がなければ魚も入れて、アクアリウムは完成です。
水草の下処理方法は?
水草は、通常ポットに入った状態で購入するので、下処理をして水槽に移し変える必要があります。水草の準備方法についても、以下から見ていきましょう。
ポットから外す
まずは根の周囲に付いたウールはそのままの状態で、水草をポットから取り出します。なお親株が大きい苗の場合は、必要な分だけカットして、水槽に入れるまで水に浸しておきましょう。
ウール(土)をほぐして取り除く
苗に付いているウールは、根や茎が傷まないように、ピンセットなどでキレイに取り除きます。水を張ったバケツなどに入れて、ほぐすように取っていくとスムーズです。なお苗のウールは、手に刺さって危険なケースもあるので、必ず素手ではなくピンセットなどの道具を使うようにしましょう。
傷んだ葉をカットする
もし枯れそうな古い葉があれば、水槽に植え込む前に取り除いておきます。
ビニールタイを巻く
例えば流木や石など、中身のアイテムに水草を取り付けて固定させたい時には、細いビニールタイを使うと便利です。水草の根付近にビニールタイを巻いておき、各種アイテムに固定させると、より自立しやすくなります。
【応用】アクアリウムのおしゃれなレイアウトは?

ここからは、よりセンス感のあるアクアリウムに見せるレイアウト術をご紹介していきます。特に水槽が大きめになると、さまざまなアイテムの配置にも迷いやすいので、まずは全体の構図から決めるのがコツ。ちなみにアクアリウムのレイアウトでは、次のような配置方法がよく見られます。
三角構図
「三角構図」は、水槽を真正面から見た時に、対角上で斜めになるように配置するレイアウト方法です。左右のどちらか片側に、背の高い水草などを固めて設置し、そこから階段状にだんだん下がるように各アイテムを置いていきます。そうすると、真正面からのレイアウトの全体像が三角形になることから、三角構図と呼ばれています。各アイテムが片側に集まるので、水槽内の余白のバランスが取りやすく、魚の泳ぐ姿も見えやすいのが特徴です。
凹型構図
「凹型構図」は、水槽を真正面から見た時に、中央部分がへこむような形に配置するレイアウト方法です。両サイドに背の高い水草などを置き、真ん中には横型の流木などの背の低いアイテムを設置。横に広がりのあるレイアウトなので、大きめの水槽で活用しやすい特徴があります。
凸型構図
「凸型構図」は、水槽を真正面から見た時に、中央部分が突き出たような形に配置するレイアウト方法です。先ほどの凹型構図とは反対に、背の高いアイテムを真ん中に集めて設置。すっきりとコンパクトにまとまりやすく、比較的小さめの水槽でも映えやすいのが特徴です。
放射構図
「放射構図」は、水槽を真正面から見た時に、各アイテムが中央部分からさまざまな方向に広がるように配置するレイアウト方法です。凸型構図にも少し似ていますが、放射構図ではもっと四方八方に広がるような、大胆なデザイン感になるのが特徴です。
おしゃれな水槽作りのコツ
ここまでにご紹介したレイアウト構図を活用しつつ、以下のポイントも押さえた配置にしていくと、よりおしゃれに見えやすくなります。
器具が見えないようにする
ろ過装置など、水槽内の器具が目に付いてしまうと、せっかくの自然にあふれる世界観が半減してしまいます。アクアリウムらしい幻想的な雰囲気を演出するなら、人工的なアイテムはできるだけ目立たないようにするのがベスト。例えば水草・流木・石などの装飾品で目隠しするなど、なるべく自然物だけ見えるようなレイアウトにしてみましょう。
水槽内に傾斜・段差を付ける
砂や石などの敷材を使う際には、平たく均して整地するよりも、傾斜や段差を付けたほうがメリハリのある印象になっておすすめ。例えば三角構図なら頂点にする片側、凹型構図なら両サイドの砂や石を高く盛ると、レイアウト感もくっきりとして見えます。水草や流木などの置物に加えて、水槽の底も使って傾斜や段差を付けると、立体感が出ておしゃれな演出ができます。
黒いバックスクリーンを使う
水槽を真正面から見た時の背景に、黒などのバックスクリーンを貼っておくと、奥側の目隠しができてデザイン性も高くなります。例えば水槽の背面に電源ケーブルや器具があると、真正面から見た時に目に入ってしまい、どことなく雑多な印象になりがちです。そこでバックスクリーンを付けることで、余分なアイテムを隠すことができ、よりスタイリッシュに見えます。もちろん再現したいデザインによっては、さまざまなカラーや柄を選ぶのもテクニックですが、慣れないうちはシンプルな黒を使うと無難です。
奥行きを意識する
水槽内の装飾は、奥から手前にかけて背が低くなるようにレイアウトすると、奥行きのあるおしゃれな印象にできます。手前のレイアウトが低くなっていると、視野が広がって立体感のある雰囲気になるのでおすすめ。例えば背の高い水草を奥に置いたり、砂や石を背面側が高くなるように敷いたり、奥行きを意識するとセンス感も出やすくなります。
アクセントを付ける
例えば、水草の緑のなかに流木を取り入れると、ウッドの茶色が映えてメリハリのある印象にできます。他にも、一部の水草に少し変わった色味の種類を入れたり、大きめの岩を配置してみたりなど、何かアクセントがあると引き締まって見えます。全体のカラーリングやテイストなどは、統一させておくとスタイリッシュですが、そのなかでもアクセントを付けるとおしゃれ感が増します。
アクアリウムを楽しむための注意点は?

できるだけ長くアクアリウムを楽しむコツとして、気を付けておきたいポイントも見ていきましょう。
昼夜をはっきりとさせる
魚も人間と同様に、自然のなかでは太陽の動きに応じた、一定の生活リズムで生息しています。基本的には魚も、太陽の出ている日中に活動して、暗くなったら体を休めるのが通常。例えば1日中明るい場所にいては、休息できるタイミングがなく、体調を崩してしまいます。特に夜間でも光が当たる状態になりそうな場合には、ダンボールや布などで水槽をカバーして、昼夜がわかりやすくなるように工夫しましょう。1日8時間ずつを目安に、水槽周りの明るさを調整するのがベストです。
水槽内に入れるものに気を付ける
拾った石や木などには、魚にとって有害な物質や生物が付着している可能性もないとはいいきれません。またフィギュアなどの塗装品も、魚への有害物質を発してしまうケースもあります。水槽内に入れる装飾アイテムは、必ずアクアリウム用に市販されている安全なものを選びましょう。ちなみにガラス玉もよく入れがちですが、水質を保つために必要なバクテリアが発生しにくくなる一面もあり、多用しすぎるのは避けたほうが無難です。
水交換は1週間~2週間に1回程度
水槽内の水は、1週間~2週間に1回ほど、全体の3分の1ずつを目安に交換するのがベストです。いきなり水槽内のすべての水を換えてしまうと、魚にとっては大きく生息環境が変わることになり、負担がかかりすぎてしまいます。元々の水をある程度は残して、少しずつ交換するようにすると、魚にとっても快適でキレイな水質を維持できます。
賃貸物件で安心してアクアリウムを楽しむために

アクアリウムは、魚などの生き物を育てながら楽しむもので、飼育する環境やメンテナンス方法にも注意しておく必要があります。特に賃貸物件で、快適かつ安全にアクアリウムを満喫するには、以下のような部分にも配慮しましょう。
ペット可物件を選ぶ
アクアリウムでは魚を飼育するのが一般的で、犬や猫と同じようにペットを飼うという一面もあります。基本的に賃貸物件では、貸主となる大家さんや不動産会社に無許可で、ペットを飼うことはできないのが原則。きちんとペットを飼うのが認められている物件でないと、魚を飼育するアクアリウムも設置できません。自宅でアクアリウムを楽しみたい時には、必ずペット可の物件を選んだうえで、大家さんや不動産会社にも事前に相談するようにしましょう。
水槽は専有部分に置く
他の荷物などと同じく、水槽は入居者の私物なので、必ず専有部分で管理するのが基本です。ちなみにベランダなどは共用部分になるうえに、緊急時の避難経路になるケースも多く、アクアリウムを置いてしまうと避難の妨げになってしまう可能性があります。アクアリウムを設置するのは、専有部分となる室内にしましょう。
ベランダの排水溝に水を流さない
ベランダの排水溝も共用部分になるため、アクアリウムのお手入れ時に水を流すのはNG。場合によっては水槽の砂や藻が流れて詰まってしまったり、隣のベランダまで排水が流れてしまったりする可能性もあります。他の入居者の迷惑にならないためにも、アクアリウムのメンテナンスは部屋でおこなうようにしましょう。
ろ過装置などの音に気を付ける
アクアリウムで使用するろ過装置・ヒーター・照明など、機器によっては稼働する音や光を発しやすい種類もあります。各種機器はなるべく消音タイプを選ぶなど、近隣の方々への迷惑にならないように工夫しておくのがベストです。
水槽の水漏れに気を付ける
水槽から水漏れしてしまうと、床などを濡らして傷めてしまい、退去時などに原状回復費用が発生してしまう可能性も。また水槽からの水漏れによって、家電やコンセントが濡れてしまうと、漏電火災の原因になる恐れもあります。必ず水漏れしないように、安全な場所に設置して管理するようにしましょう。
この記事のまとめ
アクアリウムは水中の世界観を鑑賞して癒しをもらえるだけでなく、慣れてきたら水槽を広げたり中身をアレンジしたりなど、幅広く楽しめるもの。どんどん自分なりのアクアリウムを追求できる、奥の深さが魅力です。また魚1匹程度を飼うコンパクト型であれば、比較的手軽に始めやすいのも特徴。ぜひ本記事を参考に、自分だけのアクアリウムを作り上げてみてくださいね。ではここから、アクアリウムの基礎知識を簡単にまとめていきます。
アクアリウムとは?
アクアリウムは、おもに魚や水草などの水中生物の生息環境を作って、飼育しながら眺めを楽しむ水槽鑑賞設備です。なかには陸上の水辺の植物と水の中の生き物を同じ水槽内で育てる、アクアテラリウムといった種類もあります。
アクアリウムを作るのに必要な予算は?
きちんとした水槽によるアクアリウムの場合、少なくとも5,000円は用意しておくのがベスト。より本格的な水槽にしたい時には、10,000円はあるとさまざまなアレンジもできます。なお簡単な構成のコンパクトなもの(ボトルアクアリウムなど)であれば1,000円程度ではじめることも可能です。
アクアリウムに必要なものは?
ボトルアクアリウムのようなコンパクトのものでも、最低限揃えておきたいのは、水槽・魚・エサ・カルキ抜きの4つ。さらに作りたいアクアリウムの種類・規模・予算に応じて、装飾品(水草や流木など)・敷材(砂や石など)・ろ過装置・ヒーターやクーラー・照明・比重計・水質計器・自動給餌器なども準備します。またお手入れ用品として、事前に水槽の掃除や水交換に使うアイテムも用意しておくと便利です。
アクアリウムを楽しむ時の注意点は?
アクアリウムを楽しむには、大前提としてペット可の物件を選ぶのが基本。また設置するのは室内の安全な場所で、水槽が傾いたり、落下の危険がないスペースを確保しましょう。また近隣の方々の迷惑にならないように、共用部分でのお手入れや各種機器の音などの十分な配慮も必要。生き物を育てるからこそ、物件の大家さんや不動産会社、ご近所さんとのトラブルにも注意して、より快適な飼育環境を整えましょう。
物件を探す





