ペットと引越しする方法とは?移動方法や手続きについて解説

記事の目次
ペットの引越し方法

ペットと引越すための方法は、主に3つあります。それぞれ、以下で確認していきましょう。
自分で連れていく
飼い主が自分で連れて行く方法です。キャリーに入れて自家用車に乗せたり、公共交通機関で一緒に移動したりします。ずっと飼い主がそばにいられるため、お互い安心して引越せるでしょう。
ただし、公共交通機関では通常運賃のほかに、「手荷物料金」が必要となることがあります。引越し先までの経路を確認し、各交通機関のルールを確認しておいてください。また、公共交通機関では周囲に他の乗客がいるため、鳴き声など配慮も必要です。
なお、ペットも長距離移動にストレスを感じてしまうケースもあります。遠くへ引越す際には、キャリーから出して少しストレス発散させてあげるなどの工夫も検討してください。
引越し会社へ依頼する
引越し会社のなかには、荷物だけでなくペットの運搬も対応してくれる場合があります。対応の可否については、依頼前の段階で確認しておいてください。ペットを気にせず移動できるので、飼い主側の負担は軽減されます。
ただし、ペットの運搬には費用が必要です。通常より高額になる点には注意し、事前に見積もりを確認してください。なお、対応可能な会社でもペットの種類を限定しているケースがありますので、同様に可否の確認が必要です。
ペットの輸送専門会社へ依頼する
ペットの輸送を専門におこなう会社へ依頼する方法もあります。特に初めてのことでペットとの引越しが不安だったり、長距離の引越しだったりする場合は、専門会社への依頼が安心です。移動中も休憩を設けてくれたり、水分補給してくれたりと、ペットがストレスなく安全に引越せるよう対応しています。なかには飼い主が一緒に付き添える場合もありますので、サービス内容を比較して検討してください。
ただし、他の方法と比べると費用が高額になります。特に移動距離に応じて費用が変わることが多く、見積もりでの確認が欠かせません。一方、引越し会社と比べてペットの種別で断られることは少ないでしょう。
【ペット別】自力でペットと引越す方法

自分でペットと引越す方法について、ペットの種類別に詳しく見ていきましょう。
犬と引越す方法
移動時はキャリーバッグに入れますが、公共交通機関ではサイズが指定されている場合があるので、あらかじめ確認しておいてください。
移動中にストレスが溜まらないよう、いつも遊んでいるオモチャなどを一緒にいれておくと安心です。また、念のためトイレシートも敷いておきましょう。ペットが乗り物酔いしやすい場合は、事前に動物病院で酔い止め薬をもらっておくのがおすすめです。移動が長時間におよぶ場合には、こまめに休憩を挟むようにしてください。その際にお散歩や運動をさせるため、リードを用意しておきます。
公共交通機関によっては、大型犬の持ち込みが禁止されていることもあります。また、飛行機では短頭種がNGということもあるため、経路と使用手段に応じて確認しておくことが大切です。
猫と引越す方法
猫との引越しは、基本的に犬と同様です。ただし、万が一脱走してしまった際の対策として、首輪に迷子札を付けておきましょう。
飛行機で移動する際、猫は貨物室での預かり荷物として扱われます。貨物室は客室と違って夏は暑く冬は寒くなるため、季節に応じて冷却マットや毛布等をケージに入れておくと安心です。
鳥や小動物と引越す方法
鳥や小動物は、ケージに入れて引越します。周囲からの刺激がストレスになる可能性があるため、外が見えないようケージをシーツ等で覆っておくとよいでしょう。できるだけ移動中の環境変化がないよう、いつも使用しているケージに入れてください。
ただし、引越しの際には揺れたり、何かにぶつかったりして衝撃が及ぶことがあります。その際、ドアが開いてしまったり、ちょっとした隙間から逃げ出したりしないかは、あらかじめ十分に確認が必要です。もし懸念点があれば、新しいケージを使用しましょう。
なお、公共交通機関では、種類に制限を設けていることがあります。特に猛禽類(フクロウ 等)はNGということがありますので、事前に自分の飼っているペットの種類が問題ないか確認しておいてください。
爬虫類と引越す方法
爬虫類は移動中も温度管理等が必要なことから、できるだけ専門の業者に依頼することが望ましいでしょう。どうしても自分で運びたい場合は、布袋に入れたうえでケージを使用します。亀など水が必要なペットなら、水槽や水漏れしないケースに入れて運んでください。
ただし、公共交通機関ではヘビなど特定の種類を禁止していることがあります。また、飛行機では爬虫類を運べない場合もあるので、いずれも使用予定の会社にあらかじめ確認しましょう。
魚と引越す方法
魚は水温・水質等の管理が難しく、長時間の移動では糞や尿で環境が悪化し、魚の健康状態が悪くなってしまう可能性があります。また、水槽の大きさによってはかなりの重量となり、移動が非常に困難です。そのため、できるだけ専門の業者へ依頼するのがおすすめです。自分で運ぶなら引越し先が近く、また軽量の水槽程度にしましょう。
引越し時のペットのストレスを減らすには
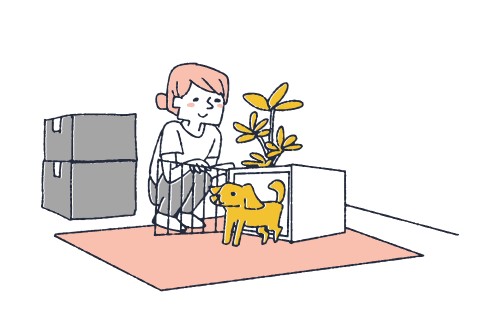
ペットは周囲からの影響やちょっとした変化などを敏感に察知し、ストレスを感じやすいものです。そのため、引越しの際にはできるだけストレスを軽減できるよう、以下のような対策をおこないましょう。
引越し作業中は安全な場所へ
引越し作業中は業者のスタッフが頻繁に出入りするほか、たくさんの声や音が室内に飛び交います。また、作業中にぶつかったり、物が当たったりする可能性もあるため、静かで安全な場所へ移動させておきましょう。
引越し前に使用していたものはそのまま使用する
移動に使用するケージは、引越し前に使用していたものをそのまま使いましょう。引越しに当たって買い替える人もいますが、少しの環境変化がペットにとってはストレスになります。ただし、劣化して移動中に逃げ出してしまうリスクがあるといった場合は別です。また、オモチャや毛布なども、できるだけ引越し前に使っていたものを選んでください。
スキンシップを増やす
引越し中でもペットを放置せず、定期的にお散歩に連れ出したり遊んだりと、スキンシップの時間を持ちましょう。最初は不安があっても、スキンシップを通じて移動に慣れ、ストレスを感じにくくなります。
引越し後におこなうペットの引越しに関する手続き

ペットと引越して住所が変わった場合は、種類に応じて手続きが必要となります。
犬の引越しに関する手続き
犬を飼っている場合は、役所の窓口等へ登録事項変更届を提出し、住所変更の手続きをおこなわなくてはいけません。書類を提出すると「狂犬病の予防注射を受けていること」を証明する標識である「鑑札(かんさつ)」がもらえるので、飼い犬に着けておいてください。なお、この手続きでは登録事項変更届の他に、以下の書類等も必要になります。
- 旧住所で受け取った鑑札
- 狂犬病予防注射済票
- 登録料、注射済票交付手数料
なお、自治体によってはこれ以外にも必要書類が設けられていることがあるので、窓口で確認するか、事前にホームページ等を確認しておくとよいでしょう。
この手続きは、引越しから30日以内におこなう必要があります。手続きしないと20万円以下の罰金に処される場合がありますので、余裕を持って早めに済ませると安心です。
特定動物の引越しに関する手続き
特定動物とは人に対して危害の及ぶ可能性のある動物で、具体的にはヘビやワニ、タカなどが該当します。これら特定動物と引越した際には、別途手続きが必要です。手続きの内容や手順については、引越し先の住所を管轄する都道府県、あるいは政令市の動物愛護管理行政担当部局に問い合わせてください。手続きをおこなわなかった場合は、6カ月以下の懲役、または100万円いかの罰金が課せられます。
ペットの引越しに関する注意点

ペットの引越しには、ペットのストレス軽減や引越し後の手続きだけでなく、さまざまな注意点があります。スムーズに引越してペットと新居での暮らしをスタートさせるため、以下の点についても頭に入れておきましょう。
ペットの体調に注意する
引越しでの移動中、そして新居へ住み始めてから慣れるまでは、ペットの体調に注意しましょう。移動中はこまめに水分補給をさせてあげないと脱水になる可能性があるほか、乗り物酔いしてしまうことも考えられます。乗り物酔いについては、乗車前にペット用の酔い止め薬を飲ませて挙げましょう。
また、引越し直後は家に慣れていないため、疲れやストレスから体調を崩すケースが少なくありません。食欲が低下したり、下痢などの症状が見られたりする場合には、すぐ動物病院を受診してください。
新居でペットが落ち着ける場所をすぐに準備する
ペットは環境が変わることによりストレスを感じやすいため、新居ではすぐに落ち着いて過ごせる場所を作ってあげましょう。引越し前に使用していたケージ等があれば配置し、同様に愛用してきたオモチャや毛布なども置きます。できるだけ飼い主がそばにいてあげられる場所にすると、ペットも安心できるはずです。
ただし、あまり無理に遊ぼうとするなど、構い過ぎるとかえって疲れてしまうかもしれません。少しずつ慣れていきますので、様子を見ながら過ごしてください。
新居近くの動物病院を確認する
ペットは、いつ体調を崩してしまうか分かりません。また、予防接種など定期的な受診が必要なケースもありますので、新居近くの動物病院を早めに確認しましょう。利用者からの評判はもちろんですが、移動距離も大切です。緊急時を考えれば、できるだけ近くだと安心できます。車移動になる場合は、駐車場の有無と数も見ておきましょう。
また、動物病院によっては診察対象のペットを限定していることがあります。特にエキゾチックアニマルなどは診察不可という動物病院が多いため、自分の飼っているペットをちゃんと見てもらえるのかも確認が必要です。
引越したあと旧居の掃除をする
引越した後は、旧居の掃除も忘れずにおこないましょう。ペットを飼っていると、どうしても壁や柱に引っかき傷がついたり、フローリングに爪跡が残ったり、壁や床に染みがつくといったことがあります。また、飼っている本人は気付きにくいですが、ペットを飼っていると部屋全体に臭いが染みついてしまうものです。
賃貸物件の場合、退去時には原状回復が必要になります。ペットによる傷や臭いについては、基本的に飼い主が負担することとなるでしょう。たとえペット可の物件だとしても同様です。少しでも負担を抑える意味合いからも、できるだけ引越し後はきれいに掃除してください。
海外への引越しは国ごとに必要な書類が異なる
ペットと海外へ引越す場合は、渡航先の国によって手続きが異なります。基本的に、出国時には動物検疫所で「輸出検疫」が求められるほか、犬であれば引越し先の国で狂犬病予防の注射が必要になるでしょう。
そのほか、輸入許可証の発行や日本における在住証明書の提出を求められるケースもあるので、あらかじめ確認しておくと安心です。こうした情報は、引越し先の国の大使館ホームページ等で確認できます。
まとめ
ペットと引越すための方法や注意点について、詳しく解説しました。ペットは引越し時、あるいは新居での環境変化により、ストレスを感じることがあります。十分に配慮し、できるだけストレスを軽減させてあげてください。近くであれば自分で連れて行くことも可能ですが、遠方の場合は、専門の業者に依頼した方がよいでしょう。
なお、ペットの種類等によっては、公共交通機関が利用できないこともあります。自分で連れて行く場合にはあらかじめ移動手段を調べ、ペットを連れて行けるか確認しておいてください。引越し後はペットが環境に慣れるよう落ち着けるスペースを確保するなど工夫し、新しいペットライフを快適かつ安心してスタートさせてください。
物件を探す
注文住宅を建てる






