水槽を引越し先へ運ぶ方法は?必要な準備と注意点を徹底解説

本記事では、水槽を引越し先へ運ぶ方法や具体的な準備の手順、知っておくべき注意点を解説します。デリケートな魚と水槽を安全に運ぶため、ぜひ参考にご覧ください。
記事の目次
水槽の引越しは自分でできる?

水槽の引越しは、自分でおこなうこともできます。しかし、水中生物はとても繊細な生き物です。少しの環境の変化で体調を崩したり、なかには温度や水質のごくわずかな変化で死んでしまったりすることもあります。
まず大切なのは、その生き物の特性をしっかり理解すること。本やネットの情報で不安が残るようであれば、ペットショップへ赴き相談するのもいいでしょう。特性をきちんと把握したうえで、引越しの準備を進めるのが肝要です。
1時間以上の運搬は専門会社に任せるのが安心
水中生物を安全に新居へ運びたいのなら、自分でおこなうのではなく、専門会社に依頼する方がいいでしょう。生体をパッキングして酸素を確保しなければなりませんし、運搬中は温度が変化しないように注意する必要だってあります。なにかと気忙しくなりがちな引越しの際、生体の安全を確保するのは心身ともに負担がかかりますし、運搬に必要な道具類を用意するのも大変でしょう。
その点、専門会社は水中生物に精通しています。運搬中、生き物にとって負担の少ない環境を保つための知識やノウハウが豊富です。なお運搬にかかるコストは移動距離が30km以内の場合、水量60リットル以内は2万〜2万6,000円、180リットル以内は4万5,000〜5万円が相場といわれています。ただし、移動距離や水槽の大きさだけでなく、その他の条件によっても変動しますので、事前に見積もりを依頼するのがおすすめです。
引越し会社に水槽の運搬を頼める?
残念ながら、すべての引越し会社が水中生物の運搬に対応しているわけではありません。なぜなら、国土交通省が定める「標準引越運送約款」に、動植物の運搬を拒絶していいとする規定があるためです。中には専門会社と提携しオプションで対応しているところもありますので、引越し会社を選ぶ際は水中生物の運搬に対応しているかを確認しましょう。しかし、対応しているのは稀なケースです。そのため、最終的には引越し会社ではなく、水槽の引越しに精通した専門会社へ依頼することが多いでしょう。
水槽を引越しする前に新居で確認すべきこと

水槽を引越しする際は、新居の状況についてもあらかじめ確認しなければなりません。具体的には、次の4点を押さえましょう。
水槽の設置可否
賃貸物件へ転居する際、第一に確認が必要なのは、水中生物を飼っていいかということです。生き物を飼うことが禁じられている場合、連れて行くことは断念しなければなりません。契約書で「ペット不可」の記載を探し、水生生物が含まれているかをチェックしましょう。
なお、物件によっては、ペットの飼育規約が書面化されていない場合もあります。その際は、管理会社や大家さんに確認してください。
水槽の設置に適したスペース
引越しの際は水槽をスムーズに設置できるよう、置き場所をあらかじめ想定しておくのがおすすめです。水槽の大きさを踏まえて場所を検討するのはもちろん、電源の位置確認も忘れないようにしましょう。
水槽を移動するための動線
新居に水槽を運び入れる動線も、事前に確認しておきましょう。と事前にイメージしておくとスムーズに運び入れられるだけでなく、道幅が意外と狭くて運搬に手間取ることがあるためです。物件のエントランスやエレベーター、廊下など、部屋までの動線をひと通り確認してシミュレーションしておきたいところです。
床の耐荷重
意外と盲点になりがちなのが、床の耐荷重です。特に、90cm以上の大型水槽の場合は注意してください。水槽の重さが床の耐荷重を超えていると、床の補強で対処できることもありますが、難しい場合は水槽を設置できません。そのため、管理会社や大家さんに確認しておきましょう。床が水平か自分でわからない場合は、耐荷重を確認する際にあわせて尋ねるとよいでしょう。
水槽を引越しする前におこなう準備

水槽を引越しする際は、1カ月前から準備が必要です。具体的にどういったことをするべきかを、以下で詳しく紹介します。
- STEP 1: 引越しの1カ月前水換えの頻度を上げ、新しい飼育水に慣れさせる
- STEP 2:引越しの1週間前常温の水温に慣れさせる
- STEP 3:引越しの前日引越しの前日は魚に餌を与えない
引越しの1カ月前
引越しの1カ月前になったら、週1回のペースで水を換えましょう。水中生物を水換えに慣れさせることで、引越し時のストレスを軽減させる目的です。
引越しの1週間前
引越しの1週間前になったら、ヒーターやクーラーの出力を下げ始めて徐々に常温へ近づけていきます。こうすることで、水温調整のしにくい引越し当日も、生き物がそこまでびっくりせずに済むはずです。
引越しの前日
前日はエサをあげずに絶食させましょう。なぜなら、引越しの間は水質をコントロールできず、糞をするほど水質が悪化してしまうためです。できれば、2〜3日前からエサの量を少しずつに減らしてください。
水槽の引越しに必要なもの

水槽と水中生物を引越し先へ運ぶ際は、さまざまな道具が必要になります。少なくとも前日までにはひととおり揃えておきましょう。
ポリタンクは、飼育水を運搬するために使用します。
発泡スチロール容器は、魚を入れたパッキング袋を運ぶために必要です。発泡スチロール容器に入れることで、水温の変化を極力おさえることができます。なお、クーラーボックスでも代用可能です。
パッキング袋は魚を入れるために使います。魚の大きさに応じてサイズを選ぶだけでなく、移動中に破れることのないよう、魚の運搬を目的とした厚手のタイプを使ってください。
酸素スプレーやエアーポンプは、パッキング袋に入れる飼育水に酸素を注入するために必要になります。大型の魚、あるいは移動時間が長い場合には、酸素スプレーだけだと足りなくなることがあります。状況に適したエアーポンプを選びましょう。
水槽内のきれいな飼育水を汲むために、バケツが必要になります。バケツを介すことで、砂利などの混ざっていない透き通った水をスムーズに取り出せます。
水草を乾燥させずに運ぶために使うのが新聞紙、そしてビニール袋です。新聞紙はガーゼでも代用できます。
水槽を衝撃から守るために、梱包材が必要になります。できれば、機材類も破損しないよう梱包材で包みましょう。おすすめは、気泡の入ったエアクッションタイプです。万一用意を忘れてしまった場合は、新聞紙やタオルでも代用できます。しかし、ズレてガラスがむき出しになることのないよう、くれぐれも注意してください。
ここで紹介したものは、いずれもホームセンターなどで購入可能です。
水槽を運ぶ引越し当日の流れ

引越し当日は、どのような流れで支度をすればいいのでしょうか。具体的な手順を一つずつ説明します。
【STEP 1】水槽の飼育水をポリタンクに移す
まずは、飼育水の半分ほどをポリタンクに移しましょう。ポリタンクに入れた飼育水は、新居で水槽を設置した後で再度使用します。
【STEP 2】バケツにも7割くらいまで飼育水を移す
新居で使う安定した飼育水を確保したら、バケツにも飼育水を汲みましょう。透き通った水を汲めるよう、砂利などが舞わないように注意しながらおこなってください。
【STEP 3】流木や水草、砂利などのレイアウト資材を梱包する
流木や水草、砂利などのレイアウト資材を梱包します。流木と水草は、十分に濡らした新聞を巻き付けるようにして一つずつ包んでください。すべて包み終わったらビニール袋に入れましょう。砂利はそのままビニール袋にまとめて入れます。
【STEP 4】飼育水を入れたバケツに魚を移す
水槽の中の魚を1匹ずつ確保し、飼育水を入れたバケツに移します。
【STEP 5】魚を飼育水と一緒にパッキング袋に入れる
バケツの中の飼育水を汲んでパッキング袋へ入れ、続いて魚を優しく入れます。魚のストレスを最小限にとどめるためにも、1袋当たり1匹ずつ入れるのがおすすめです。
【STEP 6】パッキング袋に酸素スプレーを注入する
パッキング袋に飼育水と魚を入れたら、空気を抜き酸素スプレーを注入します。空気がしっかり抜けていないと酸素をうまく注ぐことができないため、入念に作業を進めてください。
【STEP 7】パッキング袋を発泡スチロールに入れる
パッキングが完了したら、発泡スチロール容器に袋を入れます。なお、パッキング袋を詰めた後も、発泡スチロールはそのまま室内で保管してください。すぐに車に積んでしまうと、外気温の影響を受けやすくなるためです。他の荷物をすべて積み終わった後、最後に搬入しましょう。
【STEP 8】ポンプやろ過装置などの周辺機器を梱包する
ポンプやろ過装置などの周辺機器を、さっと清掃してから梱包します。ろ過装置は、水槽内に残っている飼育水を使って洗ってください。そうすることで、バクテリアの減少をおさえられます。なお、ろ過装置は飼育水入りのパッキング袋に入れると乾燥を防げます。
【STEP 9】水槽を梱包し輸送する
最後に、水槽本体を梱包して車に積み込みます。
運搬中は、冷暖房を調整して水中生物に適した温度を保つことに加えて、車の揺れにも注意しましょう。少しの揺れでも、万一パッキング袋に穴が空きでもしたら、水がこぼれて生き物が酸欠状態になってしまいます。運搬に数時間かかる際は、途中でサービスエリアなどに立ち寄り、生き物の状態を確認すると安心でしょう。
新居での水槽の立ち上げ方
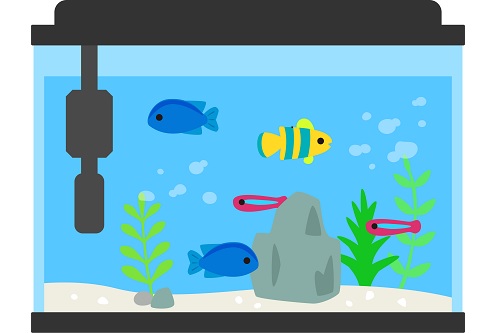
新居に着いたら、すぐに水槽に水を入れて魚たちを放ってあげたいと考えるかもしれません。しかし、その気持ちはぐっとこらえて、しかるべきステップを踏み環境を整備しましょう。
まずは水槽を配置し、ポンプやろ過装置などの周辺機器を設置します。続いて砂利、流木や水草などをレイアウトしたら、ポリタンクの飼育水を注ぎ、足りない分は中和剤を入れた水道水で補います。水量が十分になったら、しばらく空運転しましょう。
水温が安定し水が透明になったら、「水合わせ」をおこないます。水合わせとは、魚が入っているパッキング袋の水の水質と水温を、水槽内の水と合わせる作業のことです。
まず、パッキング袋を封が閉じた状態で、水槽の水に浮かべます。水温が同じくらいになったら、袋の中の水を少し捨てて、同量の水を水槽から汲んで袋に入れ、10分ほど待ちます。この作業を少なくとも3回、できれば5回ほど繰り返せば水合わせは完了です。水中生物を水槽に放ちましょう。
生き物を水槽に入れたら、病気になっていないかいつもと違うところがないかをじっくり観察してください。特に問題がないようであれば、エサを与えて大丈夫です。そこからは、いつもの状態に戻していきましょう。
水槽を引越す際の注意点

水槽を引越す際に気になりがちなことや、忘れてはいけない注意点について補足します。
発泡スチロール内の温度に注意する
発泡スチロールにパッキング袋を入れたら、温度の変化に注意しましょう。特に真夏の暑さは魚に大きなダメージを与えてしまいます。そのため、発泡スチロールの箱に保冷剤を入れるなどして、水温を調整するのがおすすめです。寒い冬は使い捨てカイロを活用し、魚にとっての適温をキープできるよう配慮しましょう。
飼えなくなった魚を川や池に逃がすのはNG
新居で魚を飼育できない、あるいは、既存の水槽のスペースを確保できないため小さな水槽に買い替える場合など、生き物を手放さなければならない状況になることがあるかもしれません。それでも、川や池など公共の場所へ逃がす行為は絶対にやめましょう。自然に帰しても環境に適応できず死んでしまうこともありますし、もともとの生態系を壊すリスクもあります。同様の理由で、水草も自然へ捨ててはいけません。飼えないときは、友人にあたって譲渡先を見つけたり、ペットショップや専門会社に相談したりして引き取ってもらいましょう。
水漏れには個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)がおすすめ
賃貸物件で水槽を設置する場合は、万一の水漏れに備えて保険に加入しましょう。水槽の水漏れが階下までおよぶと、多額の賠償金を請求されることがあります。ただし、賠償保険の種類によっては水槽の水漏れに対応していないものもあるため、契約内容をしっかり確認してください。
まとめ
熱帯魚や金魚などを新しい家に自分で運ぶ際は、まずは新居の条件を確認する必要があります。水槽を持ち込めることがわかり、自分で運搬することを決めたら、必要な道具を揃えましょう。魚を新しい環境に慣れさせるために、1カ月前から準備を始めてください。
特に引越しの当日は、生き物の状況を注視しながら作業を進める必要があります。自分で対処するのが難しい場合は、専門業者に依頼するのがおすすめです。新居でも大切な生き物とともに暮らせるよう、各注意事項をおさえながら、入念に引越しをおこないましょう。
物件を探す



