布団は干さなきゃダメ?正しい干し方と時間・頻度を徹底解説!

記事の目次
布団を干さないとどうなる?

人が眠っている間には、毎晩コップ1杯ほどの汗をかいているといわれており、基本的にその水分は布団に吸収されています。布団は、毎日の睡眠ごとに汗を吸っていることになるため、きちんと乾燥させないと湿気がどんどんこもる結果に。そしてそのまま干さずに放置していると、常に湿気が溜まった状態になり、布団が劣化する原因になってしまいます。また湿気がこもったままの布団は、雑菌などの温床になってしまう可能性もあり、結果的に不衛生な環境で眠ることになってしまう点にも注意が必要です。
布団を干すことで得られる効果

ここまでに出てきたように、定期的に干さないと布団は長持ちしにくくなり、衛生的にもよくありません。ではきちんと布団を干すことで、実際にどのような状態になるのか、以下から詳しい効果を見ていきましょう。
布団がふかふかになる
布団に湿気がこもると、中身の素材に水分が含まれることになり、クタクタのへたった状態になってしまいます。そこで布団を干して乾燥させることで、溜まった湿気が外に放出され、ふんわり感を復活させることが可能。ふかふかの心地よい布団にできるメリットがあります。さらに水分が飛んだ分は重さもなくなるので、布団が軽くなって寝返りもしやすく、体への負担がかかりにくくなる効果も。布団を干すことで、睡眠の質がよくなりやすい一面もあります。
イヤなにおいを防ぐ
基本的に、布団は毎日人肌に触れるもので、汗や皮脂が付着しやすい一面があります。そこで湿気による水分が残っていると、気になるにおいを発生させる原因になってしまうケースも。しっかりと乾燥させて湿気を逃すことで、イヤなにおいを発しづらくさせる効果が見込めます。また繊維の種類によっては紫外線が引き起こす化学反応から、布団を天日干しにすると、人がリラックスできる香りの元となるアルデヒドやケトンを放つともいわれています。これがいわゆる“お日様のにおい”とされるもので、布団を干すことで香りがよくなるケースもあります。
ダニ・カビを抑制する
ダニやカビは、ジメジメとした場所を好んで繁殖するものです。湿気がこもった布団は、まさにダニやカビにとっての絶好の生息場所で、放っておくと知らない間にどんどん増殖してしまう可能性も。そこで布団をこまめに干して、なるべく乾燥させた状態に維持しておくと、ダニやカビの発生を抑えることにつながります。なおダニやカビは、場合によってはアレルギーなどの健康被害を引き起こす恐れも。しっかりと布団を乾燥させて、ダニやカビを繁殖させないように対策するのは、日々の健康を守る意味でも効果的です。
布団の正しい干し方【時間・頻度】

ではここからは、より快適で衛生的な状態に保つことができる、正しい布団の干し方を解説していきます。
季節によっておすすめの干す時間帯が変わる
季節によって日射しの強さや湿度は異なるので、きちんと湿気を取り除くためにも、まずは時間帯を意識して干すことが大切です。時間帯によっては、湿気がうまく逃せないこともあるので要注意。また干しっぱなしにしてしまうと、せっかく湿気を飛ばしたにも関わらず、外気からの水分を再び吸ってしまいます。しっかりと乾燥させるには、各季節それぞれで、次のような時間帯で干すようにしましょう。
- 春…10~14時頃
- 夏…9~11時頃
- 秋…10~14時頃
- 冬…11~14時頃
春・秋・冬では、太陽が高くなる日中に干すと、周りの空気も乾燥していて湿気を飛ばしやすくなります。ちなみに空気は、暖かくなるほど水分を取り込みやすく、冷たいほど含みにくい性質があります。そのため基本的には、気温が高くなりやすい時間帯に干すのが原則。ただし夏場に限っては、強い日射しで布団を傷めてしまいやすいので、午前中の早い時間帯に干せるのがベストです。なおどの季節も夕方以降は、気温が下がって湿っぽくなるため注意が必要。せっかく乾いた湿気が戻らないように、取り込む時間帯も意識しておきましょう。
布団の素材によって干す時間・頻度が変わる
先ほども出てきたように、布団はただ干しっぱなしにすればいいわけではありません。布団はあまり日光に当てすぎても、紫外線や熱によるダメージを受けて劣化してしまいます。直射日光を浴びすぎてしまうと、日焼けして変色してしまったり、繊維が傷んでゴワゴワしてしまうケースも。また素材によって、乾きやすさや日光に対する強さは異なるので、各性質に合わせた干し方をするのも重要です。布団の素材として代表的なのは、以下のような種類で、それぞれ次の時間数と頻度で干すことをおすすめします。
- 木綿(コットン)…【干す時間】2~4時間 /【頻度】週に2~3回
- ポリエステル …【干す時間】1.5~3時間 /【頻度】週に1回
- 羊 毛 …【干す時間】1~2時間 /【頻度】月に2回
- 羽 毛 …【干す時間】30分~1時間 /【頻度】月に1回
干す時間は、表と裏の片面ずつに必要な長さです。なお時間数には幅がありますが、季節に合わせて長さを調整するのがベスト。気温が低くなるにつれて、長めに干すのが基本です。ここからは、各素材の干し方のポイントを見ていきましょう。
木綿(コットン)
木綿(コットン)は、水分を吸いやすく湿気がこもりやすい材質で、乾きにくい素材です。できれば週2~3回ほどのペースで、こまめに干すようにしましょう。夏なら片面2時間、冬なら片面4時間は天日干しにしておくと、しっかりと湿気を取り除けます。
ポリエステル
ポリエステルは、さほど湿気も吸わずに乾きやすい材質のため、週に1回ほどのペースでOKです。干す時間は、夏なら片面1.5時間、冬なら片面3時間が目安。日陰で干しても問題ありません。
羊毛
羊毛は、湿気がこもりにくく乾きやすい素材で、なおかつ直射日光で劣化しやすい一面があります。干す頻度は月2回(2週間に1回)ほどで、時間もさほど長くなくてOK。夏なら片面1時間、冬なら片面2時間を目安に、できれば陰干しするのがおすすめです。
羽毛
羽毛は、水分を吸収しやすい一方で、乾きやすい材質なのが特徴。さらに羊毛と同じく、直射日光には弱い素材でもあります。そのため干す頻度は月1回、夏なら片面30分、冬なら片面1時間ほどの短めで、羊毛と同様に陰干しするのがおすすめです。
| 素材 | 干し時間 | 頻度 | 干し方 | 乾き やすさ |
|---|---|---|---|---|
| 木綿 (コットン) |
2~4時間 | 週に 2~3回 |
天日干し | × |
| ポリエステル | 1.5~3時間 | 週に1回 | 天日干し ・陰干し いずれも可 |
〇 |
| 羊毛 | 1~2時間 | 月に2回 | 陰干し | 〇 |
| 羽毛 | 30分~1時間 | 月に1回 | 陰干し | 〇 |
素材に合わせた干し時間と頻度を把握しましょう
ここまでに見てきたお手入れを続けることで、布団が長持ちするだけでなく、快眠にもつながる効果が見込めます。心地よい睡眠時間を作るためにも、ぜひ参考にしてみてください。
また屋外に出すのが難しい場合には、少し場所は取ってしまいますが、室内干しでも問題ありません。例えば物干しスタンドなどを使って、扇風機・サーキュレーター・エアコン(除湿運転)で風を当てておけば、きちんと湿気を逃せます。ソファなどに広げてかけて、風に当てて乾かしておくのもよいでしょう。もしくは、より万全のダニ対策をしたいのであれば、布団乾燥機を使うのもおすすめ。高温でダニを死滅できるうえに、ふかふかの仕上がりになるのも特徴です。ベランダに布団を干せなかったり、天気が悪かったりする際には、室内干しや布団乾燥機も活用してみましょう。
布団を干す際のポイント

では、より衛生的に布団を干すコツとして、知っておきたいポイントもご紹介していきます。
シーツ類は付けたまま干す
シーツ類は付けたままのほうが、屋外に飛んでいるゴミや花粉などが直接付着するのを防ぐことが可能です。またシーツ類でカバーをすることで、布団への直射日光も遮ることができ、紫外線による劣化予防にもなります。ちなみに布団を干す際の専用カバーとして、布団干し袋といった便利アイテムも市販されています。特に日光を吸収しやすい黒タイプにしておくと、内部の温度上昇にともなうダニ退治効果にも期待できて一石二鳥です。
途中で裏返し両面干す
前述の正しい干し方でも少し出てきているように、布団は片面ずつ裏返しながら干すと、より湿気を逃しやすくなります。両面ともに、日光や風に当てることで、しっかりと内部まで湿気を取り除くことが可能。特に肌に触れる面側は、反対側よりも少し長めに干すのがおすすめです。なお冬の敷布団は、床に接する面でも、結露による湿気がたまりやすくなります。肌に触れる面と反対側の両方ともに、しっかりと干すようにしましょう。
布団を強く叩きすぎない

布団を強く叩いてしまうと、布団の素材が傷んでしまい、機能性や手触りが悪くなる原因にもなりかねません。せっかくのふかふか感や、温まりやすさなどを損ねてしまう可能性があるので、布団を干す際には叩きすぎないように要注意。また強く叩いた時に、元々付着していたダニの死骸が舞って、自分で吸ってしまうケースもあります。ゴミなどの汚れを取りたい時には、叩くのではなく、手などで軽く払うようにしましょう。
干したあとに布団を冷ます
布団を干すと、日光や屋外の気温で内部に熱がこもった状態になります。熱が残ったままで、収納スペースなどに片付けてしまうと、周りとの温度差で結露が出てしまう可能性も。
もしすぐに使わないのであれば、布団を取り込んだら、まずは放熱させてしっかりと冷ましてから押し入れやクローゼットなどに入れるようにしましょう。
干したあとはクリーナーをかける
シーツ類やカバーなどを付けて干した場合でも、布団本体には、ダニの死骸などのハウスダストが残っていることも多くあります。しっかりと汚れを取るためにも、布団を干して取り込んだら、クリーナーをかけておくのがベスト。収納スペースにしまう際にも、より清潔な状態で片付けられるメリットがあります。専用クリーナーか、もしくは布団用ヘッドを取り付けた掃除機を使うと、細かい汚れまできちんと落とすことができます。
花粉の季節は布団を干さないほうがいい?
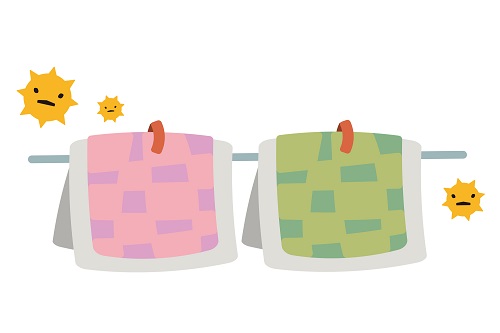
花粉・黄砂・PM2.5などが飛んでいる時期に、布団を屋外で干してしまうと、その汚れが部屋まで入り込んでしまう恐れも。取り込む前に布団を払ったとしても、完全に取り除くのは難しいので、どうしても室内まで侵入してきてしまいます。アレルギー症状の悪化などにつながる危険も考えられるため、布団を干したい時には、室内にするか布団乾燥機を使うようにしましょう。室内干しや布団乾燥機なら、例えば雨が増える梅雨にも布団が干せて便利です。
まとめ
では最後に、ここまでに解説してきた布団の干し方について、簡単におさらいしていきましょう。
布団を干さないとどうなる?
布団を干さずにいると、毎日の睡眠時の汗を吸ったまま湿気がこもり、布団の傷みや雑菌繁殖などの原因につながります。布団ならではのふっくらした手触りなども損なわれてしまうので、なるべく定期的に干すようにしましょう。
布団を干すと得られる効果は?
布団を干すと湿気が取り除けるため、ふかふかした立体感が出やすくなったり、イヤなにおいを軽減したりできる効果があります。またこまめに乾燥させることで、ダニやカビの繁殖を防ぐことも可能です。
布団の正しい干し方は?
基本的には気温が高くなる日中に干して、夕方になる前の昼過ぎには取り込みます。なお布団の素材ごとに、干しておく長さや頻度には違いがあり、天日干しか陰干しか異なります。材質に合わせたお手入れをするようにしましょう。
布団を干したあとは、やはりすっきり眠れる気がしますし、なんだか気分もよくなりますよね。実際に布団を干すことは、質の高い睡眠や健康を守る効果もあり、毎日イキイキと過ごしやすくなるメリットがあります。睡眠は日々に欠かせないものだからこそ、布団を干して快適に眠れる環境を整えることは、よりよい住まいづくりにもつながるもの。ぜひ本記事を参考に、心地よい睡眠ができるお手入れをしていきましょう。
物件を探す





