公租公課とは?不動産売買での扱いと注意点をわかりやすく解説
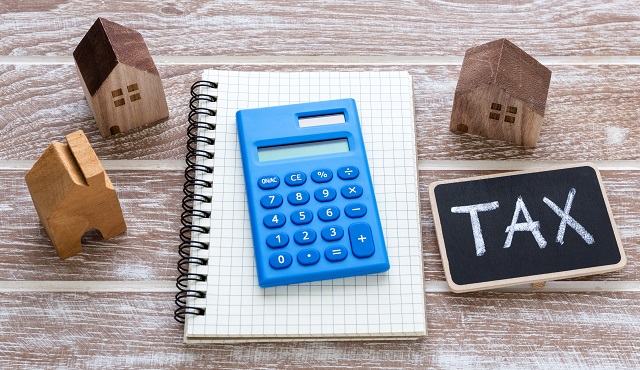
しかし、今後不動産の売買をおこなう際に「公租公課」の意味を十分に理解せず取り扱うと、思わぬ出費が発生したり支出を抑える対策ができなかったりと、後悔してしまう可能性があります。
そこで本記事では、公租公課の言葉の意味や不動産売買との関係性、分担方法、取り扱う際の大事なポイントなどについて解説します。公租公課という言葉の意味について十分に理解できていない方、あるいは、不動産売買における公租公課について把握したい方は、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
公租公課(こうそこうか)とは

公租公課とは、国や地方公共団体に納める公的金銭負担の総称です。一般的に「公租」は所得税や住民税、法人税、固定資産税などの税金を指し、「公課」は健康保険料や社会保険料、国・地方公共団体が発行する各種証明書の発行費用など、公的な負担金を指します。延滞税や過怠税、交通反則金などの罰金も「公課」に含まれます。
このように、公租と公課を合わせた勘定科目が公租公課です。税法上、必要経費として認められるものと認められないものがある点に注意しましょう。不動産売買においては、主に固定資産税や都市計画税を指して使われます。
公租公課と租税公課は同じ意味
公租公課は租税公課と呼ばれることもありますが、いずれも同じ意味です。聞きなじみのない言葉ですが、「公租=租税」と覚えておくとよいでしょう。
公租公課が不動産売買に関係するのはどんな時?
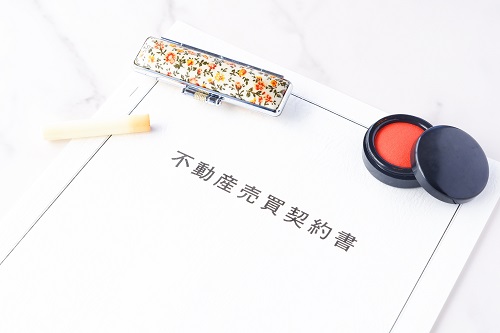
先述のとおり、不動産売買に関係する公租公課は、「固定資産税」と「都市計画税」の2種類です。固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点での不動産の所有者が納税義務を負います。そのため、不動産の売買取引がおこなわれた年は、売主と買主で固定資産税・都市計画税の分担や清算がおこなわれるのが一般的です。以下では、不動産売買に関係する固定資産税と都市計画税について解説していきます。
固定資産税
固定資産税は、土地や家屋、償却資産などの固定資産の所有者に対して課される税です。毎年1月1日時点での固定資産の価格をもとに税額が算定され、固定資産が所在する市町村や都が課税します。納税義務があるのは、毎年1月1日時点で固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。毎年4~6月頃に納税通知書が届き、一括納付または年4回に分けて納付します。
固定資産税は固定資産評価基準により評価額を算出し、評価額をもとに課税標準額が決定します。評価額をもとに決まった課税標準額に税率(原則1.4%)をかけた額が税額です。土地と家屋の評価額は3年毎に評価替えをおこない、それ以外の年度は原則据え置きとなります。また、税額は新築住宅で一定の要件を満たしている場合などに、減額措置を受けられる可能性があります。一般的な計算式は以下を参考にしてださい。
【固定資産税の計算方法】
課税標準※1×1.4%(標準税率)
都市計画税
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業をおこなう市町村が、都市計画区域内にある土地や家屋に対してその事業に要する費用に充てるため、目的税として課す税のことです。都市計画税は、地域ごとの都市計画事業等に応じて市町村が自主的判断して課税します。
都市計画税の対象となる資産は、原則市街化区域内に所在する土地と家屋で、償却資産は課税の対象ではありません。市街化区域内に土地や家屋を所有する方が市町村や都に対し、固定資産税とあわせて納税します。都市計画税がかからない地域もありますが、2023年(令和5年)4月1日時点での都市計画税の課税対象となる自治体は、日本全体で見ると約3分の1となります。
都市計画税は、固定資産税の課税標準額に対して税率0.3%をかけた額が税額です。税率は課税する市町村の条例で決められますが、0.3%を超える税率には設定できません。なお、固定資産税と同様に、税額は特例措置が適用される場合があります。計算式は次のとおりです。
【都市計画税の計算方法】
課税標準※1×0.3%(制限税率)
固定資産税に関する詳細は、以下の記事を参考にしてください。
売主と買主の公租公課の分担は?

上述のとおり、不動産の売買取引をおこなう際は、売主と買主で固定資産税や都市計画税の納税を分担・清算するのが一般的です。固定資産税や都市計画税は税制上、1月1日時点で土地や家屋を所有する方に、4月1日からの年度分の納税義務が発生します。年度の途中で所有者が変わったとしても、納税負担者は変わりません。ただし、不動産売買の実務では、起算日をもとに売主・買主で日割り計算して分担するのが一般的です。ここからは、起算日によって納税負担がどのように変わるのかを解説していきます。
一般的に起算日によって変わる
年度の途中で不動産売買がおこなわれた場合、起算日によって負担額が変わります。税額の清算は、365日の日割り計算です。起算日から引き渡し日までの日数分が売主、引き渡し日以降が買主となり、買主が売主に税額分を支払います。
起算日については、法律で決まっているわけではありません。主に、関東では1月1日、関西では4月1日になるケースが多い傾向にあります。起算日ごとの売主と買主の負担割合について以下で紹介するので、計算する時の参考にしてください。
起算日が1月1日の場合の負担割合
まずは、関東で一般的な起算日が1月1日の場合の売主と買主の負担割合について解説します。1月1日時点で不動産所有者に課される固定資産税・都市計画税が15万円、引き渡し日を9月1日と仮定した計算例は以下のとおりです。
売主負担:243日分(1月1日~8月31日)
15万円÷365日×243日=9万9,863円
買主負担:122日分(9月1日~12月31日)
15万円÷365日×122日=5万137円
売主負担額が9万9,863円、買主負担額が5万137円と、起算日が早いのに対して引き渡し日が年度の後半となっています。そのため、売主の負担割合がやや多くなっている点が特徴です。12月31日以降は、所有者が変わらない限り買主の全額負担となります。
起算日が4月1日の場合の負担割合
一方、関西で多い4月1日起算日の場合の負担割合について紹介します。条件は上記と同様、固定資産税・都市計画税が15万円、引き渡し日が9月1日です。
売主負担:153日分(4月1日~8月31日)
15万円÷365日×153日=6万2,877円
買主負担:212日分(9月1日~3月31日)
15万円÷365日×212日=8万7,123円
上と比較して起算日が遅い分、同じ引き渡し日でも買主の負担額のほうがやや多くなります。買主は、できるだけ固定資産税・都市計画税の納税額を少なくしたいと考え、1年の後半に引き渡し日を設定するケースがあるかもしれません。しかし、このように起算日によっては買主の負担割合が多くなる可能性があるので、契約時には公租公課の起算日を必ず確認するようにしましょう。
不動産売買の公租公課の注意

不動産売買に関係する公租公課は売主・買主で分担することになるため、取り扱いには十分な注意が必要です。ここからは、不動産売買の公租公課を取り扱う際に知っておくべき、以下3つのポイントについて解説します。
- ・起算日や負担割合を確認する
- ・不動産売買契約書をよく読んでおく
- ・確定申告で必要経費にできる場合がある
後になってトラブルに発展することのないよう、事前に理解を深めておきましょう。
起算日や負担割合を確認する
公租公課の取り扱いを誤らないためには、起算日や負担割合を必ず確認することが大切です。先述のとおり、実際の公租公課の負担額は起算日によって変更します。起算日の設定は、法律で決められているわけではありません。そのため、自分が想定している起算日とは異なり、負担額が思っていたより多くなってしまうケースもあるでしょう。
売買金額以外にかかる諸費用がどれくらいになるのかをあらかじめ把握し、計画的に準備を進めていても前章で解説したように、同じ税額、同じ引き渡し日でも起算日が変わるだけで負担額が大きく変わるので、忘れず確認するようにしましょう。
不動産売買契約書をよく読んでおく
公租公課に限らず、不動産売買契約書はよく読んで契約を結ぶようにしてください。不動産売買契約書には、対象物件の概要や契約金額、契約日・引き渡し日、売買代金の支払方法など、売買取引に関する重要な情報が記載されています。
不動産売買契約書は、契約日当日に不動産会社の担当者から説明を受けながら読み合わせをおこないます。ただし、専門用語の多い契約書の内容を一度で理解するのは困難でしょう。内容をしっかり理解し、同意したうえで契約を結ぶためにも、契約日より前に担当者から契約書のひな型を受け取り、読み込んでおくことをおすすめします。わからないことや不安な点は、積極的に質問して解消しておきましょう。契約書の理解を深めることで、トラブル回避にもつながります。公租公課についても記載されていますので、ほかの重要事項とあわせて確認しましょう。
確定申告で必要経費にできる場合がある
公租公課は、確定申告の際に必要経費にできる場合があります。自社ビルや駐車場として使用している土地など、事業に必要な財産として経費計上することが可能です。経費計上できる公租公課の例は、以下のとおりです。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
- 事業税・事業所税
- 利子税
- 事業用の自動車税・自動車取得税 など
確定申告書類の収支内訳書の経費欄には、「租税公課」の項目があります。上記の中で、事業用として所有している分の税額を記入しましょう。なかには、固定資産税や自動車税など、一部のみ事業用として使用しているケースもあります。その場合は事業用と生活用で按分し、事業用の部分のみ経費計上することが可能です。反対に、以下のような税金は経費として認められないため注意が必要です。
- 住民税
- 所得税
- 相続税
- 贈与税
- 加算税・延滞税など
公租公課に関するよくある質問
最後に、公租公課における重要なポイントを「よくある質問」にまとめました。簡潔におさらいできるので、重要ポイントを把握したい場合は以下を参考にしてください。
公租公課とは?
公租公課(こうそこうか)とは、国や地方公共団体に納める税金等の総称です。「公租」は所得税や住民税などの国税・地方税を指し、「公課」は公的機関が発行する書類等の各種手数料、公的団体の会費・交付金、所得税、延滞税などの公租以外の税金や負担金を指します。公租と公課を合わせた勘定科目が「公租公課」で、税法上では必要経費として認められるケースがあります。
公租公課と租税公課の違いは?
公租公課と租税公課は同じ意味を持ち、違いはありません。「公租=租税」と覚えておきましょう。
不動産売買で出てくる公租公課の意味は?
不動産売買における公租公課は「固定資産税」と「都市計画税」の2つを指します。固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点での不動産の所有者に課される税で、年度の途中で所有者が変わったとしても、納税負担者は変わりません。ただし、不動産売買の実務では、起算日をもとに売主・買主で日割り計算して分担するのが一般的です。
まとめ
ここでは、公租公課の言葉の意味や注意点などについて解説しました。「公租公課」という言葉は、日常生活においてなかなか耳にしない言葉です。聞きなじみのない言葉であることからもわかるように、意味を把握できていない方も多いでしょう。特に不動産売買に関係する公租公課は、自身だけでなく他の人とのトラブルに発展する恐れがあるため、取り扱いには十分注意が必要です。公租公課に限らず、不動産売買契約には重要事項が非常に多く含まれています。内容をしっかり理解して売買取引をおこなえるよう、疑問点をなくして明瞭な契約をおこなうようにしましょう。
物件を探す





