2025年度(令和7年度)税制改正を解説!住まいに関わるポイントは?

本記事では、2025(令和7)年度税制改正大綱をもとに、予定されている改正内容をわかりやすく解説します。
記事の目次
税制改正大綱とは?
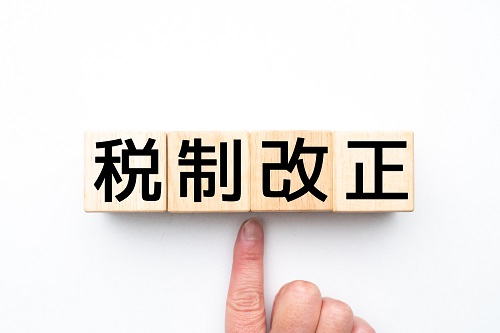
「税制改正大綱」とは、翌年度以降の税制改正の具体的な方針や内容を取りまとめた文書のことです。各省庁や各種団体から税制改正の要望を集め、税制調査会で審議をおこない、閣議決定を経たあと、財務省ホームページで公開されます。
いつから適用?税制改正までのスケジュール
ではここで、税制改正までの一般的なスケジュールをご紹介します。
-
8月末まで
財務省と総務省に、各省庁や各種団体などからの税制改正の要望が提出されます。 -
9月~11月
与党の税制調査会が提出された要望に対し審議を重ねます。 -
12月中旬
最終的な改正法案を税制改正大綱として閣議へ提出、閣議決定したあと、メディアなどで公開されます。 -
1月~3月
閣議決定した改正法案を通常国会に提出し、まずは財務金融委員会(衆議院)で審議し、衆議院本会議で可決後、参議院に送られます。参議院では財政金融委員会(参議院)で審議をおこない、参議院本会議に提出されます。 -
3月末
参議院本会議で可決、承認され、税制改正法案は成立します。 -
4月1日
税制改正法が施行されます。
2025年(令和7年度)税制改正大綱の目的は?
2025(令和7)年度税制改正大綱は、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化などに対応することを目的に、さまざまな改正法案が取り上げられています。
そのなかで、盛り込まれた事項の一部が以下のとおりです。
- 物価上昇局面の税負担の調整及び就業調整への対応
- 確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引き上げ
- 子育て支援に関する政策税制
- 固定資産税の課税標準の特例措置の延長等
- 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長 など
昨今、物価の高騰で私たちの生活は大きな打撃を受けています。国民の経済的状況を踏まえて、控除の見直しや子育て世帯への支援、資産形成に向けた確定拠出年金等の見直しなどが盛り込まれた税制改正大綱となっています。
「令和7年度税制改正大綱」の気になる7項目

ここでは、「令和7年度税制改正大綱」のなかから、私たちの生活に関連するものを7つご紹介します。
基礎控除・給与所得控除の見直し(103万円の壁)
本年度は、すべての人が該当する「基礎控除」と、働いて給与をもらっている人が該当する「給与所得控除」が見直されることになりました。
背景
これまでは、物価高騰で家計の負担が増えているが、控除額は変わらないので、実質的な税負担が増える状況でした。
施行時期
2025(令和7)年分以後の所得税に適用されます。
改正内容(概要)
-
基礎控除
合計所得金額が2,350万円以下の場合、48万円だった控除額が58万円に引き上げられます。 -
給与所得控除
これまで55万円だった最低保障額が65万円に引き上げられます。
特定親族特別控除(仮称)の創設
人手不足が続く中、働き控えを解消し、扶養者の税負担を軽減するため、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。
背景
アルバイトを雇用する側は人手不足のため、できるだけ長く働いてもらいたいと考えています。そんななか、特に大学生アルバイトの場合、年収の壁(103万円)を超えることで親の税負担が増えるため、働きたいのに働き控えをする大学生が多く見受けられています。
施行時期
2025(令和7)年分以後の所得税に適用されます。
改正内容(概要)
19歳以上23歳未満の特定扶養親族(大学生の子どもなど。配偶者や青色事業専従者は除く)の場合、要件を満たせば扶養者は63万円の扶養控除を受けられますが、特定扶養親族は年収103万円以下でなければ控除を受けられませんでした。
今回の改正で、特定親族特別控除により特定扶養親族が年収150万円以下(給与所得85万円以下)であれば、満額の扶養控除を受けられるようになります。また、特定扶養親族が年収188万円以下(給与所得123万円以下)であれば、段階的に控除額は減りますが、扶養者は所得から控除が受けられるようになります。
子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
生命保険加入者は、年間で支払った保険料に応じて一定額の所得控除を受けられる制度が「生命保険料控除」です。今回の改正で、子育て中の場合、生命保険料控除で受けられる控除額が一部引き上げられます。
背景
子育て中の世帯は、世帯主に万が一のことが起きた時、残された家族の生活費を補うため生命保険(死亡保険)に加入するケースが多く見受けられます。そこで、国は子育て支援の一環として、2026(令和8)年分の生命保険料控除を拡充することになりました。
施行時期
2026(令和8)年分の所得税に適用されます。
改正内容(概要)
23歳未満の扶養親族がいる場合、新制度(2012年以後に締結した保険契約が対象)の一般生命保険料控除の適用限度額は現行では4万円でしたが、2026年は6万円に引き上げられます。
また、旧制度(2011年以前に締結した保険契約が対象)と新制度の両方が適用される生命保険の保険料を支払った場合も、2026年は一般生命保険料控除の提要限度額が4万円から6万円に引き上げられます。
ただし、生命保険料控除の合計適用限度額は、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除をあわせて12万円となっていますが、2026年も現行どおり12万円のままです。
企業年金・個人年金制度の見直しにともなう税制上の所要の措置

今回の税制改正大綱には、企業型確定拠出年金や確定給付企業年金、iDeCo(個人型確定拠出年金)に関する見直しが盛り込まれています。
背景
企業年金やiDeCoは、老齢年金を補てんする私的年金制度として重要な役割を果たしています。そこで誰もが安定して資産形成を継続できるよう、確定拠出年金などの拠出限度額の引き上げが実施されることになりました。
施行時期
今回、拠出限度額は引き上げられますが、税制上の措置に改正はありません。
改正内容(概要)
主な見直しポイントは5つあります。
(1)企業型確定拠出年金のマッチング拠出で、企業型年金加入者の掛金は事業主掛金の額を超えることができないという制限は廃止となります。
(2)企業型確定拠出年金の拠出限度額は以下のように引き上げられます。
- 確定給付企業年金に加入していない人:月額5.5万円⇒月額6.2万円
- 確定給付企業年金に加入している人:月額6.2万円(現行5.5万円)から確定給付企業年金の掛金相当額を差し引いた額
(3)60歳以上70歳未満でiDeCoに加入できない人のうち、iDeCoの加入者・運用指図者、または私的年金の資金をiDeCoに移換でき、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない人は、新たにiDeCoの対象者となります。その際の拠出限度額は月額6.2万円です。
(4)iDeCoの拠出限度額が以下のように引き上げられます。
- 国民年金の第1号被保険者(自営業者、個人事業主など):月額6.8万円⇒月額7.5万円
- 国民年金の第2号被保険者(会社員、公務員など):
○企業年金に加入している人:月額6.2万円(現行2万円)から確定給付企業年金および企業型確定拠出年金の掛金相当額を差し引いた額
○企業年金に加入していない人:月額2.3万円⇒月額6.2万円
(5)国民年金基金の掛金上限額が月額6.8万円から月額7.5万円に引き上げられます。
退職所得控除の調整規定等の見直し
退職金を受け取った時、退職所得控除が適用されますが、現行では2カ所以上から退職金を受け取る場合、一定期間が空いていないと退職所得の計算で重複する勤続年数が調整される決まりがあります。今回の改正では調整期間が見直されます。
なお、退職金控除とは、勤続年数20年までは1年につき40万円、20年を超える部分は1年につき70万円が控除額となる制度です。退職金などの収入が控除額を上回った場合は、超過分の2分の1が課税対象となります。
背景
退職金を受け取る年の前年4年内にiDeCoや企業型確定拠出年金を一時金で受け取っていると、退職所得を計算する際、重複する勤続年数が差し引かれます。ただ、定年年齢の引き上げで、先にiDeCoや企業年金の一時金を受け取り、5年以上空けてから退職金を受け取り、iDeCo等も退職金も満額の退職所得控除を利用できるケースが増えています。そこで課税の公平性の観点から、調整期間が延長されることになりました。
施行時期
2026(令和8)年1月1日以後に支払われる確定拠出年金の一時金、退職金に適用されます。
改正内容(概要)
退職金を受け取る前年以前9年内(現行4年内)に確定拠出年金の一時金を受け取っている場合、退職所得控除の計算で勤続年数の重複する期間が排除されます。
各種控除証明書類の提出省略
確定申告の際、生命保険料や地震保険料などの控除を受ける時に提出しなければならなかった控除証明書が省略できるようになります。
背景
生命保険料控除や地震保険料控除などを受ける際、確定申告書に保険会社から控除証明書を添付する必要がありました。
施行時期
2026(令和8)年分以後の確定申告書を2027(令和9)年1月1日以後提出する時から適用されます。
改正内容(概要)
確定申告で小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除を受ける際に、以降の添付・提示に代えて、明細書を確定申告書に添付できるようになります。
- 小規模企業共済等掛金控除証明書
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
ただし、確定申告の期限から5年間のうちに税務署長から控除証明書を求められた時は、提出・提示しなければなりません。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の延長
父母や祖父母から結婚資金や子育て資金を贈与された場合、一定額までは贈与税が非課税になる制度が延長されます。
背景
経済的な不安があるため、結婚や出産を躊躇する人たちがいます。そこで、父母や祖父母が持つ資産を子や孫に贈与する際の税制優遇を継続することで、国は引き続き結婚や出産、子育てを支援していくことになりました。
施行時期
制度が2年間延長されます。期限は2027(令和9年)3月31日までです。
改正内容(概要)
父母や祖父母の直系尊属から結婚や子育て資金の贈与を受けた時、1,000万円までは贈与税が非課税になります。このうち結婚関係の資金として制度を利用できるのは300万円までです。
また、贈与を受ける子や孫は18歳以上50歳未満で、合計所得金額は1,000万円以下という要件があります。
「令和7年度税制改正大綱」で不動産に関する4項目

「令和7年度税制改正大綱」のなかで、不動産に関する事項を4つご紹介します。
住宅ローン等に係る所要の措置
2025年度は、子育て世帯(※1)と若者世帯(※2)が住宅ローンを組んで長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅を新築・取得し、2025年12月31日までに入居する場合、住宅ローン控除の借入限度額が通常よりも上乗せとなります。
(※1)子育て世帯とは、19歳未満の子どもがいる世帯のこと。
(※2)若者世帯とは、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯のこと。
□入居年が2025年の場合
| 住宅の種類 | 通常の 借入限度額 |
子育て世帯・若者世帯の 借入限度額 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・ 低炭素住宅 |
4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、新築で2025年12月31日以前に建築確認を受ける場合、住宅ローン控除を受ける際の床面積の要件が緩和されます。通常は床面積が50平方メートル以上のところ、合計所得金額が1,000万円以下であれば50平方メートル未満40平方メートル以上でも住宅ローン控除を利用できます。
相続登記等の登録免許税の免除に関する特例措置の延長
親や親族が持っていた不動産を相続した時、所有権移転登記(相続登記)をおこないます。その時、原則土地の価額に対し0.4%の登録免許税がかかります。
また、相続登記等の登録免許税は2つの免税措置があります。
●相続登記をしないまま死亡した場合の登録免許税の免税措置
相続(1次相続)をした人が相続登記をする前に死亡し、その子どもなどへの2次相続が発生した場合、その土地は1次相続の相続登記を済ませてから、2次相続の相続登記をおこなう必要があります。
この場合、1次相続の相続登記をおこなう際に発生する登録免許税は免税となります。また、この免税措置は2025年3月31日までとなっていました。しかし、2025(令和7)年度税制改正により2年延長となり、2027(令和9)年3月31日まで受けられます。
●不動産の価額が100万円以下の土地にかかる登録免許税の免税措置
土地を相続し、所有権移転登記、または表題部所有者の相続人が所有権保存登記をおこなう場合、相続した土地の価額が100万円以下の時は登録免許税が免税となります。
この免税措置も2025(令和7)年3月31日までとなっていましたが、2025(令和7)年度税制改正により2027(令和9)年3月31日まで2年延長となります。
固定資産税に係る特例措置の延長
長寿命化のために大規模修繕工事を実施したマンションは、各区分所有者に課せられる固定資産税が、市町村の条例で定める割合に応じて減額される措置が2027(令和9)年3月31日まで2年間延長となります。
子育て対応改修工事に係る住宅リフォーム税制の延長
子育て世帯・若者世帯(※1)が、一定の子育て対応リフォームをおこなった場合、250万円を限度に住宅改修工事費用の10%が所得税から減税される特別控除があります。これは2024(令和6)年12月31日までの措置でしたが、2025(令和7)年度税制改正により1年延長され、2025(令和7)年12月31日まで控除を受けられます。
| 一定の子育て対応改修工事の内容 |
|---|
| ①住宅内における子どもの事故を防止するための工事 |
| ②対面式キッチンへの交換工事 |
| ③開口部の防犯性を高める工事 |
| ④収納設備を増設する工事 |
| ⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事 |
| ⑥間取り変更工事(一定のものに限る) |
(※1)19歳未満の子どもがいる世帯または、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯のこと。
2025年は住宅の買い時?

長期に渡り低金利時代が続いた日本ですが、2024年に日銀が金利の引き上げをおこない、それにともなって住宅ローンの金利が上昇しました。2025年も金利の上昇が予想されるため、住宅ローンの金利も上がる可能性があります。特に変動金利は半年ごとに金利の見直しがおこなわれるため、今よりも金利が上昇するかもしれません。
とはいえ、本当に金利が上昇するのか、またどれくらい金利が上がるのかは予測できません。そんななか住宅購入を考えているのであれば、住宅ローン控除を利用するとよいでしょう。2025年は新築の場合、長期優良認定住宅など限られた住宅に限定されますが、中古住宅には住宅の限定はありません。
住宅ローンを組んで中古住宅を購入し、リフォーム工事をおこなうのもよいでしょう。住宅ローン控除がいつまで続くかは未定ですが、現時点では2025年に入居することで住宅ローン控除を受けられることになっています。住宅資金が準備できていれば、物件をチェックしてみてもよいでしょう。
住宅購入で利用できる制度は住宅ローン控除だけではありません。リフォーム工事による減税措置や自治体が実施する住宅関連の補助金や助成金もあります。何か使える制度はないか、最新情報をチェックしてみましょう。
また、住宅購入の際は資金計画が重要になります。頭金を準備し、住宅以外に必要な出費を確認したうえで、無理なくローンを返済できるよう資金計画を立てることをおすすめします。
2025年度(令和7年)の税制改正のまとめ

最後に2025(令和7)年度税制改正の目的や不動産に関する内容をまとめました。
税制改正大綱とは?
税制改正大綱とは、翌年度以降の税制改正の具体的な方針や内容を取りまとめた文書のことです。
「令和7年度税制改正大綱」の目的は?
「令和7年度税制改正大綱」は、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化などに対応することを目的に、税負担を軽減する控除の見直しや子育て世帯への支援、資産形成に向けて確定拠出年金の拠出限度額の引き上げなどが盛り込まれています。
「令和7年度税制改正大綱」で不動産に関する項目とは?
不動産に関するものから、対象者が比較的多い3つの項目をピックアップしました。
子育て世帯と若者世帯が住宅ローンを組んで認定住宅等を新築・取得し2025年中に入居すると、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされ通常よりも多くなります。
また、子育て世帯・若者世帯が住宅に対し、一定の子育て対応のリフォーム工事をおこなった場合、250万円を限度に工事費用の10%が所得税から控除されます。
さらに、住んでいるマンションで長寿命化に向けた大規模改修工事がおこなわれた場合、固定資産税が一定割合減額されます。
2025(令和7)年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除、大学生の子どもがいるご家庭に関連する特定親族特別控除の創設など、私たちの税負担が軽減される措置が実施される予定です。また、確定拠出年金の拠出限度額の見直しで、将来に向けた資産形成が効率的にできるようになります。
加えて、2025年は、子育て世帯や若者世帯に対し、住宅関連の減税措置が複数実施されます。家計の負担を減らすには、国や自治体がどのような制度や減税措置を実施するのかチェックすることが重要です。あらゆる面で情報収集しながら、利用できる制度を活用することをおすすめします。






