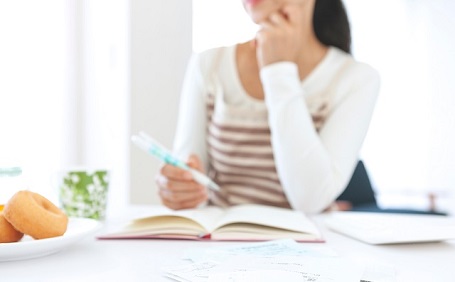妻の親からの住宅取得資金の贈与は非課税になる?条件と注意点を徹底解説

この記事では、妻の親からの住宅取得資金の贈与が非課税になる条件や注意点を解説します。
経済的な利点を最大限に活用しながら、夫婦の新しい生活を豊かにしましょう。
記事の目次
住宅ローンを組む際に贈与を受ける時の非課税制度とは

「住宅ローンを組む際に資金の援助を受けると贈与税がかかるかもしれない」ことは、耳にしたことがあるかもしれません。しかし、具体的な内容まで理解している方は多くないでしょう。そして、非課税になるのかも気になる点です。
住宅取得資金においての贈与に関する非課税制度は、特定の条件下で住宅ローンを組む際に受けた贈与が、税金の対象とならないようにするものです。法律や規制を理解しておくことで、よりよい選択をする助けとなります。
住宅資金贈与は最大1,000万円まで非課税になる
「住宅取得資金贈与の非課税特例」は、特定の条件を満たす場合に限り、贈与税が免除される制度です。
特例が適用されるのは、贈与される資金が、契約者本人が居住する住宅の購入資金として使われる場合です。
そして、特例を利用する際には、住宅の性能によって控除対象となる贈与額に違いが生じます。
具体的な例を挙げると、省エネなどの基準を満たさない住宅に適用されるのは500万円が上限となり、省エネなどの基準を満たすと、限度額が1,000万円となります。
夫の単独名義では妻の親からの贈与は対象外となるケースがある
住宅取得資金贈与の非課税特例は、特定の条件を満たす場合に贈与税を免除する制度として知られています。
特例を利用できるのは、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に限られます。
特例は、贈与を受けた人が単独で住宅を保有するケースだけではなく、複数人が共有名義で住宅を保有する場合にも適用される制度です。
直系尊属とは、自身の父母や祖父母を指します。したがって、妻の親から贈与を受ける場合は、基本的には非課税制度は適用されません。しかし、妻が住宅の名義人になっていれば、特例を利用することができます。
なお、例外的なケースとして、配偶者の父母や祖父母から贈与を受けた場合でも、養子縁組が成立している状態であれば、直系尊属として認識されます。
特例を受けるための要件
住宅取得等資金贈与の非課税特例を受けるためには、特定の要件を満たす必要があります。
まず、住宅に関する要件として、日本国内に位置していることや床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であることなどが挙げられます。
床面積によっては、年間合計所得が1,000万円以下であることも条件となっているため、注意しましょう。
また、受贈者自身にもいくつかの要件があります。
一つ目は、先述したように、贈与者の直系卑属であること、つまり子や孫であることが必要です。
さらに、贈与される年の1月1日時点で18歳以上であることが求められます。(ただし、令和4年3月31日以前の贈与に関しては、その時点で20歳以上である必要があります。)
住宅取得等資金の贈与の非課税特例にはさまざまな要件が設けられているため、制度を利用する際には、国税庁の「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を確認しましょう。
住宅取得資金の贈与に関する非課税制度を利用する際の3つの注意点

非課税制度を利用することで得られるメリットは大きいですが、利用するには一定の条件が必要です。
ここでは、非課税制度を利用する際に注意すべき3つのポイントを深く掘り下げて解説します。特に、妻の親からの贈与をスムーズに進めるためには要点を押さえておくことが重要です。
非課税制度を利用して住宅の購入をする際に、トラブルを避け、効率的な進行を実現できるでしょう。
不動産取得税や登録免許税は払う必要がある
相続税の非課税制度を利用する場合でも、住宅を取得する際には、「不動産取得税」や「登録免許税」などの税金が発生します。
まず、「不動産取得税」は、新築や購入で住宅用の不動産を取得すると、固定資産税評価額の3%が税金として課されます。
次に、「登録免許税」は、住宅購入時には土地と建物に対して異なる税率が適用されます。
具体的には、土地に関しては固定資産税評価額の1.5%、建物に関しては新築の場合は0.15%、購入の場合は0.3%が登録免許税として課されます。
相続争いに発展する可能性がある
妻の親からの贈与を受ける際には、将来的な遺産相続争いを避けるためにも、他の相続人候補、例えば兄弟姉妹とのバランスを考慮することが重要です。
特定の相続人が多くの財産を受け取ることで、他の相続人の取り分が減少する、あるいはなくなる可能性があります。
取り分を受けられなかった配偶者や子どもは、「遺留分」を主張することが可能です。
遺留分の主張は、相続財産だけではなく、特定の条件を満たす生前贈与にも適用されます。
具体的には、相続開始前1年以内におこなわれた贈与や、双方が遺留分侵害を承知のうえでおこなった贈与、さらには結婚や住宅購入のための特別受益にあたる贈与も、遺留分の対象となるため、注意が必要です。
遺留分を主張されると、同額分を金銭で支払う必要があります。
妻の親からの贈与を受けたことによって、のちに追加の出費が発生するリスクが生じるため、将来的な相続問題を避けるためにも、他の親族との関係を慎重に考慮しましょう。
相続時精算課税制度を利用する際には注意が必要
妻の親から住宅取得資金の贈与を受ける際に、「相続時精算課税制度」を利用したいと思う人もいらっしゃるのではないでしょうか?相続時精算課税制度とは、生前贈与を受けた場合、2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時に贈与財産の贈与時の価額と、死亡時の相続財産の価額を合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
住宅取得等資金贈与の非課税特例と相続時精算課税制度を併用する際には、いくつかの重要な注意点があります。
まず、相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなった場合、「暦年課税制度」を利用することができなくなるため、注意しましょう。暦年課税制度とは、その年の1月~12月までに受けた贈与に対して毎年110万円以内の金額については申告不要で無税で贈与できる制度です。
相続時精算課税制度を利用した場合は、年間110万円以下の贈与であっても、申告をおこなう必要があります。申告を怠ると、贈与税が課されるリスクがあり、累計での贈与額が非課税枠の2,500万円を超えると、超えた分に対して一律で20%の贈与税が課税対象です。
さらに、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続時に贈与時の価額で相続財産に持ち戻されますが、孫への贈与にも適用され、相続税が課されることになります。
相続時精算課税制度を利用する際には、これらの注意点を考慮しましょう。適切な税務対策をおこなうためにも、正しい知識を身に付けておくことが重要です。
非課税制度の限度額よりも贈与を受ける時の4つの方法

非課税制度の限度額を超える贈与を受ける際には、さまざまな方法があります。
特に、妻の親からの贈与を受ける場合は特殊な状況のため、しっかり知識をつけておくことが重要。
ここでは、限度額を超えた額を贈与してもらうための4つの方法を解説します。
超過分を納税する
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、特定の上限額までの贈与に対して特別控除が適用されることを理解しておくことが重要です。
贈与の上限額を定めるものではなく、あくまでも一定額までの贈与に対して税金の控除を受けることができる制度です。
例えば、特別控除の額が1,500万円である場合に、2,000万円の贈与を受ける状況では、1,500万円までは非課税となりますが、残りの500万円に対しては贈与税が課されます。
しかし、500万円に対して贈与税を支払うことで、合法的に贈与を受けることが可能となります。
限度額までだとしても、特例を利用しない場合に比べれば、大幅な節税効果を得ることができるので、特例制度の金額以上の贈与を受ける場合でも、特例制度が使えないと諦めるのではなく、限度額までは特別控除を受けるようにしましょう。
毎年110万円までの贈与を活用する
贈与税の課税を避ける方法として、「暦年課税制度」を利用する方法もあります。前述したとおり、毎年の基礎控除額である110万円以下の範囲で贈与を受ける方法です。
この方法は、贈与税の支払いを回避しながら、一定の資産移動をおこなうことができるのがメリットです。
この贈与をおこなう際には、契約書を作成し、毎年新たに110万円の贈与に関する契約を結ぶことが推奨されます。
契約書を結ぶことで、年度ごとに基礎控除額内での贈与として認められ、贈与税の課税を避けることが可能となります。
ただし、大きな金額の贈与を受けたい場合、長い年月がかかることがデメリット。住宅ローンを組む際に住宅購入資金の頭金として贈与金を使用したい場合には早めに贈与を開始しておかなければなりません。
相続時精算課税制度を活用する
住宅取得等資金贈与の非課税特例と相続時精算課税制度を併用することで、最大で3,500万円までの資金援助を贈与税ゼロで受け取ることが可能となります。
具体的には、非課税の特例を利用して1,000万円と、相続時精算課税制度を利用して2,500万円の贈与を受けることができます。
しかし、いくつか注意が必要です。
先述したとおり、相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与と呼ばれる、年間110万円までの基礎控除を利用した贈与が利用できなくなります。また、相続時精算課税制度を利用した贈与は、将来的に相続税の課税対象となる可能性があります。
贈与をおこなう際には、将来の相続税負担を考慮したうえで、適切な計画を立てることが重要です。
贈与をしてもらう親と共有名義の住宅にする
住宅取得等資金贈与の非課税特例の枠内で贈与を受けることは一般的な方法ですが、非課税枠を超える資金に関しては、親が出資した分を持分として設定し、住宅を共有名義とする方法があります。
しかし、これは贈与の段階での課税を避ける方法として有用ですが、親が亡くなった際には相続手続きが必要となるので注意が必要です。
特に、兄弟姉妹がいる場合には、相続時にトラブルが生じる可能性があり、他の相続人から遺産分割を要求されるケースがあります。
住宅を共有名義として設定する割合は、事前に家族間で相談をおこなうことが重要です。
また、遺言書を作成しておくことで、将来的なトラブルを避けることができます。
遺言書には、持分の割合や共有名義に関する取り決めなど、具体的な内容を記載しておくことが推奨されます。
事前の準備と相談をしておくことで、スムーズな相続ができるようになるでしょう。
贈与税の確定申告をする際の必要書類
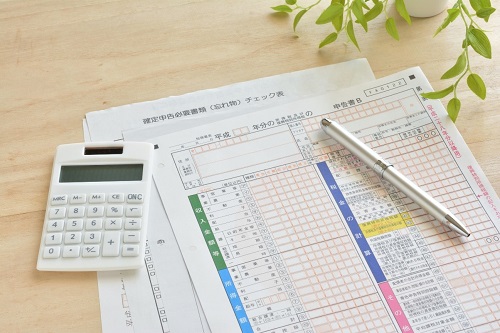
住宅取得資金贈与の非課税特例を利用して贈与税を免れる場合でも、確定申告は避けて通れません。
一連の手続きと必要書類の提出が求められます。
ここでは、手続きの概要と必要書類を解説します。
まず、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、管轄の税務署に必要書類を提出することが必要です。
申告をしなかった場合は、非課税特例を利用できなくなるため、注意してください。
提出する主な書類としては、戸籍謄本や源泉徴収票などの基本的な書類があります。
さらに、新築や増築、取得した建物の登記事項証明書や、請負契約書、売買契約書の写しも必要となります。これらの書類は、住宅の面積などの詳細をもとに、非課税特例の適用可否が判断されるため、重要です。
また、先述した書類は適切に保管しておくことで、将来的なトラブルを避けることができます。
さらに詳しい書類のリストは、国税庁のチェックシートを参照して、必要書類の準備と確定申告の手続きを適切におこないましょう。
この記事のまとめ
最後に、妻の親から住宅購入資金の贈与を受けることについてよくある質問をまとめてみました。
妻の親からの贈与は非課税になる?
住宅取得資金贈与の非課税特例は、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に限られるため、原則、非課税の対象ではありません。
しかし、妻が住宅の名義人になる場合や、養子縁組が成立している状態であれば、非課税の対象となることがあります。
非課税制度を利用する際の注意点は?
住宅取得資金贈与の非課税特例を利用する際の注意点には以下のようなものがあります。
- 小規模宅地等の特例と併用できない
- 不動産取得税や登録免許税は払う必要がある
- 相続争いに発展する可能性がある
- 相続時精算課税制度と併用する際には注意が必要
節税効果がある他の制度との併用には、特に注意しましょう。
非課税制度の限度額よりも贈与を受けたい場合は?
住宅取得資金贈与の非課税特例の限度額よりも贈与を受ける場合、納税額を少なく抑えるには、以下の方法があります。
- 超過分の贈与額に対する贈与税を納税する
- 毎年110万円までの非課税贈与を活用する
- 相続時精算課税制度を活用する
- 贈与をしてもらう親と共有名義の住宅にする
住宅取得資金贈与の非課税特例以外にも納税額を抑える方法があるため、正しい知識を身に付けておきましょう。
住宅取得資金の贈与に関する非課税制度は、多くの利点がありますが、利用する際にはいくつかの条件と注意点があります。
最大1,000万円までの住宅資金贈与が非課税となる特例がありますが、残念ながら妻の親からの贈与は特例の対象外となります。特例を受けるためには、特定の要件を満たす必要があるため、注意しましょう。
非課税制度を適切に利用しながら法律を遵守することで、節税しつつ夢のマイホーム購入が実現できるでしょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ