住宅ローンのペアローンと連帯債務の違いは?それぞれのメリットとデメリットを紹介!
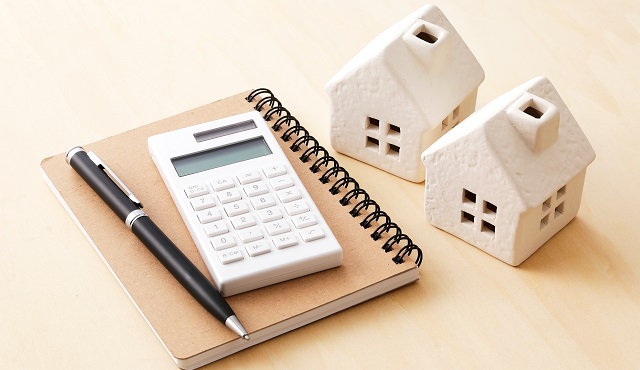
それぞれの違いを把握することで、ライフプランに合わせた正しい判断ができます。
本記事ではペアローンと連帯債務の違い、それぞれのメリットやデメリットを解説します。
記事の目次
住宅ローンにおけるペアローンと連帯債務の違い

夫婦で住宅ローンを組むことを検討している人のなかには、ペアローンと連帯債務の違いが明確になっていない人もいるのではないでしょうか。
そこで、まずはペアローンと連帯債務の違いを解説します。
ペアローンとは
ペアローンは、夫婦や親子関係にある二人が一つの物件に対してそれぞれで住宅ローンを契約することで、共同で借入ができるローンのことです。
ペアローンを組む際には、それぞれの住宅ローンを双方が連帯保証人となる必要があります。
連帯保証人は、住宅ローンの契約者が返済できなくなった際に返済の義務を負うため、自分の返済に加えて相手方の返済額も負担します。
しかし、一人では希望の融資額まで到達できなくても、ペアローンを組むことで融資金額を増加させて、希望の物件を購入できる可能性が高くなるでしょう。
たとえば、夫だけでは3,000万円までしか借りられなくても、夫が3,000万円、妻が2,000万円を借りることで5,000万円の物件を購入できます。
上記では、住宅ローンの金額の割合がそれぞれの住宅の持分となります。
つまり、それぞれの持分は夫が60%、妻が40%です。
住宅ローンの負担割合と不動産に登記されている割合が異なると、贈与税の課税対象となる可能性が高いため、注意が必要です。
連帯債務とは
連帯債務は、二人の収入を合算して住宅ローンを借りることで、それぞれが主債務者と連帯債務者となるローンのことです。
連帯債務で住宅ローンを組む際には、主債務者と連帯債務者が同等の債務を負うことになるため、主債務者が返済できなくなると連帯債務者に返済義務が発生します。
しかし、主債務者の年収だけでは希望の融資額まで到達できなくても、収入のある配偶者が連帯債務者となることで、希望の物件を購入できる可能性が高くなるでしょう。
配偶者以外にも連帯債務者になれる可能性がありますが、金融機関によって基準が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
一例として、フラット35では以下の人が連帯債務者になれると定めています。
- 申込みご本人の親、子、配偶者等
- 申込時の年齢が70歳未満の方
- 申込みご本人と同居される方
引用:フラット35
連帯債務で住宅ローンを組めば、連帯債務者も主債務者と同様の住宅ローン控除を受けることができる点は、メリットといえるでしょう。
ペアローンと連帯債務の違い
ペアローンと連帯債務は、両方とも共働き世帯が選びやすい住宅ローンですが、それぞれの違いは以下のとおりです。
| ペアローン | 連帯債務 | |
|---|---|---|
| 住宅ローンの契約 | 夫と妻それぞれ | 夫か妻の一方 |
| 収入合算 | できる | できる |
| 住宅ローン控除 | 借入額に応じて それぞれに適用可能 |
物件の持分に応じて それぞれに適用可能 |
| 団体信用生命保険の 加入 |
名義人二人が加入 | 名義人一人が加入 |
| 手数料などの 諸費用負担 |
二人分 | 一人分 |
| 所有権 | 借入額を考慮して 夫婦で登記 |
返済額を考慮して 夫婦で登記 |
両方とも収入を合算して希望の融資額に到達させるのが目的となりますが、契約名義人が一人なのか二人なのかが大きな違いとして挙げられます。
住宅ローンを組む際のペアローンのメリットとデメリット

住宅ローンを組む際のペアローンに関して、メリットとデメリットを見ていきましょう。
ペアローンのメリット
住宅ローンをペアローンで組むメリットは以下の4つです。
- 多額の融資を受けることができる
- 住宅ローンの自由度が高い
- 二人が住宅ローン控除を受けることができる
- 二人が団体信用生命保険に加入できる
それでは、順番に見ていきましょう。
多額の融資を受けることができる
住宅ローンをペアローンで組む1つ目のメリットは、一人で組むよりも多額の融資を受けることができることです。
一人分の年収では希望する融資額を受けられない可能性がありますが、夫婦それぞれが住宅ローンを組むことで多額の融資を受けることができます。
また、二人で住宅ローンの負担を分担することで、それぞれの返済額の負担を軽減できるでしょう。
一人ではなく二人で融資を受けるペアローンならではのメリットといえます。
住宅ローンの自由度が高い
住宅ローンをペアローンで組む2つ目のメリットは、住宅ローンの自由度が高いことです。
住宅ローンを組む際には、金利のタイプや返済期間、借入額を決めることになりますが、ペアローンでは夫婦それぞれの条件で契約ができます。
たとえば、夫婦で合計5,000万円の借入をすると、以下のような契約ができます。
| 夫 (3,000万円の借入) |
妻 (2,000万円の借入) |
|
|---|---|---|
| 金利のタイプ | 全期間固定金利型 | 変動金利型 |
| 返済期間 | 35年間 | 20年間 |
| 金利 | 1.54% | 0.475% |
固定金利型と変動金利型を使い分けることで、教育費がかかる時期の負担を減らしたり、退職時期に合わせて返済期間を設定したりできます。
各家庭のライフプランに合わせて住宅ローンを組めるのは、それぞれが契約をするペアローンのメリットといえるでしょう。
二人が住宅ローン控除を受けることができる
住宅ローンをペアローンで組む3つ目のメリットは、二人が住宅ローン控除を受けることができることです。
住宅ローン控除が適用されるのは住宅ローンの契約者となるため、ペアローンを組むことでそれぞれが制度を利用できます。
住宅ローンの控除額には限度額が設定されているため、ローンの残高が高くても一人で契約すると制度をフル活用できない可能性があります。
しかし、ペアローンを組めば夫婦それぞれが住宅ローンを組むことになるため、二人とも住宅ローン控除の対象です。
ペアローンを組むことで、融資額を上げるだけではなく節税効果も図れます。
二人が団体信用生命保険に加入できる
住宅ローンをペアローンで組む4つ目のメリットは、二人が団体信用生命保険に加入できることです。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が死亡や高度障害など万が一のことがあった際に、住宅ローンを0にする制度のことです。
団体信用生命保険に加入しておくことで、残された家族が返済をすることなく家に住み続けることができます。
民間の金融機関で住宅ローンを組む際には、基本的には団体信用生命保険への加入が必須条件となっていますが、住宅ローンの契約者にのみ適用されます。
ペアローンを組んでそれぞれが住宅ローンの契約者となることで、死亡や高度障害など万が一の時にも備えることができます。
ペアローンのデメリット
住宅ローンをペアローンで組むデメリットは以下の3つです。
- 事務手数料が通常の2倍かかる
- 一方の収入が減ると返済が困難になる
- 二人とも健康でいる必要あり
事務手数料が通常の2倍かかる
住宅ローンをペアローンで組む1つ目のデメリットは、事務手数料が通常の2倍かかることです。
先述したとおり、ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンの契約を締結するため、契約書や融資の手続きが2回分必要となります。
そのため、契約者を一人にする通常の住宅ローンよりも事務手数料が2倍かかる点には注意が必要です。
一方の収入が減ると返済が困難になる
住宅ローンをペアローンで組む2つ目のデメリットは、一方の収入が減ると返済が困難になることです。
夫婦の一方が転職や退職などで収入が減少しても、住宅ローンの返済は継続する必要があります。
特に女性は妊娠や出産、子育ての期間などは収入が減少することが多いでしょう。
そのため、ライフプランをしっかりと計画して融資額や返済期間を決めることが大切です。
二人とも健康でいる必要あり
住宅ローンをペアローンで組む3つ目のデメリットは、二人とも健康でなければいけないことです。
ペアローンを組むことで二人が団体信用生命保険に加入できる点をメリットとして先述しましたが、あくまで生命保険であるため、健康状態が良好であることが求められます。
また、夫が死亡や高度障害になると、夫が契約している住宅ローンは完済されますが、妻が契約している住宅ローンの返済は継続したままです。
つまり、妻の収入が低いと支払いが困難になるため、それぞれの収入とのバランスを考慮してペアローンを組む必要があるでしょう。
住宅ローンを組む際の連帯債務のメリットとデメリット

住宅ローンを組む際の連帯債務に関して、メリットとデメリットを見ていきましょう。
連帯債務のメリット
住宅ローンを連帯債務で組むメリットは以下の3つです。
- 融資額を増やすことができる
- 要件を満たすことで二人が住宅ローン控除を受けることができる
- ペアローンよりも諸費用を抑えることができる
それでは、順番に見ていきましょう。
融資額を増やすことができる
住宅ローンを連帯債務で組む1つ目のメリットは、融資額を増やすことができることです。
連帯債務を利用することで、主債務者と連帯債務者の収入を合算できるため、一人で融資を受けるよりも多額の融資を受けることができます。
たとえば、年収が500万円の夫だけで融資の審査を申し込むのではなく、年収300万円の妻と合算して800万円の収入があるものとして申し込みができます。
より多い収入で申し込みができるため、理想の物件を購入できる可能性が高くなるでしょう。
二人が住宅ローン控除を受けることができる
住宅ローンを連帯債務で組む2つ目のメリットは、二人が住宅ローン控除を受けることができることです。
連帯債務は総借入額を二人が債務者となることで、住宅ローンの負担を軽減する仕組みです。
二人で住宅ローンを組むことになるため、住宅ローン控除も二人が受けることができます。
ペアローンよりも諸費用を抑えることができる
住宅ローンを連帯債務で組む3つ目のメリットは、ペアローンよりも諸費用を抑えることができることです。
ペアローンは夫婦それぞれが契約をするため、契約や融資の手続きが二人分となりますが、連帯債務はあくまで一方のみが契約者となります。
ペアローンが5,000万円の借入を夫が3,000万円、妻が2,000万円の住宅ローンを組むのに対し、連帯債務は5,000万円の借入を夫婦で住宅ローンを組むことになります。
契約や融資の手続きが一人分で済むため、ペアローンよりも諸費用を抑えることができるでしょう。
連帯債務のデメリット
住宅ローンを連帯債務で組むデメリットは以下の2つです。
- 持分と融資負担割合が異なると複雑になる
- 連帯債務者が団体信用生命保険に加入できない可能性がある
それでは、順番に見ていきましょう。
持分と融資負担割合が異なると住宅ローン控除額が減る
住宅ローンを連帯債務で組む1つ目のデメリットは、持分と融資負担割合が異なると住宅ローン控除額が減ることです。
連帯債務を利用すると、基本的には物件の持分によって住宅ローン控除を受けることができます。
ただし、物件の持分と住宅ローンの負担割合が異なると控除額が異なるため、融資負担割合には注意が必要です。
具体例として、持分が2分の1ずつの物件を、夫が3,000万円、妻が2,000万円の総額5,000万円の借入をするケースを例に挙げます。
持分が2分の1ずつのため、それぞれが本来負担すべき借入額は2,500万円となりますが、夫が利用できる住宅ローン控除の対象額は2,500万円で、妻は2,000万円です。
つまり、物件の持分と住宅ローンの負担割合が異なると住宅ローン控除額が減り、場合によっては贈与税の課税対象となるため注意が必要です。
連帯債務者が団体信用生命保険に加入できない可能性がある
住宅ローンを連帯債務で組む2つ目のデメリットは、連帯債務者が団体信用生命保険に加入できない可能性があることです。
連帯債務を利用すると、主債務者しか団体信用生命保険に加入できないのが一般的です。
団体信用生命保険に加入できないため、万が一に備えて別途生命保険に加入する必要があるでしょう。
ただし、金融機関によっては二人が加入できるプランも用意されているため、事前の確認をおすすめします。
住宅ローンを組む際のペアローンか連帯債務を選ぶ時の3つのポイント

住宅ローンを組む際のペアローンか連帯債務を選ぶ時のポイントは以下の3つです。
- 住宅ローン控除
- 返済額
- 生命保険の加入の有無
それでは、順番に見ていきましょう。
住宅ローン控除
住宅ローンを組む際のペアローンか連帯債務を選ぶ時の1つ目のポイントは、住宅ローン控除です。
住宅ローン控除の限度額は、一般の新築住宅が21万円、認定長期優良住宅などは35万円です。
住宅ローン控除を最大限活用するには、夫婦それぞれの借入金額によって控除を受けることができるペアローンがおすすめです。
ただし、所得税から控除しきれない分は住民税から控除されることになるため、注意しておきましょう。
返済額
住宅ローンを組む際のペアローンか連帯債務を選ぶ時の2つ目のポイントは、返済額です。
金融機関がシミュレーションした返済額が、一人で支払える金額であれば連帯債務でもよいですが、一人で負担するのが困難であればペアローンにして負担を軽減するのがおすすめです。
各家庭のライフプランや、夫婦それぞれの収入を考慮して選択しましょう。
生命保険の加入の有無
住宅ローンを組む際のペアローンか連帯債務を選ぶ時の3つ目のポイントは、生命保険の加入の有無です。
先述したとおり、連帯債務は主債務者しか団体信用生命保険に加入できないケースがほとんどです。
そのため、住宅ローンを組む時点で生命保険に加入していない人は、ペアローンを選択するか、連帯債務で団体信用生命保険に加入できる金融機関を選択しましょう。

- ペアローンのメリットとデメリットは?連帯債務型・連帯保証型についても解説
- 住宅購入を検討する際、「自分はいくらまで住宅ローンを借りられるのだろう?」と多くの人が気になるのではないでしょうか
続きを読む

まとめ
夫婦で住宅ローンを組む際のペアローンと連帯債務には、それぞれメリットやデメリットがあるため、各家庭のライフプランに合わせて選択するのがおすすめです。
自分だけで判断が難しい場合には、不動産会社や金融機関に相談してみましょう。
物件を探す

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成を行うため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
ライフマネー研究所



