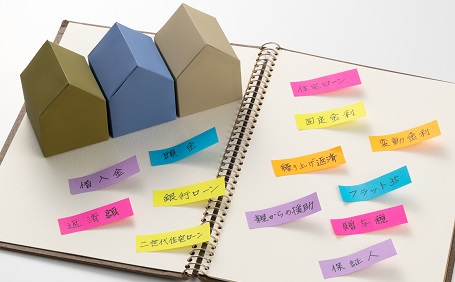住宅ローンの本審査に向けた準備は万端?必要書類をチェックしよう!

そこで、この記事では、住宅ローンの本審査の必要書類はどのようなものなのか、わかりやすく解説します。また、住宅ローンの本審査に向けて必要な情報もあわせてお伝えします。
記事の目次
住宅ローンの本審査とは?

住宅ローンを契約するには、契約者のローン返済能力を確かめるための審査があります。審査は、事前審査と本審査の2段階でおこなわれます。
本審査では、以下のような内容を精査します。
- 事前審査の内容が正しいか
- 事前審査と本審査で内容に相違がないか
- 事前審査時の不動産を本当に購入予定かどうか
- 物件の担保評価調査
- 健康状態の確認
本審査の合否が出るまでは、2週間ほどで遅くても1カ月で結果が出ます。審査に通過したら速やかにローン実行の手続きに入るためにも、日程には余裕を持ち計画立てて対応していくことをおすすめします。
住宅ローン本審査と事前審査(仮審査)との違い

住宅ローン本審査と事前審査の2つの違い
住宅ローンの本審査と事前審査で異なる点は以下の2つです。
- 借入希望者の情報精査レベル
- 健康状態のチェック
特に、健康状態に関しては事前審査では問われませんので、金融機関の担当者は本審査時に初めて持病の存在を知ることになります。もし持病が団体生命信用保険の加入に影響する場合、本審査が否決される可能性があるため、注意が必要です。
本審査が否決された場合、再度団体生命信用保険の加入を必要としない金融機関を探す必要があります。したがって、あらかじめ持病の有無を金融機関の担当者に伝え、本審査時の健康状態のチェックを受けることが重要です。
事前審査に必要な書類は、借り手が給与所得者(会社員や公務員など)、個人事業者(フリーランスなど)か、または法人の代表者か、さらに他の借り入れがあるかどうかによって異なります。
住宅ローン事前審査の必要書類
住宅ローンの事前審査で必要になる主な書類は以下のとおりです。
- 事前審査用の住宅ローン申込書
- 物件の情報がわかる資料
- 収入確認用書類
- 本人確認資料
- 印鑑
購入物件の資料は、チラシや見積書、物件の間取り図などを用意しましょう。本人確認書類は、運転免許証やパスポートなどです。書類で表裏があるものをコピーする場合は、両面印刷が必要です。印鑑は、認印でも使用できます。また、他で借り入れがある場合には、償還予定表の写しか残高証明書も用意しましょう。
収入を確認する書類
収入を確認する書類は、職業によって異なります。会社員など給与所得者の場合は、職場でもらえる源泉徴収票を用意します。前年分のものがあればよいです。個人事業主の場合は、確定申告書と付表で直近3年分ほど準備しておきましょう。法人の場合は、源泉徴収票、確定申告書と付表をともに直近3年分にくわえ、決算報告書も3期分の勘定科目内訳明細書付きで用意しましょう。
なぜ住宅ローンの審査は2回おこなうのか
住宅ローンの審査は、前段階の事前審査と本審査の2つの段階でおこなわれます。事前審査では、ある程度の選定を事前におこないます。住宅ローンの本審査は売買契約後におこなわれるため、もし本審査に落ちてしまうと購入ができず、契約を解除しなければなりません。その結果、売り手と買い手の両方に大きな損害が生じます。
このリスクを回避するために、売買契約前におこなわれるのが住宅ローンの事前審査です。主に借り手の返済能力や信用情報の有無が確認されます。事前審査では、借り手の返済能力などが調査され、物件価格までの融資が可能なのか、またどの程度の融資が可能なのかが確認されます。
借り手にとっては、金融機関の事前審査を通過すれば、安心して希望の物件の購入手続きを進めることができるようになります。
住宅ローン審査の一般的な流れと期間の目安

住宅ローン審査は、まず金融機関を選ぶところから始まります。以下、住宅ローン審査の一般的な流れを解説します。
- step1金融機関を決める
- step2事前審査(仮審査)
- step3本審査
- step4金融機関と契約を締結
- step5融資の実行
step1.金融機関を決める
インターネット専業銀行では金利が安かったり手数料が不要だったりと、金融機関にはそれぞれ特徴があります。金融機関にはたくさん種類があるので、まずは不動産会社や住宅を購入したハウスメーカーに聞いて、おすすめの金融機関を紹介してもらいましょう。そのうえで、インターネットなどで調べ比較して絞り込みましょう。
また、住宅ローンを複数提案してくれるサービス「モゲチェック」を活用して金融機関を選ぶ方法もあります。Web上で借りたい金額や自分の属性などの情報を入力するだけで利用でき、金利や総返済額の比較にも便利なので、以下から一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
step2.事前審査(仮審査)
金融機関の候補が決まったら、事前審査を依頼しましょう。審査は、取引相手の不動産会社やハウスメーカーに依頼して案内してもらいましょう。なぜならば、不動産会社やハウスメーカーでは各金融機関と提携し、個人で直接交渉をするのとは違う特別な融資枠などを設けている場合があります。書類の案内や申し込みの手続きなどもサポートしてもらえるので、うまく活用しましょう。
事前審査では、主に返済能力の確認と、どれくらいの融資ができるのかを確認します。そのため、氏名や住所、物件の情報に加え、年収や勤務先の確認と、借入の有無などを確認していきます。事前審査の合否がでるまでの期間は3~4日、遅くても1週間程度です。インターネットで確認できる会社では当日に判定がでるところもあります。
step3.本審査
事前審査をクリアすると、物件の契約をします。売買契約が締結したあとに、いよいよ本審査となります。
本審査では、事前審査の項目をより詳細に確認するとともに、健康状態の確認などもおこなわれます。事前審査では必要書類はFAXでも受け付けてもらえますが、本審査では金融機関の担当者と直接会って面談をおこないます。そのため、用意した書類は持参し、面談日の設定は早めに調整するようにしましょう。本審査の合否がでるまでの期間は、2週間程度、遅くても1カ月です。
step4.銀行と契約を締結
本審査を通過したら、銀行と融資の契約をおこないます。契約で使用する書類はどれも大変重要な書類なので、十分に内容を確認し納得できたら署名・捺印に応じるようにしましょう。
融資の実行までは、早い銀行であれば当日に、また時間がかかる場合には2週間程度の期間がかかる場合もあります。物件の引き渡しに間に合うよう、スケジュールをよく確認して行動しましょう。
step5.融資の実行
本審査を通過し、銀行と契約を締結したらいよいよ融資の実行です。このタイミングではもう、融資に関する書類のやりとりはありません。融資は引き渡しと同時に実行され、一連の手続きが完了します。
住宅ローン本審査の必要書類とは

住宅ローンの本審査で必要になる書類は、以下のような書類です。
- 本人確認書類
- 所得証明書類
- 物件情報書類
- 返済予定明細書
- 印鑑と印鑑証明
- 勤務証明
本人確認書類
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)などは原本を用意しておきます。申込者本人のもので有効期限が切れていないものを用意します。
住民票などを取得する場合は、発行後何カ月以内のものといって指定があるためよく確認しておきましょう。住民票などは市役所およびコンビニでも取得できます。住民票には、家族全員の記載が必要です。ただし、本籍地やマイナンバーの記載は不要で、あると不備になるので注意しましょう。住民票は他の手続きでも使用するので、数枚用意しておきましょう。
所得証明書類
源泉徴収票や課税証明書もしくは住民税決定通知書などが必要になります。確定申告をしている人は、納税証明書なども必要になる場合があります。会社に勤めている場合は、源泉徴収票や住民税決定通知書は勤務先で受け取ることができます。また、課税証明書は市区町村役場で、納税証明書は税務署で受け取ることができます。
所得を証明する書類は数年分必要になる場合があるので、3年程度準備できるようにしておきましょう。
物件情報書類
購入物件の平面図や間取り図、売買契約書、重要事項説明書、全部事項証明書などが必要になります。また、物件によっては工事請負契約書、建築確認申請書、土地登記事項証明書、建物登記事項証明書、不動産登記簿謄本なども必要書類となります。書類の内容をよく確認のうえ、事前に準備しておきましょう。
返済予定明細書
他からの借り入れがある場合に必要です。金融機関から受け取っている、借り入れ状況や返済計画がわかる書類を用意しましょう。もし手元にない場合は、利用中の金融機関に問い合わせて発行を依頼しましょう。
印鑑と印鑑証明
印鑑は実印を用意しましょう。印鑑証明は市区町村役場や、証明書類発行センター、もしくはマイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。使用には1カ月以内、あるいは3カ月以内など使用期限があるので金融機関で確認しておきましょう。印鑑証明も他の手続きで使用するので複数枚用意しておきましょう。
勤務証明
直近で転職した場合などには、勤務先確認書類が必要になる場合があります。取得の際は勤務先に依頼し、勤務先の名称や所在地の記載があるものを使用しましょう。
その他、本審査用の住宅ローン申込書が必要です。持病がある方は直近の健康診断結果が必要になる場合があります。銀行によって特別に必要な書類もあるので、実際の手続きをおこなう際には、よく確認するようにしましょう。
住宅ローンの審査に落ちてしまう理由と対策

事前審査を通過しても、本審査を通過できるとは限りません。両方の審査にも合格して初めて、融資を受けることができます。では、住宅ローンの審査に落ちてしまうのはなぜでしょうか。この章では、住宅ローンの審査に落ちてしまう代表的な理由と、落ちてしまった時の対策を解説します。
ケース1 信用情報に問題がある
事前審査を依頼してから短期間で住宅ローンの審査に落ちたことがわかる場合には、信用情報に問題がある可能性があります。例えば、過去に債務不履行や延滞があった場合や、借金の返済能力や収入の安定性が不安定だったり、多重債務を抱えていたりする場合です。これらの要素は貸付機関がリスクを最小限に抑えるために考慮する要素となり、審査で問題として判断されることがあります。
このような場合にはまず、信用情報の正確性を確認しましょう。クレジットレポートを入手し、不正確な情報や誤解釈された情報がないか確認します。もし問題がある場合は、信用情報機関に修正を依頼できます。個人情報を調べることができる機関に依頼し、確認してみましょう。
滞納などが事実で、信用情報を改善しようと努めるなら長い時間が必要になります。ただし、最終的な滞納月から5年以上経っていれば、再審査をして通過できる場合もあります。本審査を依頼してすぐ、否決の判定が出た場合には、信用情報を確認してみましょう。
ケース2 書類に問題がある
住宅ローンの本審査で、書類に問題があると審査に落ちる場合があります。金融機関は正確で完全な情報を必要とするので、書類に問題があると否定的な結果にせざるをえません。
具体的な例を挙げると、重要な書類が欠けていたり、不正確な情報が記載されていたりする場合があります。例えば、収入証明書に必要な情報が抜けていたり、申請フォームの記入漏れがあったりすると、金融機関は必要な情報を確認できず、審査で問題が生じる可能性があります。
ただし、不備が見つかった場合は、速やかに対処すれば改善する可能性があります。金融機関からの指示や問い合わせに迅速に対応し、必要な修正や補完書類の提出をおこないます。また、金融機関とのコミュニケーションを円滑にするため、担当者との連絡先や通信手段を確保しておくことも重要です。
ケース3 事前審査の情報と相違している
住宅ローンの本審査で落ちる理由の一つは、事前審査と本審査の内容が相違していることです。例えば、事前審査では収入や雇用状況が十分と判断されたにも関わらず、本審査で提出した書類で否決されてしまった場合です。
通常、不動産売買契約にはローン特約が設定されます。ローン特約が設定されると、本審査が通らなくても買主の過失でなければ、買主の責任は問われません。しかし、事前審査との情報差異による審査不合格は、買主の責務になります。すると、ローン特約は適用されず、買主は売主に違約金を支払わなければなりません。さらに、不動産会社にも仲介手数料を支払う必要も生じるため注意が必要です。
まずは、事前審査と本審査の内容を一致させることが大前提です。正確な情報の提供と要求事項への適切な対応をおこなうことで、本審査で情報差異による否決を防ぐことができます。事前審査と本審査の一貫性を保つことは、契約解除や追加費用の発生などのリスクを回避するうえで重要です。
記事のおさらい
Q:住宅ローンの本審査とはどのようなことを審査しますか?
A:借り手の返済能力や信用情報の有無が詳細に確認されます。また、健康状態のチェックが入ります。
Q:なぜ住宅ローンの審査は、事前審査と本審査の2段階なのですか?
A:住宅ローンの本審査は売買契約後におこなわれるため、本審査に落ちて契約が解除になると、売り手と買い手の両方に大きな損害が生じます。損害を防ぐため、事前に審査がされています。
Q:住宅ローンの本審査の必要書類は何ですか?
A:おおまかには、本人確認書類をはじめ、収入を証明する書類や、購入物件情報を確認する書類です。詳細は本文、あるいは利用中の金融機関で確認しましょう。
まとめ
この記事では、住宅ローンの本審査の必要書類はどのようなものなのか、わかりやすく解説しました。また、住宅ローンの本審査に向けて必要な情報もあわせてお伝えしました。住宅ローンの審査にあたって、事前に書類を準備しておけば、スムーズに審査を通過できるはずです。ぜひ参考にしてみてください。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ