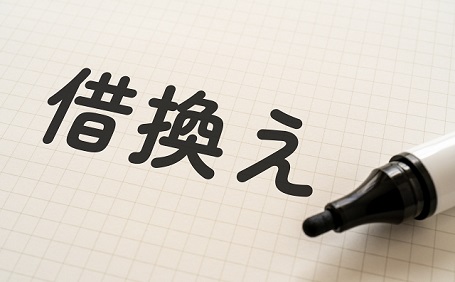住宅ローンがあると離婚できない?そう言われる理由や問題回避のチェックポイントとは

本記事では、住宅ローンを抱えたまま離婚する際に発生する問題点と、それに対する具体的な対処法を解説します。名義変更や財産分与の難しさ、返済のトラブルを避けるための方法など、知っておくべきポイントを整理します。本記事を読んで、住宅ローンが残った状態でも適切に手続きを進める方法を知り、離婚後のトラブルを未然に防ぎましょう。
記事の目次
住宅ローンが残った状態で離婚できないと言われるのはなぜか?

離婚を考えた時に、住宅ローンが残っていると離婚できないのではないかと不安に思う方も多いでしょう。結論からいうと、住宅ローンが残っていても離婚自体は可能です。ただし、家をどう扱うかによって、ローンの返済義務や財産分与、住居の問題など、さまざまな課題が発生するため、簡単にはいきません。そこで本章では、住宅ローンが残ったまま離婚することがなぜ困難かを解説します。
住宅ローンの名義変更が難しい
住宅ローンの名義変更は一般的に難しく、金融機関の承認を得ることは容易ではありません。単に「離婚したから」という理由では却下されてしまいます。住宅ローンは契約者の信用力をもとに審査・貸付がおこなわれるため、契約途中で名義を変更すると金融機関にとって大きなリスクだからです。
夫婦で購入した家の住宅ローンが「夫」名義になっており、離婚後に「妻」が家をもらい、住宅ローンの返済を引き継ぐ場合には、名義変更を希望するでしょう。しかし、金融機関は新たな名義人の収入や信用情報を厳しく審査し、基準を満たさない場合は名義変更を認めません。
「離婚したから」という理由だけで、名義変更が承認されるケースはほとんどないのが現状です。もし、金融機関の承諾なしに名義変更を進めた場合、契約違反とみなされ、残債の一括返済を求められるかもしれません。一度組んだローンの名義変更をせずに、離婚後も今の家に住みたい場合は、住宅ローンを完済するか、あらためてローンを借り替えるかのどちらかが一般的です。
共同名義で住宅ローンを組んでいた場合の名義変更は難しい
夫婦で共同名義の住宅ローンを組んでいる場合でも、離婚後に名義をどちらか一方に変更することは困難です。これは、金融機関が融資をおこなう際、夫婦双方の収入や信用情報をもとに審査し、貸付額を決定しているためです。2人合わせて審査されているため、どちらかが欠けることは想定されていません。多くの場合、共同名義の住宅ローンでは、夫婦の収入を合算して借入可能額を増やしています。そのため、名義変更をおこない片方のみを債務者にすると、金融機関は再審査をしなければなりません。単独の収入や信用力で審査基準を満たせない場合は、金融機関も名義変更を認めるわけにはいかないでしょう。
また、ペアローンや連帯債務型のローンでは、契約上どちらも債務の責任を負っているため、一方が抜ける状態は基本的に想定されていません。名義変更をおこなう場合には、新たなローン契約を結ぶか、借り換えをする必要があります。しかし、その際に金利や条件が変わり、これまでよりも返済負担が増す可能性もあります。 もし、ローンの名義変更ができない場合は、離婚後も元配偶者と共同で債務を負うため、関係が完全には解消されません。結婚する際に離婚を想定することは難しいですが、将来のリスクを避けるためには、住宅ローン契約の段階で慎重に契約内容を検討するべきでしょう。
新たな連帯保証人を立てることが難しい
住宅ローンに連帯保証人が設定されていると、変更をおこなうことは容易ではありません。連帯保証人は、主たる債務者が返済不能になった際に、残りの債務をすべて返済する責任を負う立場です。そのため、その役割を変更することは金融機関に大きなリスクとみなされます。
特に、連帯保証人を別の人物に変更する場合には、新たな保証人が元の保証人と同等以上の信用力を持っていなければなりません。審査の結果、収入や勤務状況などが基準を満たさなければ、金融機関は保証人の交代を認めないでしょう。また、契約内容次第では保証人の変更が契約上できない場合もあるため、注意が必要です。
さらに、連帯保証人の変更が可能でも、適切な保証人を見つけることは難しいかもしれません。親族や知人が代わりに保証人になるケースも考えられますが、保証の責任が重いため、引き受けたい人は少ないでしょう。その結果、保証人の変更が実質的に不可能となり、元配偶者との関係が継続してしまうケースもめずらしくありません。
家の所有権をめぐるトラブルが起きる
離婚後、共有していた家の所有権をどのように扱うかは大きな問題になりがちです。特に、住宅ローンの名義変更が難しい場合、不動産の名義も簡単には変更できない状況に陥るかもしれません。そうなると、離婚後も元配偶者との関係を続けざるをえなくなりますが、返済や所有権をめぐりトラブルになる可能性もあるでしょう。もし、登記上の所有者が一方の名義になっていると、もう一方が住み続けていても、所有者の判断で家を売却されてしまうかもしれません。
売却や相続が複雑になる
住宅ローンが残った状態で離婚すると、不動産の売却や相続に関する手続きが複雑になりやすいです。共同名義の不動産を売却するには、すべての名義人の同意が必要になるため、どちらか一方が反対すると売却できません。仮に持分の割合が9対1でも、名義を持つ側の承諾がなければ、売却の手続きはできなくなります。
また、不動産を賃貸に出したり、増改築をしたり、担保にして融資を受けたりする場合も、名義人全員の合意がなければできません。離婚後にどちらかが家を活用したいと考えても、もう一方の名義人が許可しなければ、実現は難しくなります。
離婚後の手続きが難しいために、共同名義のまま長期間放置した場合、今度は相続の場面で問題が生じるかもしれません。例えば、元配偶者が亡くなった場合、その持分は元配偶者の相続人に継承されますが、そうなると元配偶者の家族や親族が新たな権利者となり、不動産に関する決定権を持ちます。結果、売却や管理に関する話し合いが複雑化し、予想外の相続人と交渉しなければならない事態に陥るかもしれません。離婚時に住宅ローンが残っていると、将来的に家の扱いが難しくなるだけでなく、共有者の意向によって自由に売却や活用ができなくなるリスクも生じます。
離婚時に住宅ローンが残っている場合の対処法

離婚時に住宅ローンが残っている場合、家の扱いや返済の負担をどうするかが大きな問題になります。対応は慎重に検討しなければなりません。そこで本章では、離婚時に住宅ローンが残っている場合の対処法を解説します。
金融機関に問い合わせる
離婚時に住宅ローンが残っている場合、まずは金融機関に相談しましょう。住宅ローンの契約内容や条件により、名義変更やローンの借り換えが可能な場合もあります。現在の状況を金融機関に確認し、対応策を検討してもらいましょう。特に、名義変更を希望する場合、新たにローンを引き継ぐ側の収入や信用力を審査して承認されなければなりません。
もしできなければ、返済義務が元の名義人に残るため、慎重な判断が求められます。また、家を売却する場合やローンの残債を一括返済する場合の手続きも、金融機関の助言を仰げば最適な方法が見つかるかもしれません。返済条件の変更や負担軽減の可能性もあるため、まずは金融機関と相談し、現実的な選択肢を探りましょう。
住宅ローンを借り換える
離婚時に住宅ローンが残っている場合、ローンの借り換えで問題を解決できるかもしれません。これは、現在の住宅ローンを新しい契約に切り替えて、名義を変更したり、返済条件を見直す手段になります。特に、夫婦のどちらかが家に住み続ける場合、単独名義に変更するために、新たな住宅ローンを組み直す選択は有効です。
ただし、借り換えをおこなうためには、金融機関の審査を受けなければなりません。審査では、住宅ローンを引き継ぐ側の収入や勤務状況、信用情報などが厳しくチェックされます。現時点での返済能力が十分でない場合、審査に通らず借り換えが認められないかもしれません。
仮に、借り換えができても金利や返済期間が変わる可能性もあります。現在よりも低金利のローンに切り替えられれば返済負担を軽減できますが、反対に金利が上がると負担が増える場合もあるため、慎重に比較検討する必要があるでしょう。
加えて、借り換えには手数料や諸費用がかかるため、実施する場合はローン返済に加えて初期費用でまとまったお金を用意しなければなりません。さらに、夫婦がペアローンを組んでいる場合、双方のローンを整理しなければならず、手続きが複雑になる可能性があります。借り換えは有効な手段になりえますが、憂慮すべき点もあります。金融機関の担当者や専門家に相談しながら慎重に進めましょう。
名義人がそのまま1人で住み続ける
離婚後も住宅ローンの名義人がそのまま住み続ける場合、基本的には名義変更をおこなう必要がないため、金融機関との契約も変更せずに済みます。ただし、名義人が住み続けることを前提にした場合でも、将来的に再婚などの理由で住環境を変える場合には、あらためて所有権やローン負担の協議が必要でしょう。
また、住宅ローンをペアローンで組んでいる場合は注意が必要です。ペアローンは、夫婦双方がそれぞれローン契約を結ぶ仕組みになっているため、どちらか一方が住み続けた場合でも、もう一方のローン契約は残ります。この時、金融機関によっては「ペアローン契約時に双方が同居している」状態を条件としている場合があり、離婚後に片方だけが住み続けると契約違反になるかもしれません。違反と判断された場合、金融機関から残債の一括返済を求められたり、金利の引き上げなどのペナルティを科される可能性があるため、慎重に対応しましょう。
なお、元配偶者が連帯保証人になっている場合、そのままの契約を維持すると、名義人が返済できなくなった際に元配偶者へ返済義務がおよびます。新たな保証人の用意や審査が必要となるため、手続きが難航するかもしれませんが、金融機関に相談し、連帯保証人の変更または解除する手続きを進めましょう。
売却して得た利益でローンを完済する
離婚時に住宅ローンが残っている場合、家を売却して得た資金でローンを完済する方法が有効な手段になるでしょう。売却で住宅ローンの負担を解消し、夫婦間の財産関係を明確にできるため、離婚後のトラブルを防げるメリットがあります。
しかし、家を売却して得た代金を住宅ローンの返済に充てられる点はよいですが、ローンの残債と売却価格の関係によって対応が異なる点には留意が必要です。売却価格が住宅ローンの残債を上回る「アンダーローン」の場合は、売却益でローンを完済し、残った金額を財産分与できるため、問題は生じにくいでしょう。
一方で、売却価格がローンの残債を下回る「オーバーローン」の場合、売却してもローンが完済できず、残債の処理が問題となります。この場合、名義人が引き続きローンの返済を継続するか、不足分を自己資金で補わなければなりません。オーバーローンで売却を進める場合、任意売却も選択肢になります。これは、金融機関の同意を得たうえで市場価格よりも低い金額で売却し、残債は分割返済などの措置を講じる方法です。ただし、任意売却をおこなうと信用情報に影響を及ぼし、今後のローン審査に不利になるかもしれません。実行は慎重に判断するようにしましょう。
なお、売却後もその家に住み続けたい場合、「リースバック」も利用できます。これは、不動産会社などに家を売却したあと、買主と賃貸契約を結び、家賃を支払いながら住み続ける仕組みです。住宅ローンの負担をなくしながら、現在の住環境を維持できる点はメリットですが、売却価格が市場価格より低くなる傾向にあるため、慎重な検討が欠かせません。なおペアローンや連帯債務の場合、売却には双方の合意が必要となるため、早めに話し合い、手続きを進めましょう。
家を売却すると、住宅ローンの負担を解消し、固定資産税や維持費の支払いからも解放されます。さらに、財産分与が明確になり、離婚後の金銭トラブルを避けられる点はメリットです。ただし、対応には注意すべき点もあるため、慎重に検討しましょう。
離婚公正証書を作成する
離婚時に住宅ローンが残っている場合、トラブルを防ぐ手段に「離婚公正証書」を作成する方法があります。これは、公証役場で公証人が作成する公文書で、離婚後の財産分与や住宅ローンの返済義務、養育費などの取り決めを明確にするものです。
作成するには、夫婦双方が話し合い、合意した内容を文書にまとめ、公証役場に出向かなければなりません。必要な書類は、夫婦の身分証明書、住民票、財産に関する資料(住宅ローンの契約書や不動産登記簿謄本など)です。公証人が内容を確認し、法的に適切な文言に修正したのち、公正証書として認められます。
公正証書を作成すると、取り決めた内容に強制力が生まれます。住宅ローンの返済義務が履行されない場合、裁判を経ずに給与や預金を差し押さえられるなど、離婚後の金銭トラブルを防ぐ有効な手段になるでしょう。
作成時には、一方的に不利な内容にならないよう注意し、公証人だけでなく弁護士や専門家に相談するようにしましょう。また、住宅ローンの返済義務を負う側が将来的に返済困難になる可能性も考慮し、具体的な代替案を検討しておく必要があります。
住宅ローンが残ったまま離婚する際の注意点

離婚を考える際に住宅ローンが残っていると、その扱いが大きな課題になります。本来であれば、家を売却してローンを完済することが理想ですが、状況によってはローンを残したまま離婚せざるをえないケースもあるでしょう。
しかし、住宅ローンが残ったまま離婚すると、財産分与や返済義務、住居の権利関係など、さまざまな問題が発生する可能性があります。そこで本章では、住宅ローンを抱えたまま離婚する場合に注意すべき点を解説します。問題回避のチェックポイントを押さえておきましょう。
住宅ローンの返済で養育費・慰謝料を相殺しない
離婚後、家を出た側が住宅ローンの返済を続けるケースは珍しくありません。その理由として、「養育費や慰謝料の代わりに住宅ローンを負担する」が挙げられますが、この方法には大きなリスクがあります。
そもそも、住宅ローンの返済は、養育費や慰謝料とは本質的に異なります。養育費は子どもの生活や教育のための資金であり、慰謝料は離婚による精神的・経済的な損害を補填するもの。一方で、住宅ローンの返済は金融機関に対する債務の返済であり、元配偶者や子どもに直接支払われるものではありません。そのため、仮に住宅ローンを肩代わりしても、法的に養育費や慰謝料の支払いとみなされるとは限らず、将来的に未払い問題が発生する可能性があるでしょう。
また、家を売却してしまえば、住宅ローンの返済義務はなくなります。住宅ローンの返済をせずに済むと、結果的に養育費や慰謝料が途絶えてしまう要因になりかねません。一度、養育費や慰謝料の代わりを住宅ローンの返済で合意してしまうと、ローンが消滅した際にあらためて請求することが難しくなります。慰謝料の請求権は離婚から3年、養育費の請求権も最短で5年を過ぎると法的に認められなくなる可能性があるため、あとから支払いを求めても相手が応じないケースがあるかもしれません。
さらに、住宅ローンの返済を続ける側が経済的に困窮し返済が滞った場合、家の差し押さえや競売などの問題も発生する可能性があります。その結果、住んでいる側も不安定な状況に陥り、お子さんがいる場合子どもの生活にも悪影響をおよぼしかねません。
このようなリスクを回避するためにも、養育費や慰謝料は住宅ローンとは切り離し、現金で受け取るようにしましょう。そうすると、家の処分や経済状況の変化に関係なく、安定した支払いを受けられます。
元配偶者の連絡先を把握しておく
元配偶者の連絡先は確実に把握しておきましょう。住宅ローンが残っている限り、共同名義や連帯保証の問題がある場合、元配偶者と連絡を取らなければならないケースがあります。例えば、家を売却する際やローンの返済が滞った際、名義人全員の同意が必要となる場合があるでしょう。しかし、離婚後に元配偶者と連絡が取れなくなると、スムーズに手続きを進められなくなり、問題が生じるかもしれません。
また、住宅ローンの返済状況によっては、名義変更や借り換えを検討しなければならない場合もあります。元配偶者が住宅ローンの返済を続ける約束をしていても、万が一返済が滞ると、共同名義の場合はもう一方の名義人に影響がおよぶでしょう。そのため、離婚時には今後の住宅ローンの扱いを慎重に決め、必要に応じて契約内容の見直しや、元配偶者の連絡先を把握しておき、対応できるようにしなければなりません。
約束は公正証書にしておく
住宅ローンを残したまま離婚する場合、のちのトラブルを避けるために、取り決めを公正証書にして残しておきましょう。住宅ローンの返済義務や家の扱いを口約束で済ませてしまうと、あとになって「そんな約束はしていない」「返済ができなくなった」などと主張される可能性があり、大きな問題に発展しかねません。公正証書を作成すると、返済義務や財産分与の内容を明確にし、法的効力を持たせられます。
特に、住宅ローンの返済をどちらが負担するのか、返済が滞った場合の対応、家の所有権の扱いなどとともに、しっかり取り決めておくようにします。例えば、元配偶者がローンの返済をする取り決めをした場合、滞った際にどうするのか、名義を変更する予定があるのかなどを具体的に決め、公正証書に明記しておくと、のちのトラブルを防げるでしょう。
また、公正証書には強制執行認諾文言を付けると、万が一返済が滞った際に裁判を経ずに給与や財産を差し押さえる手続きが可能になります。これは、養育費や慰謝料の支払いを約束した場合にも有効です。公正証書を作成すると、返済が滞るリスクを減らし、安心して新たな生活をスタートできるでしょう。
住宅ローンがある場合の離婚に関するよくある質問
住宅ローンがある場合の離婚に関するよくある質問をまとめました。
住宅ローンが残ったままでは離婚できない?
住宅ローンが残っていても離婚自体は可能ですが、手続きや話し合いなど、しなければならない対応が多く複雑になります。その煩わしさが、「住宅ローンが残っていると離婚ができない」と言われるゆえんです。住宅ローンの名義変更は難しく、金融機関の審査が厳しいため、単純に離婚しただけでは名義変更が認められないでしょう。共同名義の場合も再審査が必要で、片方のみでは審査基準を満たさない可能性があります。
また、住宅ローンに連帯保証人がいる場合、その変更も簡単ではありません。新たな保証人を見つける際には、困難が生じる場合があります。さらに、家の所有権をめぐるトラブルや、不動産の売却、相続時に問題が生じるかもしれません。共同名義の不動産は、一方の同意なしには売却や活用ができず、将来、相続人との間で予期しない問題が発生する可能性もあります。離婚時に住宅ローンが残っていると、返済や所有権の問題で元配偶者との関係が続く場合があり、慎重な対応が求められるでしょう。
住宅ローンが残ったまま離婚する場合の対処法は?
まず、金融機関に相談し、名義変更やローンの借り換えが可能かを確認しておきます。そのまま住み続ける場合、契約違反のリスクもあるため、慎重に対応しましょう。また、家を売却してローンを完済する方法も有効ですが、売却価格が残債を下回る場合、自己資金で補う必要があります。離婚公正証書を作成し、返済義務や財産分与の取り決めを法的に明確にしておくことも有効な手段です。将来的なトラブルを避けるため、知識を得てあらかじめ準備を整えておきましょう。
住宅ローンが残ったまま離婚する際の注意点は?
まず、養育費や慰謝料の代わりに住宅ローンを返済することは避けましょう。万が一、家を売却する場合、ローンの返済がなくなると、慰謝料や養育費を満額もらえない可能性があるからです。次に、元配偶者の連絡先を把握しておくようにしましょう。返済の滞りがあった場合に連絡が取れなければ、家を失うリスクがあります。さらに、住宅ローンの返済義務を相手に負わせる場合は、公正証書を作成するとよいでしょう。そうしておけば、相手が約束を破った場合でも、強制的に履行させられます。公正証書は離婚前に作成することが一般的で、将来的なトラブルを避けるために重要です。
まとめ
住宅ローンが残った状態でも離婚は可能ですが、家の扱いを慎重に決める必要があります。名義変更の難しさ、共同名義の問題、ローンの返済義務、連帯保証人の影響など、考慮すべき点が多く、安易に決めるとのちのトラブルになるかもしれません。また、養育費や慰謝料の代わりに住宅ローンを返済すると、家を売却した際に支払いが途絶え、相手に不利益を与えてしまう可能性もあるため注意が必要です。問題なくスムーズに手続きができるよう、本記事で解説したポイントを押さえ、円満な解決を目指しましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ