夫婦間で住宅ローンの名義変更はできる?7つの注意点を紹介!
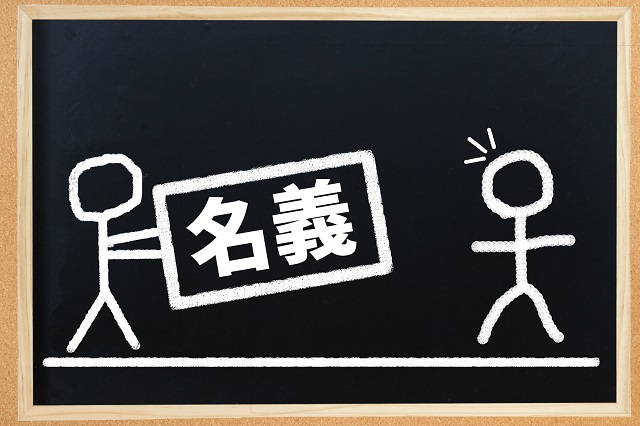
原則、夫婦間であっても住宅ローンの名義変更はできませんが、金融機関が定める一定の条件を満たすことで名義変更ができる可能性があります。
どのようなケースで住宅ローンの名義変更ができるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
本記事では住宅ローンの名義変更ができる条件や、名義変更ができない時の対処法を解説します。
記事の目次
住宅ローンの名義人変更は原則できない

住宅ローンは、契約者の収入や信用情報などをもとに金融機関が審査をおこなっているため、離婚などの諸事情があっても、原則は夫婦間でも名義変更ができません。
夫婦間でも名義変更ができない理由として、住宅ローンの契約者が変更されると金融機関のリスクが発生します。
新しい契約者に現在の契約者が持っている信用情報や、安定した収入がないと、金融機関は債権を回収できません。
しかし、新しく名義人になる人が現在の契約者と同等かそれ以上の返済能力があり、今後も安定した収入が見込めると金融機関に判断されれば、名義変更できる可能性があります。
ただし、名義変更できるかは金融機関の判断となり、配偶者が専業主婦だと名義変更できない可能性が高いです。
まずはご自身の状況に合わせた最適な解決策を見つけるために、金融機関に相談しましょう。
住宅ローンの名義人変更ができない時の3つの対処法

金融機関の判断によって、現在の住宅ローンでは名義変更ができない場合、以下の3つの対処をする必要があります。
- 住宅ローンを完済する
- 住宅ローンの借り換えを検討する
- 住宅を売却する
順番に解説します。
住宅ローンを完済する
1つ目は、住宅ローンを完済することです。
住宅ローンの返済がなくなれば、名義変更の問題もおのずとなくなります。
しかし、残債の金額によっては一括で完済できないケースもあるでしょう。
一括で完済できない場合には、ローンの完済まで待つ必要があります。
また、離婚の場合、夫が住宅ローンの契約名義人であれば金融機関から返済の請求をされるのは夫であるため、離婚をしても夫が返済を続けなければなりません。
ただし、妻が住み続ける場合には夫が返済をするのではなく、妻が夫名義の口座に入金をすることで支払いの問題は解決できるでしょう。この場合、金額によっては贈与税の対象となる可能性があるため、入金する金額には注意が必要です。
住宅ローンの借り換えを検討する
2つ目は、住宅ローンの借り換えを検討することです。
住宅ローンの借り換えをすれば、新しい契約者が残債を引き継ぐことになるため、名義変更が可能です。
また、借り換えをするメリットとして、現在の住宅ローンよりも好条件で借りられる可能性があります。
借り換えをするのに手数料などはかかりますが、金利や返済期間によっては月々の返済額や総返済額の負担を軽減できます。
ただし、借り換えをする際には新しい金融機関の審査が必要になるため、返済能力がないと判断されると借り換えが実行できない点は注意点として覚えておきましょう。
住宅を売却する
3つ目は、住宅を売却することです。
住宅ローンの一括返済や借り換えが難しい場合は、住宅の売却を視野に入れましょう。
しかし住宅を売却した資金で住宅ローンを完済できないと、住む家がなくなってしまうだけではなく、返済も残ることになります。
返済が残りながら、次の家に住むための引越し費用を捻出する必要が出てきてしまいます。
住宅の売却を検討する際は、まず複数の不動産会社に売却査定を依頼し、売却の時期なども相談するとよいでしょう。
住宅ローンの名義変更をする際の7つの注意点
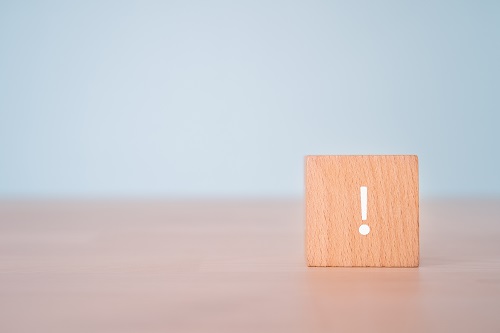
住宅ローンの名義変更をする際の注意点は、以下の7つです。
- 金融機関によって名義変更するための条件が異なる
- 審査に通過しない可能性がある
- 住宅の名義変更をする必要がある
- 金利の変動リスクを考慮する
- 無断で不動産の名義変更をするのは契約違反になる可能性がある
- 手続きに費用がかかる
- 贈与税が発生する可能性がある
順番に解説します。
金融機関によって名義変更するための条件が異なる
名義変更の手続きや条件などは、金融機関によって異なります。
具体的には、収入や信用情報、勤続年数などです。
離婚による名義変更では、離婚届などの証明書の提出が求められることもあるでしょう。
住宅ローンの名義変更に関する詳細な条件や手続きは、各金融機関の担当者へ事前に相談することが大切です。
スムーズな名義変更を実行するためにも、早めに相談しておきましょう。
審査に通過しない可能性がある
住宅ローンの名義変更や借り換えをする際は、金融機関による審査がおこなわれます。
新しい名義人が住宅ローンの債務を引き継ぐことになるため、金融機関は新たな債務者に返済能力があるか確認する必要があります。
住宅ローンの名義変更や借り換えでおこなわれる審査の、項目の一例は以下のとおりです。
- 収入
- 不動産の担保評価
- 健康状態
審査に通過しないと名義変更が実行できないため、名義変更を検討する際は審査項目を事前に確認しておくとよいでしょう。
住宅の名義変更をする必要がある
住宅ローンの名義変更をする際には、住宅の名義変更もおこなわなければなりません。
原則、住宅ローンの名義人と住宅の名義人、入居者が一致している必要があります。
たとえば、住宅の名義人が夫で、住宅ローンの名義人を妻に変更することはできません。
つまり、住宅ローンの名義人を妻に変更するためには、住宅の名義人も妻に変更する必要があります。
住宅ローンの名義変更をする際には、住宅の名義変更も必要になる点は、覚えておきましょう。
金利の変動リスクを考慮する
住宅ローンの名義変更をできない時は借り換えを検討するのがおすすめですが、借り換えをする際には金利の変動リスクを考慮する必要があります。
現在の住宅ローンよりも低い金利で借り換えができれば、月々の返済額や総返済額の負担を軽減できますが、金利が高くなることもあります。
金利が0.5%高くなった際のシミュレーションを見てみましょう。
| 金利1.0% | 金利1.5% | |
|---|---|---|
| 月々の返済額 | 8万4,685円 | 9万1,855円 |
| 総返済額 | 3,556万7,804円 | 3,857万9,007円 |
※借入額3,000万円、返済期間35年想定
つまり、住宅ローンの借り換えをする際に金利が1.0%から1.5%に上がることで、月々の返済額が約7,000円、総返済額が最大約300万円増えます。
借り換えをする時期によって総返済額が変動する点には、注意が必要です。
借り換えをする金融機関のプランによっては大きな支出となってしまうため、低金利で借り換えができる金融機関を選択しましょう。
無断で不動産の名義変更をするのは契約違反になる可能性がある
住宅ローンを完済せずに、金融機関に無断で住宅の名義変更をすると、金銭消費貸借契約の契約違反となる可能性があります。
住宅ローンを組む際に締結する金銭消費貸借契約書に、不動産の名義変更をする際には金融機関の承諾が必要である旨記載されていることが多いです。
そのため、金融機関に無断で住宅の名義変更をすると金銭消費貸借契約の契約違反となり、残債の一括返済を求められたり、住宅が競売にかけられたりする可能性があります。
金融機関から住宅の名義変更の承諾をえることは困難なケースが多いですが、無断でおこなうとリスクが発生するため、事前に相談しておきましょう。
手続きに費用がかかる
先述したとおり、住宅ローンの名義変更をする際には住宅の名義変更もする必要があります。
住宅ローンと住宅の名義変更、借り換えをする際に発生する費用は、以下のとおりです。
- 印鑑証明書
- 住民票
- 固定資産税評価証明書
- 戸籍謄本
- 司法書士の手数料
- 融資手数料
- ローン保証料
- 火災保険料
- 地震保険料
- 印紙税
- 登記費用
書類の発行にかかる数百円のものもあれば、数十万円かかるものもあります。
それぞれにかかる費用を事前に確認し、資金計画を立てたうえで住宅ローンの名義変更をしましょう。
贈与税が発生する可能性がある
住宅ローンの名義変更をする際には、贈与税が発生する可能性があります。
先述したとおり離婚の場合、夫が住宅ローンの契約名義人であれば金融機関から返済の請求をされるのは夫であるため、離婚をしても夫が返済を続けなければなりません。
住宅ローンの契約名義人以外が住宅ローンの返済をすると、贈与税の課税対象となります。
ただし、後述する非課税となる制度もあるため、有効活用しましょう。
住宅ローンに関連する贈与税を非課税にするには?

住宅ローンに関連する贈与税を非課税にするには、年間の贈与額を110万円以下にする必要があります。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。
引用:国税庁
つまり、年間に受け取る金額が110万円以下であれば、贈与税が非課税となります。
ただし、夫婦間だけではなく親子間や兄弟間で受け取った費用の合計値が110万円以下である必要があるため、注意が必要です。
贈与された金額が110万円を超えると、以下の贈与税率が課税されます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
引用:国税庁
たとえば、住宅ローンの契約者が夫で、妻が頭金を250万円負担すると、基礎控除額である110万円を差し引いた140万円に対して課税されます。
つまり、贈与税は14万円です。
贈与する金額に応じて税率が変動するため、贈与する金額には注意しましょう。
住宅ローンを組む際の贈与税を回避する時の3つの注意点

住宅ローンを組む際の贈与税を回避する時の注意点は以下の3つです。
- 贈与のタイミング
- 物件に居住するタイミング
- 贈与税が0円でも申告が必要
順番に解説します。
贈与のタイミング
1つ目の注意点は、贈与のタイミングです。
住宅取得等資金の非課税特例制度を利用して贈与税を回避するためには、住宅ローンを組んで購入した住宅に居住する前に贈与を受ける必要があります。
居住してから贈与を受けてしまうと、住宅取得等資金の非課税特例制度の要件を満たさなくなるため、贈与税の課税対象となります。
住宅取得等資金の非課税特例制度を利用する際には、贈与をするタイミングには注意しましょう。
物件に居住するタイミング
2つ目の注意点は、物件に居住するタイミングです。
住宅取得等資金の非課税特例制度を利用する際には、基本的に贈与を受けた年の翌年3月15日までに物件に居住する必要があります
ただし、災害によってやむを得ず居住することができない場合などは、贈与を受けた年の翌年12月31までに居住すれば制度が適用されます。
詳しく知りたい人は、国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を確認しておきましょう。
贈与税が0円でも申告が必要
3つ目の注意点は、贈与税が非課税になっても申告が必要なことです。
先述したとおり、たとえ夫婦間の贈与であっても贈与税がかかることがあり、一定額以上の贈与をおこなうと、贈与税の申告が必要です。
夫婦間での贈与には特別控除があるため、一定額以下の贈与は贈与税がかかりませんが、贈与税の申告漏れがあると加算税や延滞税を請求される可能性もあります。
そのため、贈与税の課税対象となる際には、贈与税の申告をおこない、税務署からの督促に備えることが大切です。
贈与税の申告期限は、贈与をおこなった年度の翌年1月1日から3月15日までとなっています。
自分が贈与税の課税対象となるか判断ができない場合には、税理士や税務署に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
住宅ローンの名義変更は原則できませんが、金融機関が定める一定の条件を満たすことで名義変更が可能となります。
ただし、多くの場合は住宅ローンの借り換えをすることになります。
借り換えをする際にも多くの注意点があるため、ご自身で判断できない場合は、まずは金融機関に相談しましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ





