根抵当権とは?抵当権との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説

本記事では根抵当権とはどのような権利を指すのか、基礎知識について解説していきます。根抵当権を設定・抹消する際の手順やよくある質問も紹介しますので、根抵当権について知りたい方はぜひ参考にしてください。
記事の目次
根抵当権は「抵当権」の一種

根抵当権は、いわゆる抵当権の一種で異なる権利です。同じ担保権ではありますが、通常の抵当権とは別の性質を持ちます。では、具体的に根抵当権とはどのような権利のことをいうのか以下で解説していきます。
そもそも抵当権とは?
根抵当権よりも耳にする機会の多い「抵当権」とは、住宅ローンを利用して購入する不動産に対して金融機関が設定する権利のことです。住宅ローンの返済ができなくなった時、金融機関は抵当権を設定した不動産を差し押さえることができます。
一方、住宅ローンを完済した場合は、抵当権を抹消することが可能です。抵当権が抹消されないと、対象不動産の売却に支障が出てくるため注意しましょう。抵当権に関する詳細は、以下の記事を参考にしてください。
根抵当権とは?
根抵当権とは、継続的取引などによって生じる不特定の債権を、あらかじめ定めた限度額を上限に担保する抵当権のことです。設定金額の範囲内で繰り返し借入・返済ができ、企業や経営者が事業性の資金の担保として利用するケースがほとんどです。担保する債権が特定されないのが特徴の一つで、根抵当権を設定するには担保する債権の範囲や債務者を定める必要があります。
一般の住宅ローンで設定することは少ないものの、近年では「リバースモーゲージ」などで取り扱う金融機関が増えつつあります。
根抵当権の「極度額」とは?
極度額とは、根抵当権によって担保される債権の上限額のことです。根抵当権の設定には極度額を定める必要があります。極度額は、不動産の評価額の範囲内で設定されるのが一般的。また、極度額は利害関係者の承諾を得たうえであれば、増減の変更も可能です。
抵当権と根抵当権の違い
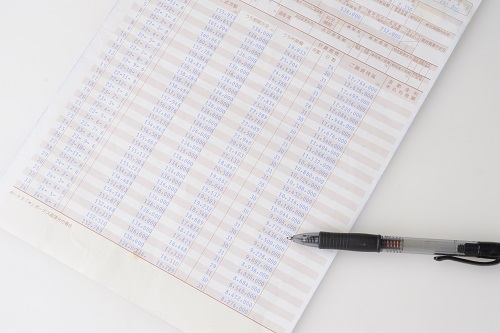
抵当権と根抵当権の特徴を理解したうえで、具体的にどのような違いがあるのか把握しておきましょう。以下では抵当権と根抵当権を比較し、抵当権との違いについて解説していきます。
合意がないと消滅しない
抵当権は債務を完済した時点で抹消され、抹消登記をおこなうことが可能です。一方で、根抵当権は債務を完済しても消滅せず、債権者との合意が必要になります。債務を完済して根抵当権の利用が今後もない場合は、債権者の合意を得て抹消手続きを進めましょう。
対象となる債権が限定されない
住宅ローンを組む場合などの抵当権は不動産の購入価格が決まっているため、借入金額や返済期間など購入対象となる債権が明確です。一方、根抵当権は極度額を定めるものの、借入金額・返済期間は都度設定することになるため、債権が限定されません。対象となる債権が限定されない代わりに、被担保債権となりえる債権の範囲が定められています。
繰り返し借入が可能
先述のとおり、根抵当権は設定した極度額の範囲内であれば、繰り返し借入することが可能です。抵当権の場合、融資を追加で受けるには再度審査や手続きが必要になるのに対し、根抵当権であれば審査等の手続きは必要ありません。そのため、ある程度まとまった金額が繰り返し必要となる事業用途の融資で、根抵当権を設定するケースが多いでしょう。
許可なく権利を移譲できない
抵当権は借入(返済)金額や返済期間が定まっているため、債権者は債務者の許可なく権利を移譲できます。しかし、根抵当権の場合は元本確定前において、債務者の承諾を得なければ権利を移譲することができません。根抵当権は、抵当権のように返済金額などの債権の内容が明確になっていないことが要因です。
連帯債務者を設定できない
連帯債務者は、債務者と同様に返済義務を負う人のことをいいます。抵当権は連帯債務者を設定できますが、根抵当権の場合は連帯債務者を設定することができません。繰り返し借入・返済ができる根抵当権は返済額や期間が不明確であることから、連帯債務者を設定するのが難しいためです。
優先弁済の範囲が異なる
根抵当権によって優先弁済を受けられる範囲は、確定した元本や利息、遅延損害金などの全部が極度額までとされています。優先弁済とは、ほかの債権者に優先して債務者の財産から弁済を受けられることです。抵当権では、元本は優先的に弁済を受けられますが、利息やその他については満期となった最後の2年分のみ優先弁済を受けることができます。
根抵当権のメリット
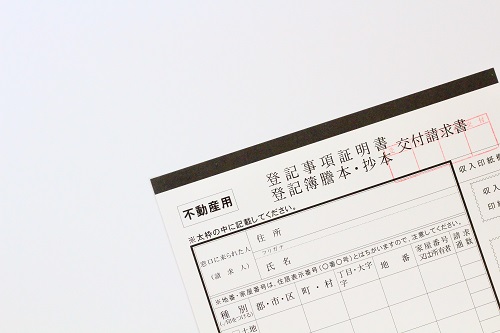
根抵当権には上述のような特徴があります。それでは、根抵当権を設定することでどのようなメリットを享受できるのか、以下で確認しましょう。
登記にかかる手間や費用を削減できる
根抵当権の場合、登記の手間や費用を削減することが可能です。通常、抵当権や根抵当権は設定・抹消するために、登記簿謄本(登記事項証明書)への登記手続きが必要です。登記手続きには登録免許税や司法書士報酬などの費用が発生するほか、必要書類を揃えるなどの手間がかかります。一般的には複数回の借入・完済をするとその都度登記をすることになりますが、根抵当権の場合は一度登記手続きをおこなえば、繰り返し借入・完済をしても登記の手間が発生することはありません。
極度額の範囲で借入が可能
極度額の範囲内で繰り返し借入が可能な点は、根抵当権の大きな特徴でありメリットともいえるでしょう。一度借入をおこなえば、2回目以降の借入に手間がかからないため、スムーズに資金調達ができます。また、極度額の範囲内で資金用途や金額を分けられる点も便利です。
根抵当権のデメリット・注意点

根抵当権にはメリットがある一方で、デメリットも存在します。デメリットを把握することで対処できることもあるので、注意点として確認しておきましょう。
借入先を変更しづらい
根抵当権は、債権者の許可が下りない限り借入先を変更することができません。抵当権は債権者との交渉は必要なく、完済することで権利を消滅させることが可能です。一方で、根抵当権の場合は完済して借入先を変更しようと考えても、解約するには債権者との合意を得る必要があります。債権者にとって、顧客である債務者を手放したくないと解約を拒む可能性もあるでしょう。
根抵当権が設定されたままだと売却が難しい
根抵当権が設定されたままだと、不動産の売却が難しい傾向にあります。根抵当権が設定されている状態の不動産を売却することは可能ですが、借入が残っていない場合でも「担保となっている不動産」とみなされるため、購入する方はほとんどいません。また、根抵当権は自動的に消滅しないため、解約や抹消手続きが必要となり、債権者との交渉をおこなうなど売却までに時間がかかることも考えられます。
根抵当権を設定する場合の手順
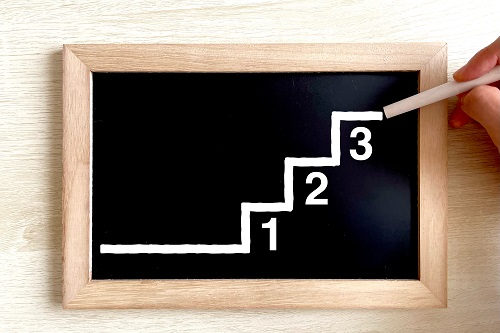
ここからは、根抵当権を設定する際の2つの手順について解説していきます。主な手順は以下のとおりです。
- STEP 1根抵当権設定契約を締結する
- STEP 2設定登記を申請する
根抵当権を設定する際に必ずおこなうことなので、しっかり把握しておきましょう。
根抵当権設定契約を締結する
まずは、債務者(根抵当権設定者)と債権者(根抵当権者)との間で根抵当権設定契約を締結することになります。契約では、「不動産の表示」「被担保債権の範囲・極度額」「元本確定期日」「根抵当権の設定登記手続き」などを定めます。
設定登記を申請する
根抵当権設定契約を締結したら、設定登記の申請をおこないましょう。不動産の所在地を管轄する法務局や地方法務局で、契約締結日と同日におこなうのが一般的です。登記申請の際は、登記原因証明情報や登記済権利証または登記識別情報、本人確認書類などの必要書類が複数あるため、事前に準備しておきましょう。また、必要書類に加えて申請費用もかかるため、司法書士に依頼する場合などは見積書を確認しておくことが大切です。
根抵当権を抹消する場合の手順

次に、根抵当権を抹消する場合は以下の手順でおこないましょう。
- STEP 1金融機関(債権者)に交渉する
- STEP 2元本確定をおこなう
- STEP 3抹消手続きを完了させる
それぞれ詳しく解説していきます。
金融機関に交渉する
根抵当権の抹消するために、まずは契約を解除したい旨を金融機関(債権者)に交渉しましょう。継続的取引を求めるために抹消の交渉に応じてもらえないケースもありますが、一般的には解約に応じてもらえます。元本が多く残っていて完済が難しいと判断された場合は、交渉により「任意売却」という選択も考えられます。
元本確定をおこなう
債権者との交渉がまとまったら、次に元本確定をおこないましょう。元本確定とは、設定金額内での借入を止めて、その時点でいくらの金額を返済する義務があるのか確定することです。元本確定をおこなうと、根抵当権は通常の抵当権に代わり、被担保債権を完済することで抵当権が消滅します。
抹消手続きを完了させる
根抵当権の抹消手続きを完了させるには、必要書類を揃えて法務局で抹消登記をする必要があります。根抵当権の消滅に関する合意書や、根抵当権設定契約書、登記済権利証または登記識別情報などの書類を準備しておきましょう。設定時と同様、抹消登記の申請の際にも登記費用がかかる点には注意が必要です。
根抵当権の設定・抹消にかかる費用

先述のとおり、根抵当権の設定や抹消の際には費用が発生します。どのような費用がかかるのか、それぞれ以下の表を参考にしてください。
| 根抵当権の設定時 | 根抵当権の抹消時 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 極度額×0.4% | 1つの不動産につき1,000円 (土地と建物で2,000円) |
| 司法書士報酬 | 3万円程度 | 1万~3万円程度 |
| その他費用 (書類取得など) |
1,000~2,000円程度 | 2,000~3,000円程度 |
根抵当権に関するよくある質問
最後に、根抵当権に関するよくある質問について回答します。簡潔に理解したい場合は、以下を確認しましょう。
根抵当権を抹消しなくても不動産売却は可能?
根抵当権を抹消しなくても、不動産の売却自体は可能です。ただし、担保となっている根抵当権がついたままの不動産を好んで購入する方はいないため、売却は難しいといえるでしょう。また、不動産を売却したいからといってすぐに抹消手続きができるかはわかりません。そのため、確実に抹消できるよう、金融機関との交渉を先に進めるのがおすすめです。
根抵当権を抹消しないままだとどうなる?
根抵当権を抹消しないままだと、不動産の売却が難しくなります。また、根抵当権が抹消されていない不動産が相続となった場合、相続人の負担が多くなってしまうでしょう。たとえ完済しても根抵当権自体は消滅しないため、根抵当権を利用する予定がなくなったら、抹消手続きまでおこなうことが大切です。
住宅ローンの借入時に根抵当権が設定されるケースは?
一般的に、法人等が事業資金として借りる場合に設定されるケースが多い根抵当権ですが、住宅ローンの借入時にも利用されることがあります。主に高齢者を対象としたリバースモーゲージを利用する場合や、完成までに着手金や中間金などの支払いが複数回発生する注文住宅を建てる場合などです。
まとめ
今回は根抵当権の特徴や抵当権との違い、根抵当権を利用する際のメリット・デメリット、手順などについて解説しました。根抵当権は事業資金として企業が借入することが多く、一般的には個人の方が利用するケースが少ないものの、なかには住宅購入時に根抵当権の設定が求められるケースもあるでしょう。住宅ローンの借入時に根抵当権を設定する際は、通常の借入とは異なるため、抵当権との違いをしっかり把握しておくことが大切です。加えて注意点も理解したうえで、住宅購入時にも根抵当権を有効に活用しましょう。
物件を探す





